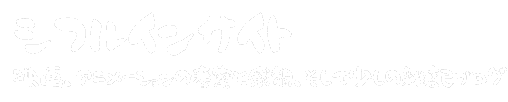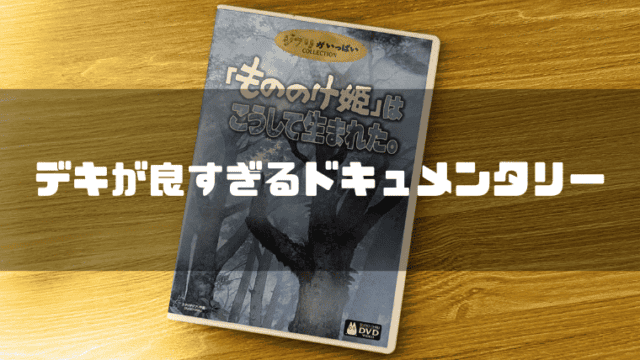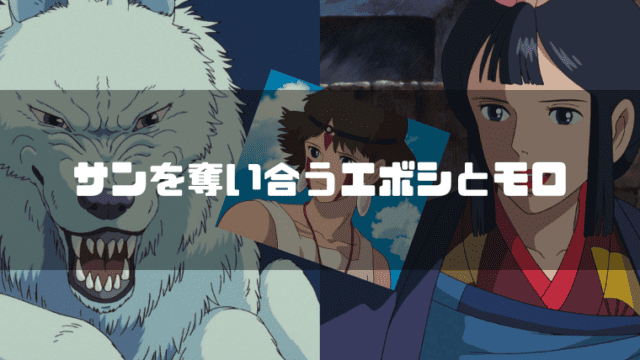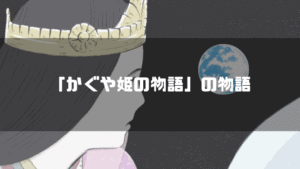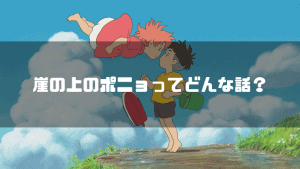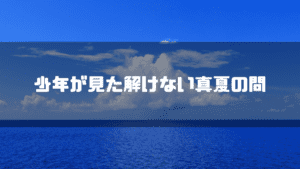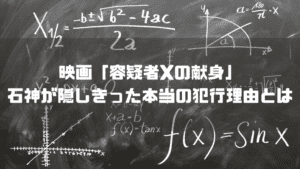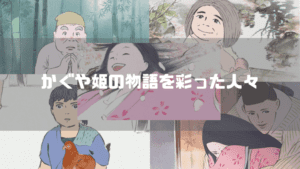「もののけ姫」は1997年に公開された宮崎駿監督による劇場用アニメーションである。
今回はその登場人物であるアシタカについて考えていこうと思。特に「主人公」としてのアシタカの側面に焦点を当てていく。
「もののけ姫」の主人公が誰であるかに関してはある程度意見が分かれるところかもしれないが、個人的にはアシタカであると思う。それは、宮崎駿監督が考えていた「アシタカセッキ」(「セッキ」は監督の造語で草に埋もれて耳から耳へ伝えられた物語という意味)というタイトルからも主人公がアシタカであると考えられるが、それ以外にも、本編中のアシタカの描写を見ると、明らかにアシタカには他の登場人物と違う点が見られることがわかる。
今回はアシタカvsその他の登場人物という形で双方の差を見ながら、「主人公としてのアシタカ」を語っていこうと思う。
まずは「主人公」としてのアシタカ以外の登場人物たちについて振り返ろうと思う。彼らは「本音をひた隠しにする人々」である(序盤のアシタカもこれに含まれている)。
「もののけ姫」における本音をひた隠す人々
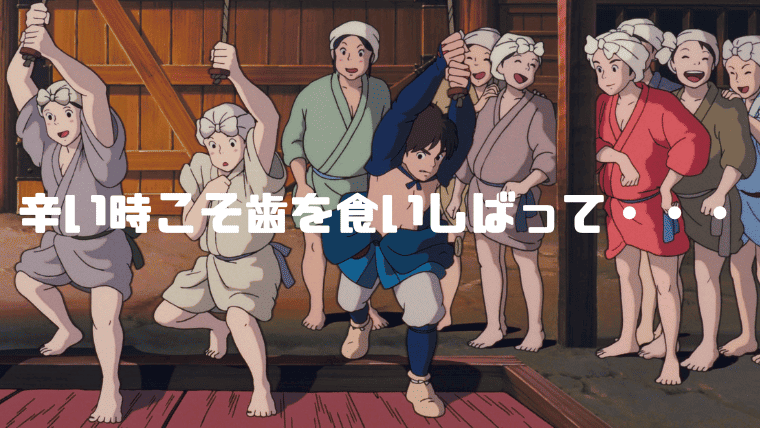
腹黒いジコ坊
「もののけ姫」の作中、その本音を最初に、明確に、隠したのはジコ坊だろう。
ジコ坊はアシタカから石火矢の礫を見せられた段階で、すべての状況を把握していたはずである。ところが彼がその礫について語ったことは特になく、アシタカの口から出た「巨大な猪」という表現にのみ反応し「シシ神の森」の存在を伝えた。
このときのジコ坊の内面を推察すると、
- 命の恩人なので情報は与えたやりたが、
- 自分の「仕事」に関わることは教えたくないし、
- 石火矢の話をすると自分の印象が悪くなる
と言ったところだろうか。何れにせよ、彼は知っていることを全ては話さない人物であることがわかる。
辛苦の過去を持つエボシ御前
「もののけ姫」の中心人物であるエボシ御前もその内面の真実を隠しきった一人だろう。
本編を見ているだけではわからないのだが、エボシ御前には「海外に売られ、倭寇の頭目の妻にさせられていた」という辛苦の過去がある(参照「もののけ姫はこうして生まれた」)。エボシ御前はその中で頭角を現し、ついには倭寇の頭目に復讐を果たして当時の部下であったゴンザとともに日本に帰ってきたのである。
これは本編を見ているだけではわからない事実であるし、エボシ御前もことさらにそのことを人に話してはいないだろう。
そんなエボシ御前が隠している内面の真実とは、そのような過酷な人生を自分に強いた世界(男たちが作った世界)そのものに対する強烈な復讐心である。
本編内でその復讐心が本人から語られることはないが、エボシ御前の「秘密の庭」にいた病者が次のように語っていた:
「コワヤ、コワヤ。エボシさまは国崩しをなさる気だ。」
この台詞は極めて冗談めかして語られているし、本編を見ても、石火矢の改良は「タタラバの自衛力を高めるため」にしか見えない。
しかし、この病者の台詞はエボシ御前の本心を代弁したものだろう。エボシ本人がその軽口になんの反応もしていないのが一つの根拠となるだろう。
まとめるならば、エボシ御前が表に出さなかった内面の真実とは、
- 自らが受けた過去の苦しみ、
- この世界をひっくり返そうという野望
ということになる。
自分を否定し続けるサン
ジコ坊やエボシ御前に比べると、サンには秘めた内面の秘密がないようにも思えるのだが、私の目には内に秘めた本音があったように思える。
ただ、基本的には別にサンの言動には矛盾がなく単に「自然を壊す人間を攻撃する」という人物に見える。
サンさんの出自に関して詳しいことはわからないのだが、モロの君の口から次のように語られている:
「森を侵した人間が、我が牙を逃れる為に投げてよこした赤子」
このような状況の中、サンはモロに育てられたのだから「森の民」として人間と対立することは自然に思える。しかし、サンの「自分は山犬である」という自意識は過剰に思えることもない。
「自分がありたい自分でない」ときにこそ人はそうであろうと暴走するのが常と考えるなら、サンは「自分が人間である」ということを誰よりも自覚していたということになるだろう。
その上で、自分を育ててくれたモロへの自然な愛情、自分が育った森への自然な愛着がサンの行動原理となり、それこそ「原理主義者」としての「山犬」に自らのアイデンティティを求めた。
つまり、彼女が表に出さなかった悲しき本音は、「私は人間であるという自覚」ということになるだろう。
そのように考えるとき、物語の終盤、シシ神が暴走した後にサンがアシタカに放った「私は山犬だ!」という魂の叫びに胸を打たれるのである。「胸を打たれる」という表現はなんとも陳腐ではあるが。
人間を憎みきれないモロの君
サンの育ての親であるモロの君も、実のところ本音を隠している存在に思える。
その根拠は「赤子のサンを育て上げた」という事実そのものに求めることができるだろう。
モロの君が真に、心の底から人間を憎んでいるのなら、人間であるはずのサンを育てることはなかっただろう。たとえサンが赤子だったとしても。というより、赤子であるからこそ殺すべきである。
しかしモロの君はそうしなかった。
つまり、モロの君が人間と対立しているのは、人間、特に「たたら製鉄」に携わる人々と自分たちの生活が矛盾するから仕方がなく対立しているということになる。
ただ、「もののけ姫」本編のモロの君にはそんな「仕方がなさ」が全く感じられなかった。
その理由はなにかと考えると・・・「サンの存在」が理由になるだろう。
つまり、モロの君は現状の致し方ない対立として人間と戦っているが、自分が大事に育てた娘であるサンはそれとは無関係に人間を憎んでいる。それに加えて、人間として生まれながら誰よりも山犬であろうとしているその気持がわかってしまう。モロの君は本当にサンの親なのである。
そのような状況下、モロの君の人間に対する攻撃性は明確で一直線なものにならざるを得なくなったのだろう。モロの君は自らの娘の苛烈な思いに寄り添ったのである。
ここからは流石に考えすぎということになるが、モロの君は、立派に育ったサンが人間と「森の民」との間に立ってくれることをわずかに願ったのかもしれない。しかし、森で育ったサンはむしろ自分たちに対して極端な帰属意識を持つことを自らのアイデンティティとしてしまった。そんなところに現れたのがアシタカであり、彼は自らの集落を追われ、生き場所がない存在であるという状況下、人間と「森の民」との共存の方法を探ったのである。モロの君としても自らの娘を託す価値があると考えたのだろう。
苛烈な労働に耐えるタタラバの人々
実のところ、タタラバの人々、少なくともタタラの吹子(ふいご)を踏んでいた女性たちも本音を隠している。
「もののけ姫はこうして生まれた」というドキュメンタリーを見ると、このシーンの作画担当したアニメーターに対して宮崎監督が次のように指摘しているシーンがある
辛いだろうから、辛く書けば良いというのは、あまりにも単純で、辛いということが前提になっている上で、なおかつ・・・マラソン選手がね、倒れる寸前にそういう顔するかって言ったらこらえるから・・・でしょ。そんなに、こう歯を食いしばってこらえてなきゃ続かないような仕事、長時間やってればつらくなるけど、そのときに逆に、もうろうとしてきたら辛いかをするよりも無表情になるだろう。
つまり、吹子(フイゴ)を踏んでいる番子の女性たちはどれほどつらくてもその辛さを表に出さず(あるいは出したくても出すことなく)、吹子を踏み続けているのである。
吹子を踏むのは苛烈な仕事ではあるが、「タタラバ」に来る前の状況のほうがよっぽどつらい状況であり、それによって生活ができるということの感謝の念の方が大きいのである。さらに、そういった辛さの中にいるのは別に自分たちだけではないとう自覚もあるのだろう(世界中の人間がなにかしら苦しんでいる)。
このように考えると、「タタラバ」の人々がアシタカを受け入れた理由には次の2つのことがあるように思える:
- 牛飼の仲間を救ってくれたこと、
- そして、こんなところに一人で来たという事実
「タタラバ」の人々は、傷ついた人々である。だからこそ、そこに行き着いた「傷ついた人」を受け入れるのである。
そしてきっとそれは、エボシ御前がしてくれたこと
だのだろう。
追放されたアシタカヒコ
この記事の主目的は「主人公」としてのアシタカを考えることであり、そのためにこれまで書いてきた「本音を隠した人々」との対比を行おうとしているのだが、実のところアシタカもその本音を隠していた。
少々矛盾があるようだが、アシタカは序盤ではその他の人々と同じであり、その後「主人公」になっていくという過程を踏んでいることになる。
では、彼が隠した本音とはなにか?それはどう考えても「故郷を追放されたことに対する悲しみ、苦しみ、悔しさと呪いという絶望」だろう。
彼がその内面に救う思いを完全に隠しきったのが、「私もだ、いつもカヤを思おう」という一言を残しで故郷を去った名シーンである。
あのときアシタカは、呪いによる死の恐怖や追放の絶望の中にいた。これからどうすればいいのかも分からずただただ西へ向かうのである。そんな苦しい状況の中で、自分を思い見送りに来てきたカヤの恩義に報いるために、彼は満面の笑みを見せたのである。
「もののけ姫」に登場する人々は、人生で一番つらいときに、最高の笑顔を他者に見せる人々なのである。
「主人公」としてのアシタカ
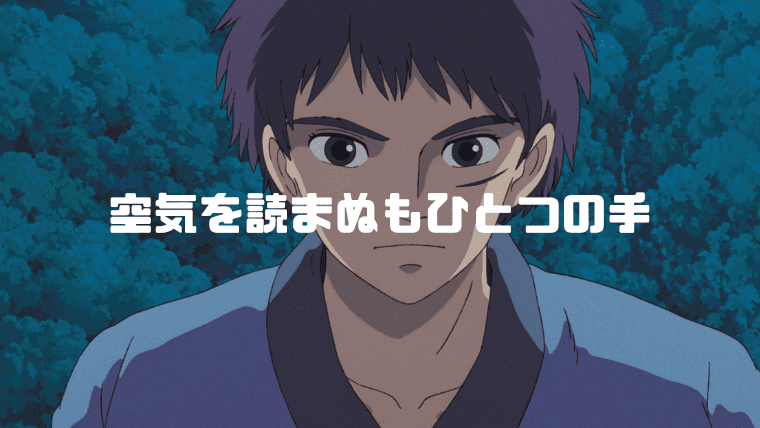
ここからは「主人公」としてのアシタカについて考えていこうと思う。アシタカ以外の登場人物がその本音をひた隠しにするのに対して、アシタカはものの見事に、ずけずけと言いたいことを言う人物として描かれる。それは一見、はた迷惑なだけの人物なのだが、アシタカはそれによって人々を開放する主人公となっていくのである。
まずはその「主人公」となっていく段階について振り返ろう。
アシタカが「主人公」になるための2つの「段落」
物語の主人公なんてものは初めから決まっているようなものだが、この映画に限って言うとその主人公の基本的な候補はアシタカとサンの二択となる。映画のタイトルだけを見るなら主人公はサンのようにも思えるが、物語はアシタカの楽園追放から始まるし、概ねアシタカの主観を通じて進行する(さらに、宮崎監督は「アシタカセッキ」というタイトルも考えていた)。
したがって何かしらのきめてが必要だと思うのだが、個人的には2つの「段落」を経ることによってアシタカは主人公になっていったと考える。
その「段落」とは、
- サンがタタラバを襲った際に行なった、エボシとサンに挟まれながらの演説
- シシ神が「呪いの痣」を消してくれなかったことを知ったときの涙
になると思う。
サンがタタラバを襲撃するまでにアシタカの右腕は二度ほど本人の意志に反して暴走している。一回目はジコ坊を結果的に救う事になった弓矢での攻撃シーン。2回目はエボシ御前と「秘密の庭」に行ったとき。
しかし、あの演説シーンの直前からアシタカの右腕は暴走していない。
つまり、アシタカは自らの中にある「憎しみ」をコントロールできるようになったということになる。
アシタカの右腕の暴走シーンは絶妙な「ミスリード」が施されている。それは、エボシ御前の「愚かな猪め。呪うなら私を呪えばいいものを。」という台詞が主な原因となっている。この台詞の直後に右腕の暴走が始まるので、それはナゴの守の憎しみによるものであるかのような印象を与えられている。しかし実際には、あの暴走はアシタカ本人の怒りや憎しみによるものと考えるべきであろう。そうでなければサンのタタラバ襲撃シーンで暴走をコントロールできた理由がわからない。彼がコントロールしたのはナゴの守の憎しみではなく、自分の憎しみである。だからこそ周りの人間に「憎しみにとらわれるな!」と言い張れるのである。
これだけでも十分に主人公の資格があるように思われるが、タタラバで演説を行なっている時点ではアシタカ自身が大きな問題を抱えていた。もちろんそれは彼の右腕につけられた呪いの痣である。
あの時点でアシタカはまだその呪いが解けるかもしれないと一縷の望みを持っていたに違いない。
しかしその後、シシ神が自らの傷を癒やしても呪いを解いてくれなかったという事実を受け、彼は自らの呪いを解くという旅に終止符を打った。
それは彼によっての希望が絶たれたということを意味するものであり、その悲しみから物語中ただ一度(そしてただ一人)涙をながしたのである。
この涙の前後ではアシタカの行動原理は根本的に異なっている。それまでは自分の為の人生であり、それからは誰か(特にサン)のための人生である。
自分の未来に絶望しながらも、他者のために生きることを決めたアシタカは主人公となったのである。
「主人公」としてのアシタカの役割
さて、「他者のために生きる」ことを決めたアシタカだが、結局どのようにすることが「他者のために生きる」ことになるのだろうか?
「もののけ姫」という物語のなかにおいてそれは明確であり、人々を「憎しみ」から開放するために生きるということになる。
そのためにアシタカは人々に対して「憎しみにとらわれるな!」とか「人と森がともに生きる道はないのか!」などと、瑞々しさあふれる台詞を平然とぶつける。
そういうことは言われた方もわかっていることであるのだが、彼らは抗うことができないなにかにとらわれて行動をしている。別の言い方をすると「もはや後戻りはできない」という感覚の中で生きているのである。
そういった人々にとってアシタカの言葉は「若者の戯言」として一蹴したくもなるだろうし、それでいて心の琴線に触れるものでもある。アシタカを否定したいという思いが強ければ強いほど、それはアシタカの言葉に対するある種の「憧れ」が大きいことを意味する。
つまりアシタカの言葉に反応してしまう彼ら自身も、ひた隠しにしてきた本音をアシタカのように表に出して叫びたいのである。
そういう形で人の心に「ゆらぎ」を与えることで自らを見つめ、最終的に「憎しみ」から人々を開放することが主人公としてのアシタカの役割であったということだと思う。残念ながらアシタカのその思いが本編中でかなったとは言い難いが、アシタカはあのあともそれをし続けてくれるのだろうと思う。アシタカを始めとするすべての「主人公」たちがやってきてくれたように。
アシタカのその後については様々な媒体で宮崎駿本人が少々冗談めかしながら語っている(例えば制作ドキュメンタリー「もののけ姫はこうして生まれた。」)。アシタカはタタラバで生きることを決めたが、サンは森で暮らすことをやめていない。つまり、アシタカは製鉄業を営むタタラバとサンとの間で板挟の状態になってしまうことが運命づけられている。片方の言い分を飲めばもう片方が立たないという無限地獄のような状況で一生懸命に生きるのである。少々可愛そうな気もするが「憎しみ」という観点でものを見れば悪くもないだろう。「憎しみ」とは一方的な感情であり、人の中にある「ゆらぎ」こそが「憎しみ」を消すほぼ唯一の武器である。アシタカは弁舌と行動によってタタラバの人々やサンにその「ゆらぎ」を与えたわけだが、アシタカは本編終了後に物理的に森とタタラバを行き来するという「ゆらぎ」に叩き込まれるということになる。身をもってその「ゆらぎ」を体現するあたりも誠に「主人公」である。
おまけ:困ってちゃんなアシタカ
ここまではアシタカのかっこいい部分について考えてきたが、よくよく「もののけ姫」本編を見ると、アシタカの困ってちゃんな側面も見えてくる。結局はその困ってちゃんな部分が彼を主人公足らしめたという味方もできるので非常にうまくできてはいるのだが、その辺のことについても振り返ってみよう。
人の仕事場にズケズケと上がり込むアシタカ。
アシタカが最初に困ってちゃんな側面を見せたシーンは、タタラバで吹子(フイゴ)を踏む番子の女性たちのところに赴いたところだろう。
その直前に、タタラバの女性たちに「仕事場を見に来て」と言われたはいるのだが、通常このような言葉は「社交辞令」であり、本当に来いということではない。
しかしアシタカは実際に彼女らの仕事場に現れたばかりか、わざわざ吹子を踏ませろと言い張った。アシタカとしては仕事を手伝ってあげたという気持ちがあったかもしれないが、過酷な状況下で厳密なルーティンを組んでいるということを考えると極めて邪魔である。
特にその場を取り仕切る人間にとっては迷惑千万。
あの場を取り仕切っているのはおトキさんだが、その対応には非常に困っただろう。自分の夫を背負って一山超えてきてくれた恩義はあるが、可及的速やかにこの場を去ってもらわなくてはならない。
そこでおトキさんがとった作戦が、「とっとと吹子を踏ませて早急に帰ってもらう」である。このシーンでおトキは「せっかくだから変わってもらいな」という言葉を番子の女性にかけるが、実はこのアフレコ何度も取り直しが行われている(参考:「もののけ姫はこうして生まれた。」)。
声優の島本須美さんの人の良さや優しさが出てしまって「実はアシタカは邪魔だ」という絶妙なニュアンスが出なかったものと思われる。
何れにせよ、アシタカがこの辺のことに思いを馳せることができない人物であることが見て取れるだろう。ただ単に「若い」ということではあるけれど。
「あの子は人間だ!」とモロに説教するアシタカ
もう一つアシタカの困ったちゃんな側面が見て取れるのが、「もののけ姫」で有名な「あの子を解き放てあの子は人げだぞ」のシーンだろう。
CMや特報でも使われた印象深い台詞だし、アシタカの決めシーンでもあっただろう。
しかしだ、あれを言われたモロの君の立場に立ってるみると「何言ってんの?そんなこと知っているよ。あの子をどうすればよいかなんて何年も何年も考えてきたよ。それこそ自分があの子を縛ってしまっているのではなんて何度も思ったよ。でも、あの子自身の思いもあるし、私達は共に暮らしてきた家族なんだよ。それに対して赤の他人のお前が『解き放て』なんてよく言えたものだな。」という思いだっただろう。
これを「黙れ小僧!」という返しで終わらせたモロの君の懐の深さには感服する。それこそ食い殺しても良かったほどの「空気読めない発言」だったと思う。
ただ、この「空気読めない発言」が「もののけ姫」においては極めて重要であり、それが結果的に人々の心をえぐり、もう一度スタートラインに立たせてくれるのである。
モロの君としても平然と「あの子は人間だぞ!」と言い放ったアシタカだからこそ、愛娘であるサンを託す気になったのだろう。
結局「空気を読まない」という性質は「主人公」が持つ重要な特性であるということもできるかもしれない。そうでなければ「ただの人」だからね。
俺は空気を読むよ。うん。
以上で、私が個人的に思うアシタカが主人公である理由と、主人公になっていく段階である。振り返ってみると、様々な要素が見事に噛み合って主人公としてのアシタカを際立たせていると感じた。
皆さんはアシタカや「もののけ姫」における「主人公」についてどのように考えるだろうか。
この記事で使用した画像は「スタジオジブリ作品静止画」の画像です。
この記事を書いた人
最新記事
- 2024年7月14日
「君たちはどう生きるか」のあらすじと考察ポイント【完全ネタバレ】 - 2024年7月14日
【君たちはどう生きるか】火事場を走る眞人シーンと高畑勲が目指したアニメーション表現 - 2024年7月3日
【ゴジラ(1984年)】あらすじと考察-ゴジラ復活を告げる小林桂樹の涙- - 2024年6月30日
【ゴジラvsビオランテ】あらすじとその面白さ-出現する2人の芹沢博士- - 2024年6月13日
【THE NEXT GENERATION パトレイバー 首都決戦】あらすじと考察-灰原零とは何だったのか?-