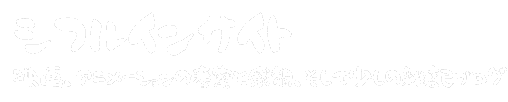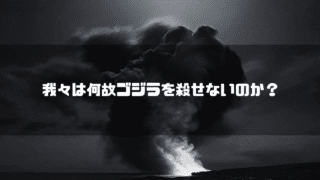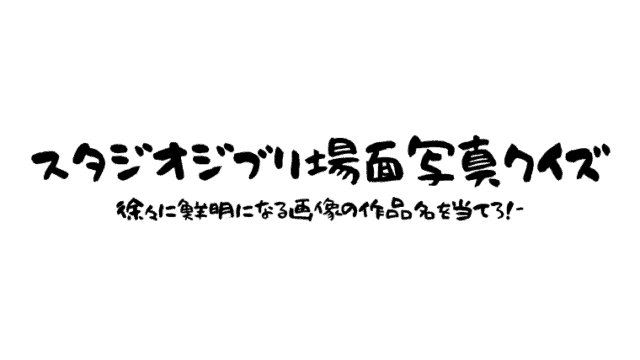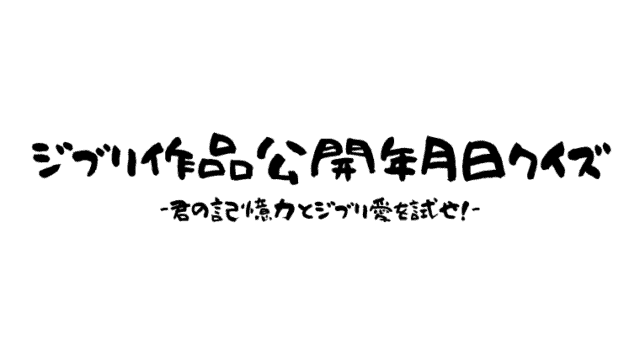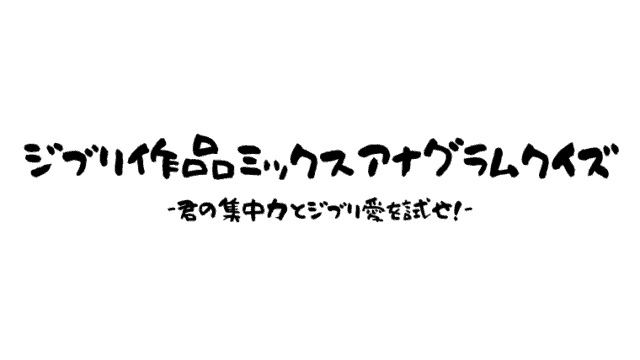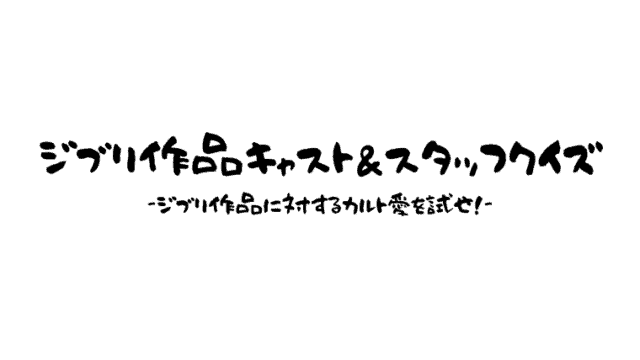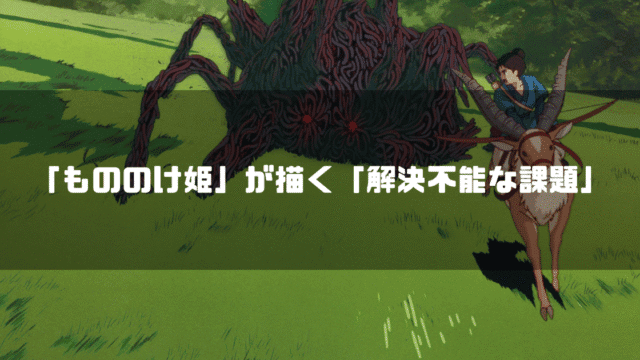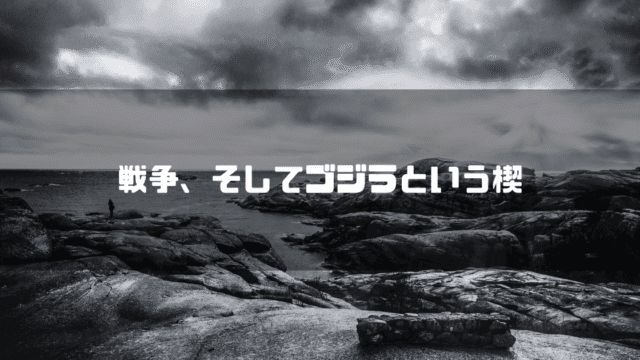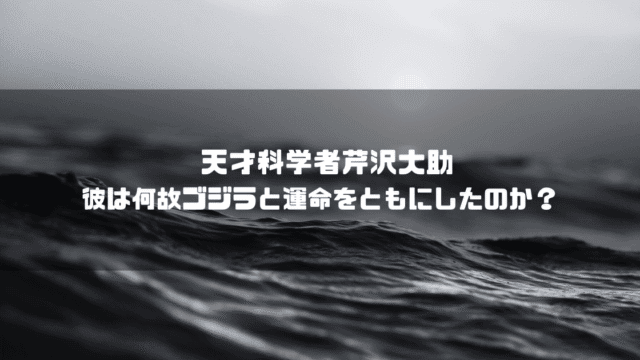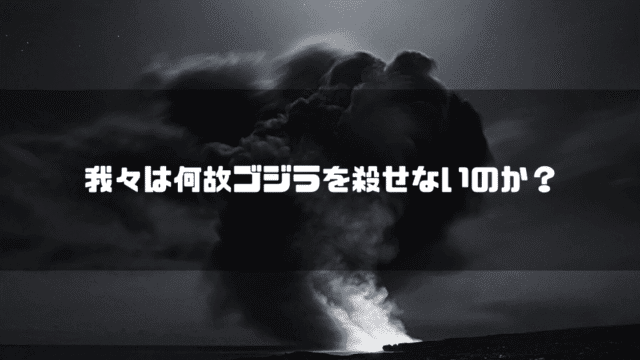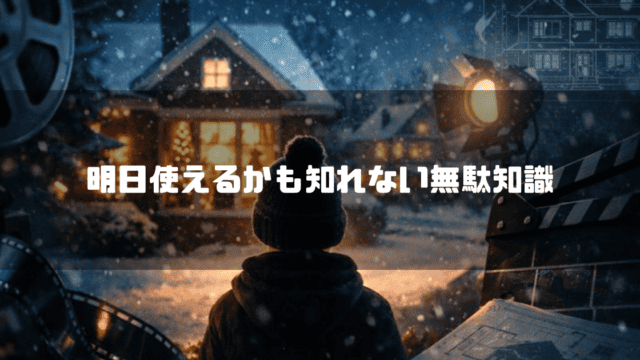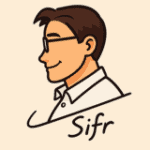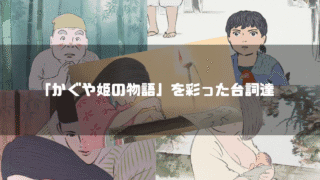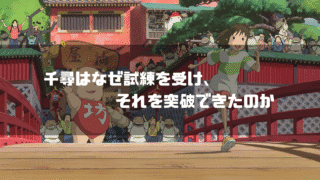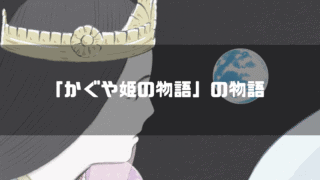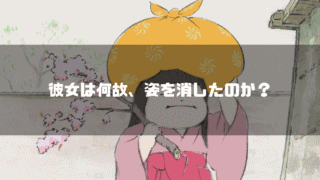「昭和ゴジラ」の変遷を考察-ゴジラは如何にしてヒーローとなったのか?-
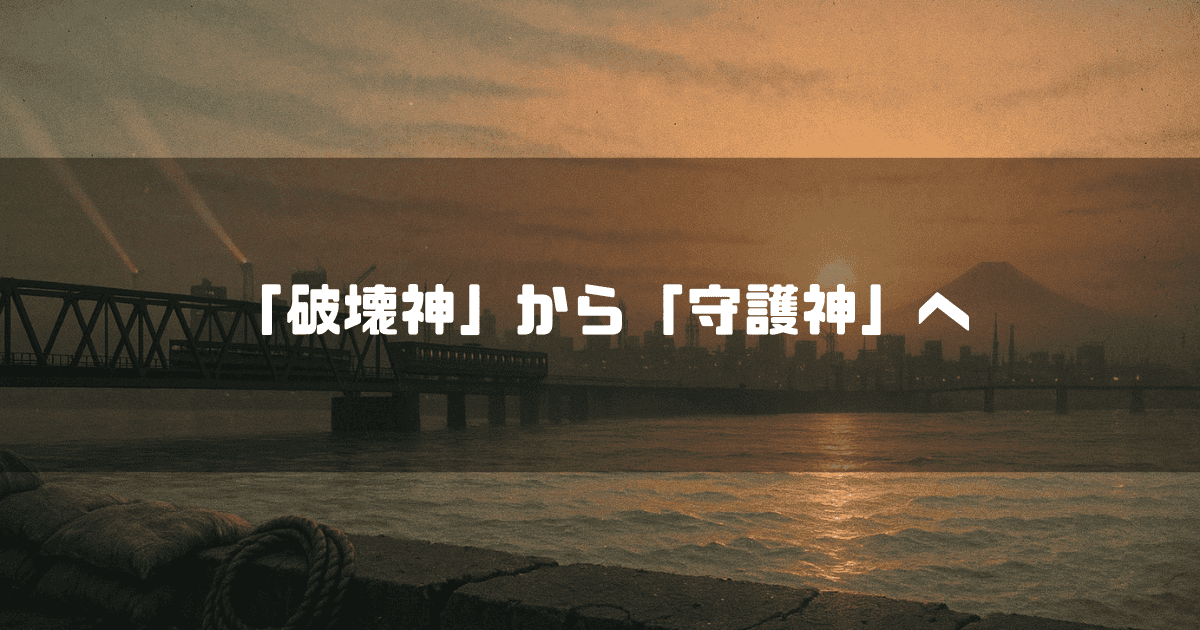
1954年に公開された「ゴジラ」。それは、単なる怪獣映画の枠を超えたものであり、戦後日本の社会に深く突き刺さる強烈なメッセージを内包していた。
水爆実験によって平安な日々を奪われ、ビキニ環礁の悲劇を彷彿とさせる姿で東京に上陸したゴジラは、戦争の記憶と核兵器への恐怖が具現化した、まさに「人間の業」の現れであったと思う。
この第一作目の「ゴジラ」を個人的にとても愛しているのだが、シリーズを重ねるごとに、恐怖の大王は、いつしか子供たちの声援を受ける「正義の味方」へとその姿を変えていく。
この記事では、恐怖の大王がいかにしてヒーローへと変貌を遂げたのか、その変遷の軌跡を、1954年の「ゴジラ」から1975年の「メカゴジラの逆襲」に至るまでの「昭和ゴジラシリーズ」全15作を振り返りながら考察していく(1984年の「ゴジラ」は通常「昭和ゴジラシリーズ」には含まれない)。
この記事の内容を、AIが対話形式(ラジオ形式)で分かりやすく解説してくれます。
-
恐怖の象徴から「戦う怪獣」へのシフト
初代ゴジラは水爆実験が生んだ「人間の業」の象徴であり、絶対的な恐怖の対象だった。しかし、次作『ゴジラの逆襲』でアンギラスという「戦う相手」が登場したことで、物語は「怪獣同士の対決」というエンターテイメント路線へと転換し、後のヒーロー化への重要な第一歩となった。 -
地球の守護者への転換―「共通の敵」の出現
当初人類の脅威だったゴジラは、『モスラ対ゴジラ』で意思疎通可能な怪獣と対峙し、続く『三大怪獣 地球最大の決戦』で宇宙怪獣キングギドラという「共通の敵」が出現したことで、他の地球怪獣と共闘。これにより、地球を守る側に立つというヒーローとしての原型が明確に形成された。 -
「子供たちのヒーロー」の確立とその後の変容
公害怪獣と戦った『ゴジラ対ヘドラ』で実質的なヒーローとなり、『ゴジラ対ガイガン』では主題歌で「ぼくらのゴジラ」と歌われ名実ともにヒーロー像を確立。しかし、ヒーローとして完成されたことで、以降の作品では物語を動かす装置的な役割へと変化し、存在感が希薄化していくことにも繋がった。
第1期:恐怖と破壊の象徴として

「ゴジラ」(1954年) – 人間の業が生み出した絶対的恐怖
全ての原点である第一作において、ゴジラは純然たる恐怖の対象として描かれる。古代の生物が水爆実験の影響で変異したという設定は、当時、厳然たる事実として突きつけられた第五福竜丸事件(「第五福竜丸」のWikipedia)の記憶と直結する。
放射能を帯びた黒い雨、破壊され炎上する東京の姿は、観客に戦争の惨禍をまざまざと思い起こさせたものだったかもしれない。ゴジラは、人類が自らの手で生み出してしまった制御不能の暴力の化身であり、その破壊活動に一切の躊躇も感傷もない(「ただ生きているだけ」とも言える)。それは自然災害のように無慈悲であり、同時に、人類への明確な「罰」のようにも見える。
この作品の深みは、ゴジラを倒す手段にも「人間の業」が色濃く反映されている点にある。
芹沢博士が発明した「オキシジェン・デストロイヤー」は、ゴジラを葬り去る唯一の希望であると同時に、水爆をも超えかねない悪魔の兵器であった。博士は、その発明が悪用されることを恐れ、ゴジラと共に自らの命を絶つ道を選ぶ。
科学の進歩がもたらす光と影、そして業を断ち切るためには更なる業を重ねるしかないという、救いのない現実。初代「ゴジラ」は、ゴジラという存在を通して、人類が抱える根源的な矛盾と罪を鋭く告発する、社会派ドラマとしての側面を強く持っていたのである。
もちろん、この「初代ゴジラ」において、「ヒーローとしてのゴジラ」の要素は微塵も見られない。

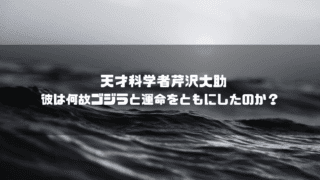
「ゴジラの逆襲」(1955年) – 「戦う相手」の出現と物語構造の変化
前作の大ヒットを受け、わずか半年後に公開されたシリーズ第二作。後の展開を考えると、この作品がシリーズの方向性を決定づけたと言って良いのではないだろうか(「ゴジラシリーズ」に新たな道筋を与えたとも言える)。
最大の変化は、ゴジラ以外の怪獣「アンギラス」が登場したことで、これにより、物語の構造は「ゴジラ対人類」という単純な図式から、「ゴジラ対アンギラス」という怪獣同士の対決を軸に展開するものへとシフトした。1984年に公開される「ゴジラ」まで、ゴジラが単独で登場する作品は制作されない。
ゴジラに「戦う相手」が現れたことで、都市の破壊は「ゴジラによる一方的な蹂躙」から、「怪獣同士の激しい戦いの余波」という側面を持つようになる。これは後の「ウルトラマン」に代表されるような、怪獣プロレス的なエンターテイメント路線の萌芽ともとれる。人類は、二大怪獣の戦いを前にして、為す術もなく逃げ惑うしかない。この構図は、結果として、ゴジラの脅威を相対化させる効果があった。
しかし、この時点ではまだヒーロー化の兆しは微塵もない。ゴジラもアンギラスも、共に水爆実験によって目覚めた「核の申し子」であり、人類にとっては等しく脅威であることに変わりはなかった。基本的な怪獣観は第一作を踏襲しており、物語の結末も、ゴジラを雪山に生き埋めにするという、暫定的な対処に過ぎなかった。
しかし、「ゴジラに敵対する別の怪獣」というフォーマットは、後のシリーズでゴジラがヒーローへと転身していくための、極めて重要な第一歩であったことは間違いない。
第2期:ヒーローへの道

「キングコング対ゴジラ」(1962年) – エンターテイメント化の象徴
7年の時を経て、初のカラー作品として公開された作品。日米の怪獣スターが激突するという企画そのものが、「戦争の痛手」や「核の脅威」といった社会的な問題を描く作品から、純然たる大衆娯楽へと舵を切ったことを明確に示している(それはそれで全然問題ない)。
本作に登場するキングコングは、核とは無関係の、南海の島に住む巨大な類人猿である。「核の申し子ではない怪獣」の登場は、ゴジラ(あるいは「怪獣」)の持つ「核の脅威」という特殊性を相対化させ、「怪獣」は必ずしも「核の脅威」と関係がある必要がないことになった。そういう意味で、昭和ゴジラシリーズの大きな転換点となった作品と言える。
もちろん、ゴジラが北極の氷山から出現する際にチェレンコフ光が描かれるなど、「ゴジラと核」というイメージは踏襲されている。しかし、物語の主眼はあくまで二大怪獣のプロレス的な対決にあり、初代のような重苦しい雰囲気は薄れている。
高島忠夫演じる主人公 桜井修を始めとして、人間側のキャラクターもコミカルに描かれ、作品全体が明るいトーンで統一されている。ゴジラは必ずしも社会的なメッセージを背負わされた存在ではなく、エンターテイメントを盛り上げるための強力なキャラクターとして扱われ始めている。
また、本作以降、ゴジラは明確に倒されることがなくなり、「戦いの末に海へ帰っていく」といった、ある種曖昧な形で物語が締めくくられるようになる。これは、続編製作を容易にするための商業的な判断であったかもしれないが、結果としてゴジラが「倒すべき絶対悪」から、「いつもそこにあり続ける自然現象のようなものに変化した」と見ることもできるかもしれない。
「モスラ対ゴジラ」(1964年)&「三大怪獣 地球最大の決戦」(1964年) – 人格の発現と「共通の敵」
この2作品は、以下の2点において、ゴジラのヒーロー化を語る上で決定的に重要な意味を持つ。
- 人格の芽生え:「モスラ対ゴジラ」で、ゴジラは初めて「人間と意思疎通が可能な怪獣」と対峙する。インファント島の小美人を介してではあるが、モスラは明確な「意志」を持ち、人類と対話することができる。卵を守るために戦うというモスラの行動原理は、それまで破壊の本能のみで動いているように見えたゴジラとは対照的である。怪獣に「人格」が与えられたこの瞬間は、ゴジラ自身にも、後の作品でより複雑な感情や役割が与えられる下地を作った。
- 共通の敵の出現:続く「三大怪獣 地球最大の決戦」では、宇宙から飛来した「キングギドラ」という、地球全体にとっての脅威が登場する。この「地球外からの侵略者」という設定は画期的であった。人類はもちろん、ゴジラやラドンにとってもキングギドラは共通の敵となる。そして、その2体の怪獣を、モスラが説得するという驚くべき(見ようによっては笑ってしまう)シーンが描かれる。最終的に、それまで敵同士だった地球怪獣たちが手を組み、キングギドラに立ち向かうという展開は、ゴジラの立ち位置を180度変える可能性を示唆した。
人類を脅かす存在であったゴジラが、より強大な「外敵」に対しては、結果的に地球を守る側に立つ。ここに、ヒーローとしてのゴジラの原型が明確に見て取れる。
もちろん、この時点ではまだ人類の味方になったわけではない。しかし、ゴジラが単なる破壊神ではない、多面的な存在へと変化していく大きな一歩であったことは間違いない。
第3期:ヒーロー性の模索と確立
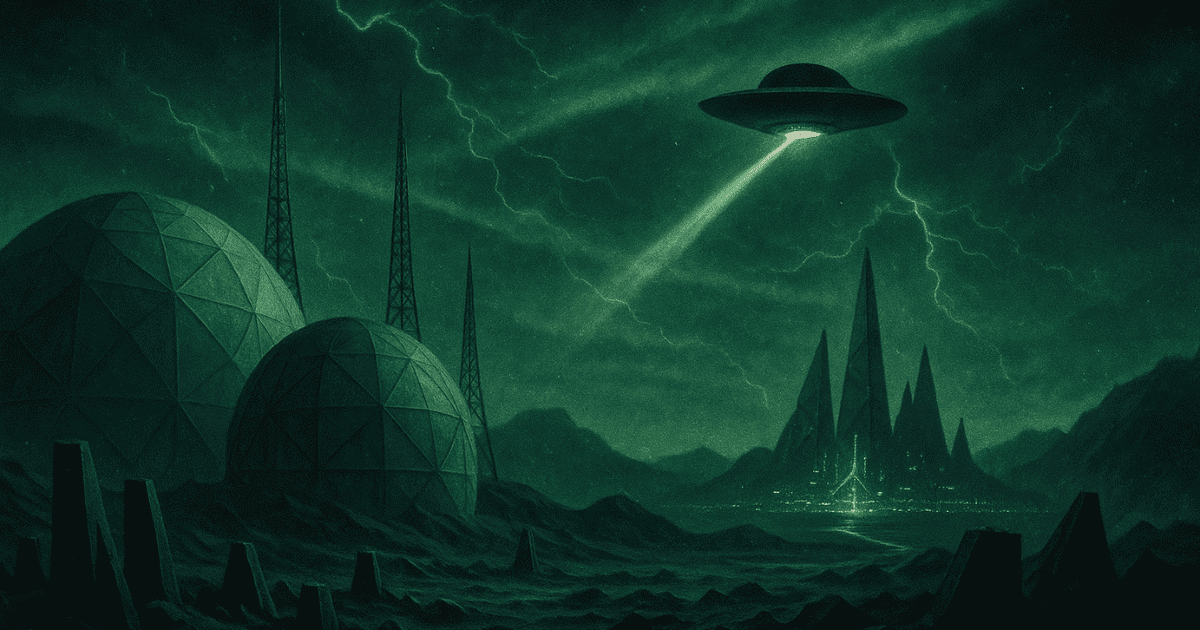
「怪獣大戦争」(1965年) – 宇宙規模のドラマと翻弄されるゴジラ
本作は、ゴジラの立ち位置という点ではやや特殊な作品である。物語の舞台は木星の衛星「X星」にまで広がり、人類は宇宙船を自由に航行させるほどの科学技術を手にしている。
ゴジラとラドンは、キングギドラに苦しむX星人の要請で「貸し出され」、彼らのために戦うことになる。しかし、それは全てX星人による地球侵略の罠であった。
この作品において、ゴジラは主体性を失い、X星人に都合よく利用される「兵器」あるいは「犠牲者」として描かれている。人間(と宇宙人)のドラマが主軸となり、ゴジラ自身の登場時間は極めて短い。
しかし、この物語はゴジラという存在を地球規模から宇宙規模の文脈で捉え直すきっかけとなり、後に何度も描かれる「宇宙からの侵略者と戦う地球の守護者」という役割への出発点となった側面もある。
また、ゴジラがX星で見せる「シェー」のポーズは、キャラクターとしての擬人化、人間化がさらに進んだことを象徴するシーンと見ることができるだろう。個人的にはとても好きなシーンである(ゴジラがゴジラであることを否定しているとはおもうけれど)。
「初代ゴジラ」を除いて、個人的にはこの「怪獣大戦争」が「昭和ゴジラシリーズ」の中で1番好きな作品となっている。
現代的には「X星人」のフォルムはなんとも滑稽で、ファニーで、結果的にむしろ前衛的であると言えるものであり、「心の準備」をしないとまともには見られないとは思う。
しかし、彼らが「ゴジラ」と「ラドン」を利用し、自分たちの被害を最小限にして地球侵略を進めようとするところが物語としてはうまいと思う。結果として、宇宙人という存在とゴジラの存在が自然と共存している。
また、グレンと波川との恋によって「電子計算機(現代的にはAIかな)によって意思決定するX星人の敗北の必然」が端的に描かれていることもうまいと思う(つまり、愛のちからですよ!)。
「ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘」(1966年) – 悪を討つ正義の味方へ
本作と次作「怪獣島の決戦 ゴジラの息子」は、物語の舞台を文明社会から離れた孤島に限定することで、ゴジラと「人間社会の破壊」という要素が絶妙に切り離されている(そういう事実は映画を見る人の「常識」となっていたと言う側面もあったと思う)。この事実が、ゴジラのヒーロー化を–おそらく意図せず–大きく前進させたと思われる。
「南海の大決闘」でゴジラが戦う相手は、怪獣エビラだけではない。島の基地で核兵器を製造する秘密結社「赤イ竹」こそが真の敵である。初代ゴジラを生み出した元凶である「核」が、ここではゴジラが打ち砕くべき「悪の象徴」として描かれているのは極めて興味深い。ゴジラは「核を悪用しようとする人間」を懲らしめ、結果的に主人公たちを救い出す存在となる。もはや人類の脅威ではなく、悪事を働く特定の人間たちにとっての天敵であり、善良な市民にとっては頼もしい味方という構図がここで明確に描かれた。
「怪獣島の決戦 ゴジラの息子」(1967年) – 「人間の業」の対象の変化と父性
本作では、物語の背景に「世界的な食糧危機」があり、その解決策として「気象コントロール実験」が行われるという、新たな「人間の業」がテーマとして設定されている。この実験の失敗によって巨大カマキリや巨大グモが出現し、島の生態系が狂ってしまう。初代ゴジラの「核」というテーマから一歩進み、より広範な文明批評へと視野が広がっている。
この作品の最大の特徴は、ゴジラの息子「ミニラ」の登場である。ゴジラは、ミニラを守り、戦い方を教える「父親」としての側面を見せる。これにより、ゴジラは単なる戦闘生物ではなく、愛情や庇護欲といった人間的な感情を持つ存在となり、観客(特に子供たち)が感情移入しやすい対象となったと言えるのではないだろうか。
人類が引き起こした異常気象という危機の中で、我が子を守るために戦うゴジラの姿は、結果的に人間を助けることにも繋がり、守護者としてのイメージをさらに強化した。
「怪獣総進撃」(1968年) – 管理される怪獣と地球防衛軍
昭和シリーズの一つの集大成とも言える本作では、20世紀末の未来が舞台となる。人類の科学は飛躍的に発展し、ゴジラをはじめとする怪獣たちは小笠原諸島の「怪獣ランド」で管理・研究対象となっている。もはやゴジラは人類にとって脅威ではない存在として描かれている。
物語は、地球侵略を企む宇宙人・キラアク星人が怪獣たちを操り、世界中の都市を攻撃させるところから始まる。人類は洗脳を解き、怪獣たちを味方につけてキラアク星人に反撃を開始する。ゴジラは地球怪獣軍団のリーダーとして、キングギドラとの最終決戦に挑む。
この作品に至り、ゴジラは完全に「地球を守るヒーロー連合」の一員としての地位を確立した。人類と怪獣が共闘し、宇宙からの侵略者を撃退するという構図は、もはや初代の面影を探すことの方が難しいほどである。
第4期:ヒーローとしてのゴジラの完成と迷走
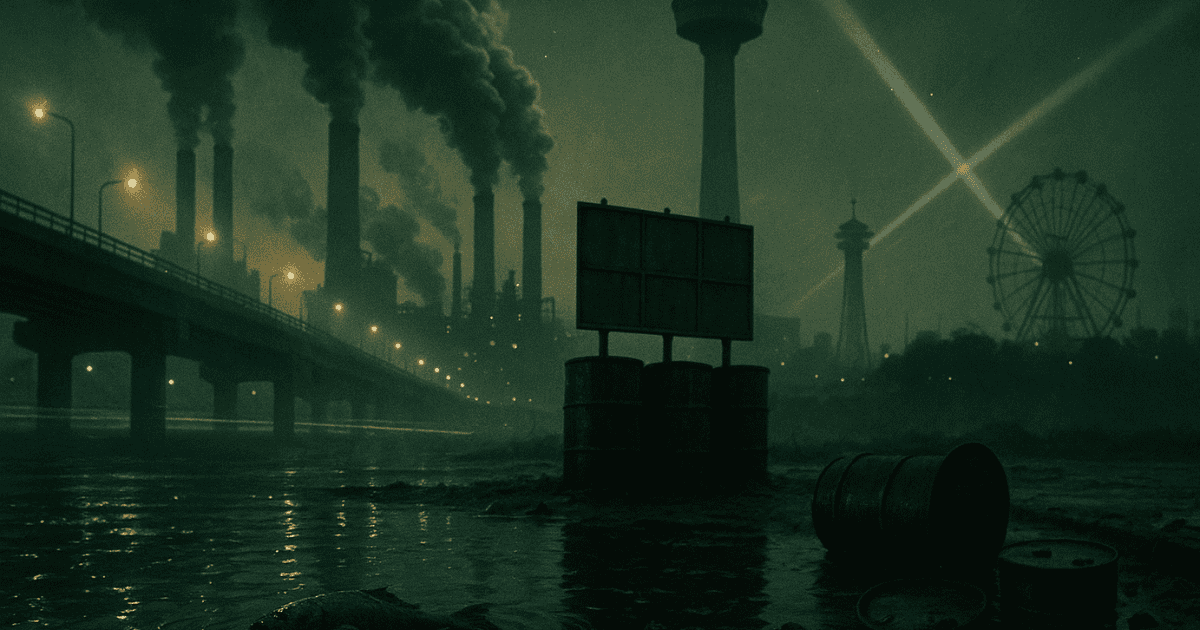
過渡期の重要作「ゴジラ・ミニラ・ガバラ オール怪獣大進撃」(1969年)
「怪獣総進撃」と次作「ゴジラ対ヘドラ」の間には、ゴジラの描かれ方において大きな断絶が存在するが、その変化を象徴するのがこの異色作である。本作の舞台は、怪獣が実在しない現実の日本。ゴジラやミニラは、いじめられっ子の主人公・一郎少年が夢の中で見る、憧れの存在として描かれる。
夢の中のゴジラは、一郎少年に勇気を与え、いじめに立ち向かう術を教える理想のヒーローである。ミニラに至っては、一郎少年と同じ悩みを抱える「友達」として登場する。この作品は、ゴジラを現実世界から切り離し、少年の空想の世界の住人とすることで、「破壊」というネガティブなイメージが完全に排除されている。
ゴジラが純粋な「憧れの対象」「正義の味方」として描かれたことで、次作以降、現実世界においてもゴジラを完全なヒーローとして描くための、いわば心理的な準備が整えられたと考えることができる(心理的な準備をしようとは思ってなかったと思うけど)。
「ゴジラ対ヘドラ」(1971年) – 実質的なヒーロー化の達成
本作こそ、ゴジラが実質的にヒーローとして確立した作品と言える。敵となるヘドラは、宇宙から飛来した鉱物が、人間が垂れ流した汚染物質を吸収して生まれた公害怪獣である。その存在自体が、高度経済成長期の負の遺産、つまり、「人間の業」の塊である(「三丁目の夕日」の裏側にあった悲しき現実!)。
本来、人類の自業自得によって生まれたヘドラと、ゴジラが戦う義理も理由もない。しかし、ゴジラは突如として海から現れ、人類に代わってヘドラとの死闘を繰り広げる。その登場シーンは、あたかも人々の苦しみや願いに応えて出現した「守り神」のようであり、極めて象徴的である。
日本本土を舞台としながらも、ゴジラによる都市破壊はほとんど描かれず、ひたすらにヘドラを追い詰め、殲滅しようとする姿は、まさしく正義の執行者そのものである。人類の愚行を浄化する超越的な存在として、ゴジラのヒーロー性はここで決定的なものとなった。
「地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン」(1972年) – 名実ともにヒーローへ
前作で実質的なヒーローとなったゴジラは、本作でその地位を誰もが認めるものへと昇華させる。物語は、平和を偽装して地球侵略を企むM宇宙ハンター星雲人が送り込んだ、サイボーグ怪獣ガイガンとキングギドラに、ゴジラとアンギラスが立ち向かうというものだった。
本作の特筆すべき点は二つある。一つは、ゴジラとアンギラスが「吹き出し」を用いて人間のように会話するシーンが挿入されたこと。これはキャラクターの擬人化の極致であり、ゴジラが完全に子供たちの目線に立ったキャラクターとなったことを示している。
そしてもう一つが、エンディングで流れる主題歌「ゴジラマーチ」の存在である。その歌詞は「がんばれ がんばれ ぼくらのゴジラ」と、明確にゴジラを応援する内容となっている。これは製作サイドが、ゴジラを「子供たちのヒーロー」として公式に宣言したということになるだろう。名実ともに、ゴジラがヒーローとなった瞬間である。
ヒーロー路線の深化と形骸化 – 「ゴジラ対メガロ」(1973年)から「メカゴジラの逆襲」(1975年)
ヒーローとして完成されたゴジラは、ここからその存在意義を問われる迷走期に入る。
- 「ゴジラ対メガロ」:電子ロボット「ジェットジャガー」という、より分かりやすいヒーローと共演。ゴジラはジェットジャガーのピンチに駆けつける助っ人的な役割となり、その存在感は希薄化している。
- 「ゴジラ対メカゴジラ」:ゴジラに偽装したロボット怪獣「メカゴジラ」が登場。本物のゴジラは、伝説の怪獣キングシーサーと共にメカゴジラに挑む。しかし初戦では敗北を喫し、絶対的な強さにも陰りが見える。物語の主役はむしろキングシーサーであり、ゴジラは共同戦線を張るヒーローの一人に過ぎない。
- 「メカゴジラの逆襲」:前作の復讐戦。敵役である真船博士とその娘・桂の悲劇的なドラマに焦点が当てられ、ゴジラの役割は侵略者の兵器を破壊する装置的なものに留まる。桂のサイボーグ化という部分に科学の業というテーマへの回帰が見られるが、それがゴジラという存在と結びついておらず、もはやゴジラである必然性が失われてしまっている。
ヒーローとして完成されたがゆえに、ゴジラは物語を動かすための便利な「装置」と化し、初代が持っていた圧倒的な存在感やカリスマ性を失っていった。昭和ゴジラシリーズの終焉は、ヒーロー化の果てに待っていた、ある種の宿命であったのかもしれない。
結論とその後の「ゴジラシリーズ」について
第一作目の「ゴジラ」で「人間の業」の象徴として誕生したゴジラは、「ゴジラの逆襲」で「戦う相手」を得たことを皮切りに、その役割を大きく変転させていった。シリーズが進むにつれて、敵は地球内部の脅威から、宇宙からの侵略者や公害が生み出した怪物へと変化していった。その過程で、ゴジラは徐々に「人格」を発現させ、地球という共同体を守るための戦いに身を投じていく。
人間と意思疎通可能なモスラとの対話、そしてキングギドラという「共通の敵」との戦いは、ゴジラが単なる破壊神ではないことを示し、ヒーローへの道を拓いた。そして、人類の自業自得の象徴である公害怪獣ヘドラと戦った「ゴジラ対ヘドラ」において、ゴジラは実質的に人類を守るヒーローとしてのアイデンティティを確立したと言える。さらに、主題歌で「ぼくらのゴジラ」と歌われた「ゴジラ対ガイガン」によって、そのヒーロー像は名実ともに決定的なものとなったのである。
「昭和ゴジラシリーズ』におけるゴジラの変遷は、時代の空気を敏感に反映しながら、一つの存在が「恐怖」から「正義」へとその意味を書き換えていくものであった。その流れは「メカゴジラの逆襲」で一旦歩みを止めることになるが、約10年の時を経て、1984年の「ゴジラ」により「恐怖の大王」として復活したゴジラは、「平成ゴジラシリーズ」で概ね同じ変遷をたどることになる(「昭和ゴジラシリーズ」ほどの露骨さは流石になかったが)。
しかもその流れは、ハリウッド版ゴジラにも踏襲されるに至っており、2014年に公開されたギャレス・エドワーズの「GODZILLA」は十分にゴジラの「破壊神的側面」を描いていたと思うが、2024年の「ゴジラxコング 新たなる帝国」では、ゴジラにはやはり人格が芽生えているように見えるし、コミカルな描写も十分に多く、コングと一緒に人類の敵となる存在と戦っている。
このように考えてみると、いわゆる「ミレニアムシリーズ」は「ゴジラシリーズ」の中でも異色の物となっていることが見えてくるが、そのことについてはいつか考えてみよう。
また、「シン・ゴジラ」や「ゴジラ-1.0」は正当な「初代ゴジラ」の系譜の中にある作品となっており、ゴジラという存在に「初代らしさ」を求めるならこの辺の作品をみることになるだろう(84年「ゴジラ」も)。
個人的には「初代ゴジラ」が一番好きだし、特段新作の必要性は感じない。それでもなお、すべてのゴジラ作品は見ているし(そして好きだし)、心の何処かで新作を待ちわびるというなんともアンビバレントな心情を抱えてもいる。
作り続けることで忘れられない存在となるという側面もあると思うので、傑作としての「初代ゴジラ」を忘れないためにも、新作が発表されることに意味があるのかもしれない。たとえそれが「ヒーローとしてのゴジラ」であったとしても。
以上が、個人的に「『昭和ゴジラシリーズ』におけるゴジラの変遷」について考えて来たことでございます。もちろん異論はあると思いますが、概ねこのような流れでゴジラはヒーローとなったのだと思います。
記事内でも述べているとおり、やはり「初代ゴジラ」の輝きが大きいのですが、基本的にはすべて好きです(少なくとも嫌いな作品はありません)。
よろしければ、以下の投票で「一番好きな昭和ゴジラ作品」を教えて下さい。
おまけ:「昭和ゴジラシリーズ」の公開年月日、主演俳優、監督情報一覧
*リンク先はすべてWikipediaの記事
| 作品タイトル | 公開年月日 | 主演俳優名 | 監督名 |
|---|---|---|---|
| ゴジラ | 1954年11月3日 | 宝田明 | 本多猪四郎 |
| ゴジラの逆襲 | 1955年4月24日 | 小泉博 | 小田基義 |
| キングコング対ゴジラ | 1962年8月11日 | 高島忠夫 | 本多猪四郎 |
| モスラ対ゴジラ | 1964年4月29日 | 宝田明 | 本多猪四郎 |
| 三大怪獣 地球最大の決戦 | 1964年12月20日 | 夏木陽介 | 本多猪四郎 |
| 怪獣大戦争 | 1965年12月19日 | 宝田明 | 本多猪四郎 |
| ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘 | 1966年12月17日 | 宝田明 | 福田純 |
| 怪獣島の決戦 ゴジラの息子 | 1967年12月16日 | 高島忠夫 | 福田純 |
| 怪獣総進撃 | 1968年8月1日 | 久保明 | 本多猪四郎 |
| ゴジラ・ミニラ・ガバラ オール怪獣大進撃 | 1969年12月20日 | 佐原健二[1] | 本多猪四郎 |
| ゴジラ対ヘドラ | 1971年7月24日 | 山内明 | 坂野義光 |
| 地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン | 1972年3月12日 | 石川博 | 福田純 |
| ゴジラ対メガロ | 1973年3月17日 | 佐々木勝彦 | 福田純 |
| ゴジラ対メカゴジラ | 1974年3月21日 | 大門正明 | 福田純 |
| メカゴジラの逆襲 | 1975年3月15日 | 佐々木勝彦 | 本多猪四郎 |
- [1]
- オープニングタイトルでの出演順で佐原健二としたが、佐原健二が演じたのは苛められっ子の少年 三木一郎の父である。三木一郎を演じたのは矢崎知紀となっている。
この記事を書いた人
最新記事