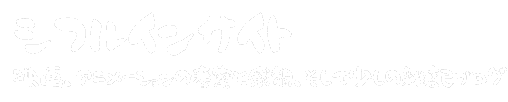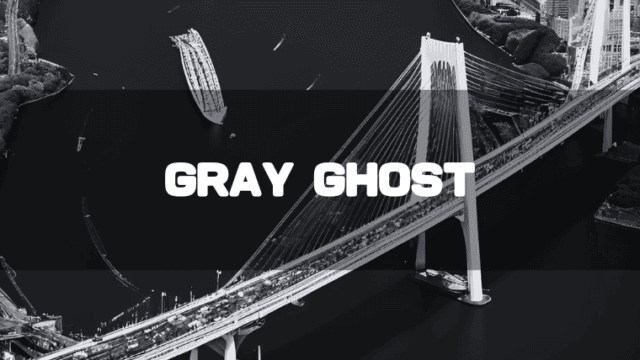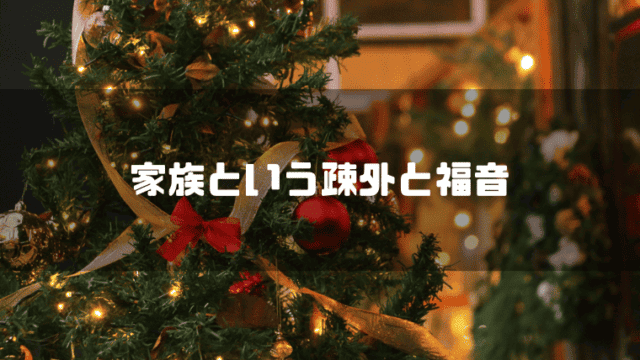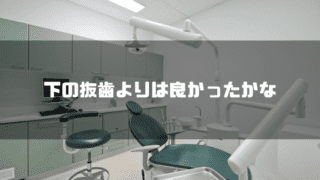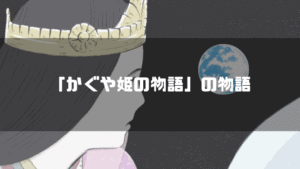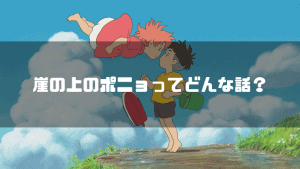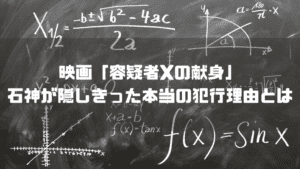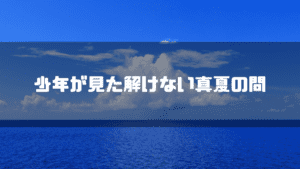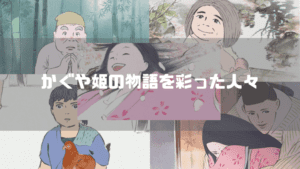「ハリー・ポッター(Harry Potter)」はJKローロングスによる全7巻に及ぶ小説作品である。世界的なヒットを記録した本作は、2001年から20011年にかけて全8作のシリーズとして映画化され、子こちらも世界的なヒットを記録した。
今回は映画版の「ハリー・ポッター」をもとに、本作の影の主人公スネイプ先生の生き様を振り返りつつ、見え隠れするダンブルドアの狂気、恐ろしさについて考えたい。そして最終的には作劇上2人がどういう意味合いを持っていたかについて個人的に考えたことをまとめようと思う。
まずは、その本心を隠しながらダンブルドアに従い続けたスネイプ先生の仕事っぷりとその生き様を思い出してみよう。
「ハリーポッター」におけるスネイプ先生の生き様

クィディッチデビュー戦
スネイプ先生が陰ながらにしてくれた最初の仕事といえば、ハリーのクィディッチデビュー戦で、密かにハリーを守っていたことになるだろう。
この一見で純真無垢な僕ちゃんは、見事にスネイプは悪いやつだと思い込んでいたが、それも今となってはいい思い出である。
ただ、未だに答えが出ないのは、スネイプ先生が守ってくれなかった場合にハリーがどうなっていたかということである。もし「万が一」なんてこともあり得たとすれば、スネイプ先生の一番大きな仕事だったとも言えるかもしれない。
狼人間事件
これも忘れてはいけない「狼からハリーたちを守った事件」。これはシリーズ3作目の「アズカバンの囚人」での出来事であった。
ハリー、ロン、ハーマイオニーが、狼人間化してしまったリーマス・ルーピンに襲われそうになるところにスネイプ先生が登場し、3人を守ってくれる。
このシーンでスネイプ先生が3人を守る素振りをするのは、演出ではなく、事前に唯一人原作者からスネイプの真実を聞かされていたアラン・リックマンの不意に出た芝居だったそうな。そういう背景を考えるとシリーズ中最もスネイプ先生らしいシーンだったと言えるのではないだろうか。
しかし「アズカバンの囚人」で最も好きなシーンはこの直前にある。
シリウス・ブラックとリーマスは、なんと12年という時間をかけてようやく憎きピーター・ペティグリューを追い詰め、後少しで止めを刺せる所まで来ていた。それを邪魔したのがまさにスネイプ先生だったが、そのスネイプに足してシリウスが発したセリフが
Brilliant, Snape. You’ve put your keen mind to the task and come to the wrong conclusion.
訳:お見事だよスネイプ。その鋭い洞察力で(また)間違った結論に達したな。
英語のセリフとしては直接「また」という表現は出ていないが、ニュアンス的には「また」であっていると思われる。あの緊迫した状況のこの皮肉が出てくるあたりは、さすがのイギリス文学といったところだろうか。私はこのシーンで毎回軽く笑ってしまう。シリーズ中いちばん好きなシーンと言っても過言ではない。
ダンブルドアの殺害
スネイプ先生にとって心理的に最難関だったであろう仕事が「ダンブルドアの殺害」であろう。
おそらくは自力でのヴォルデモート妥当の可能性が本当にゼロになったと感じたダンブルドアが、自らが所有する「ニワトコの杖」をヴォルデモートに奪われないために「双方が納得した計画殺人」を発生させることで「ニワトコの杖」の忠誠心が自分から移ることなく死ぬという作戦を立てた。これで「ニワトコの杖」は永遠に誰のものにもならなくなるという寸法である。
そんな事するくらいなら折っちゃえばよかったのにと何度見ても思うのだが、それが出来ない理由が何かあったに違いない。うん、違いない。
ただ、結果的にはマルフォイによって「武装解除」された時点で杖の忠誠心がマルフォイに移ってしまい、誰も気づくことなく杖の真の所有者がマルフォイになってしまった。
さらに、ヴォルデモートは所有権がスネイプ先生に移っていると思いこんでいたので、スネイプ先生を殺すことによって杖の所有者になったと思いこんでいたが、実際にはそれより前にマルフォイを「武装解除」したハリーに所有権が移っていた、という自分で書いていても面倒な状況になっていた。一応ラストに至る流れをまとめると
- 図らずもダンブルドアを「武装解除」したマルフォイに所有権が移る
- その後スネイプ先によってダンブルドアが殺害されるが所有系に影響はない
- ハリーによってマルフォイが「武装解除」され、誰にも気づかれることなく所有権がハリーに移る
- スネイプ先生を殺害し所有権が移ったと考えたヴォルデモートはハリーに死の呪文をかけようとするが、杖が所有者を守るためにその魔法が自分に返ってきてしまう。
という事になっている。ただ、所有権がマルフォイに移ろうが移るまいが、形式的にはスネイプ先生がダンブルドアを殺害していることになっているので、ヴォルデモートにスネイプ先生が殺害されるという未来は確定的なものであったことになる。
つまり、ダンブルドアがスネイプ先生に命令したことは「自分を殺せ」ではなく「ヴォルデモートに殺されろ」であったということになる。この辺でようやくダンブルドアの怖さが見えてきたように思われる。
怖い怖いダンブルドア

彼にとっては全てが駒
本編中ダンブルドアはハリーにとっての心の支えであり「アズカバンの囚人」までは唯一の希望と言っても過言ではなかっただろう(結局唯一の希望になっちゃったけど)。
そんなダンブルドアだが、本編を見てみるとゆうほど善良の人ではないように思われる。まず第一に、ダンブルドアは自分が知っていることを基本的には誰にも話していない。二重スパイとして活動させていたスネイプにはわずかに話していたと思われるが、ダンブルドアの狙いを知ることが出来た人間はいなかったのだろう。
結局ダンブルドアは自分以外の誰も信用せずに強大な的であるヴォルデモートを駆逐しようとしていたように見える。常人では到底なし得ないような仕事を成し遂げ続けてきたダンブルドアにとって、自分以外の、そして自分ほど優秀でない魔法使いたちは結局のところ状況を作るための駒でしかなかったようにも思えてしまう。
ハリーのことについても、ヴォルデモートの魂の一部がハリーの中にあるという説明をスネイプ先生にした場面で以下のような会話がある:
Snape “So when the time comes, the boy must die? “ 訳 「つまり、時が来たらその彼は死ななくてはならないと? 」 Dumbledore “Yes. Yes. He must die.” 訳 「そう、その通り。死ななければならない。」 Snape “You’ve kept him alive so that he can die at the proper moment. You’ve been raising him like a pig for slaughter.” 訳 「あなたは彼が然るべきときに死ぬために生かしてきた。屠殺される豚のように。」 Dumbledore “Don’t tell me now that you’ve grown to care for the boy? “ 訳 「君は彼の面倒を見るために生まれてきたわけではないだろ?(情でも湧いたか?)」 ~中略~ Snape “So when the time comes, the boy must die? “ 訳 「つまり、時が来たら彼は死ななくてはならないと? 」 Dumbledore “Yes. He must die. And Voldemort himself must do it.” 訳 「そう。死ななければならない。そしてそれはヴォルデモートが実行しなくてはならない。」
これを聞けばダンブルドアにとってはハリーもまたヴォルデモート妥当のための道具に過ぎなかったし、何なら面倒な存在だったことが分かる。もちろんダンブルドアは死の秘宝を知っていたので、ハリーの復活が可能であることを知っていたかもしれないが、これはドラゴンボールがあるから地球を見捨てても良いと言っている悟空と同じで、結局は他者の命なんでなんとも思っていないわけである(クリリンのことは怒ったくせに)。
また、「ニワトコの杖」に関してダンブルドアが立てた作戦についても彼の隠された執着が見えるようにも思える。誰が考えたって折っちゃえば済むことなのに、彼は極めて技巧的な作戦を立てて「ニワトコの杖」を温存している。この不可解な事実も、実はダンブルドアが陰ながら「ニワトコとの杖」に執着しており誰にも渡したくなかったのだと考えれば理解しやすい。
ダンブルドアは彼が生きた時代に於いて、ヴォルデモートを除くと最高にして最強の魔法使いであった。そんな彼は自分が手に入れた最強の杖に深く執着していたのかもしれないし、それを平和的に使ってみせたのもそれまでの連中とは違うところを見せるという彼なりの自己顕示欲の表し方だったのかもしれない。
そして何よりも、ダンブルドアのスネイプ先生に対する要求は常軌を逸している。全てが明らかになって私が思ったことは、「ダンブルドアは裏切り者を決して許さない」ということであった。
別の言い方をするならば、愛するリリーの命を救うためにダンブルドアに助けを求めに来た段階で、ダンブルドアにとってスネイプ先生は「最高に都合の良い駒」になったに違いない。そもそも、ヴォルデモート側についた魔法使いの連中のことなんか腸煮えくり返るほどに嫌っていたことだろう。優秀な自分よりあんな奴についたわけだから。
あまり伝わらなかったかもしれないが、私は「ハリー・ポッター」という作品で描かれるアルバス・ダンブルドアという人物がとんでもなく怖い人物に思えるのである。身内でいるうちは極めて頼れる相手だが、結局は何を考えているか分からないし、そのうちに秘めた「自分は特別である」という思いに少しでも触れてしまったらどんな扱いを受けるか分からない。
ただ、ここまで考えるとダンブルドアとスネイプが「ハリー・ポッター」という作品の中で何故特別な関係の中で対ヴォルデモート作戦を遂行していたのかもわずかに分かるような気がする。
表裏一体の2人とハリーの子供の名前
結局の所、スネイプ先生が表面上見せている凶悪さや自尊心の大きさ皮肉っぽさが、誰にも知ることが出来なかったダンブルドアの内面であり、ダンブルドアが人々に見せている慈愛の姿というのが実のところスネイプ先生の内面の真実であったということになる。
原作者のJKローロングは、1人の人間を2つに分割することによって、人間の複雑さやうちに秘めた狂気、そして優しさを描こうとしたのかもしれない。
そのように考えると、ハリーの2人目の子供の名前
Severus Potter(アルバス・セブルス・ポッター)
は、実は2人の人物が1人の人物であったことを象徴的に現すものかもしれない。
ただ個人的にはスネイプ先生の方が好きなので「Severus Albus Potter」となってほしかった。
わずかに足を踏み外したが、いい男だったぜスネイプ!
おまけ:ハリーとマルフォイ

ダンブルドアとスネイプが表裏一体の存在だったという話をしたが、それはハリー・ポッターとドラコ・マルフォイに関しても同じだったかもしれない。
マルフォイは表面上、尊大で自信家で誰よりも自分が優れていることを信じている「嫌な奴」として描かれている。一方ハリーは謙虚で仲間思いな「いいヤツ」として描かれているのだが、これもダンブルドアとスネイプ先生との関係と同じだったように思える。
物語が進むにつれてマルフォイの善良さがどんどん表に出てきたが、それは突如現れたものではなくそもそもの彼の資質であり、父であるルシウス・マルフォイの教育故に抑圧されていたものに違いない。
一方ハリーは「ヴォルデモートの影響」という言い訳が通る状況で、度々その黒い部分を表に見せてきた。しかしそれは別に「ヴォルデモートの影響で生まれたもの」ではなくて「ヴォルデモートの影響で表に出たもの」に過ぎなかっただろう。
このように「ハリー・ポッター」という作品では「人間が本来持つ複雑さ」を表現するために、1つの人格を2つに分割して表現されているのだと思う。
別に「ハリー・ポッター」に限ったことではないと思うけれど。
この記事を書いた人
最新記事
- 2024年7月14日
「君たちはどう生きるか」のあらすじと考察ポイント【完全ネタバレ】 - 2024年7月14日
【君たちはどう生きるか】火事場を走る眞人シーンと高畑勲が目指したアニメーション表現 - 2024年7月3日
【ゴジラ(1984年)】あらすじと考察-ゴジラ復活を告げる小林桂樹の涙- - 2024年6月30日
【ゴジラvsビオランテ】あらすじとその面白さ-出現する2人の芹沢博士- - 2024年6月13日
【THE NEXT GENERATION パトレイバー 首都決戦】あらすじと考察-灰原零とは何だったのか?-