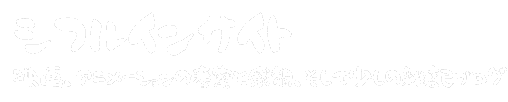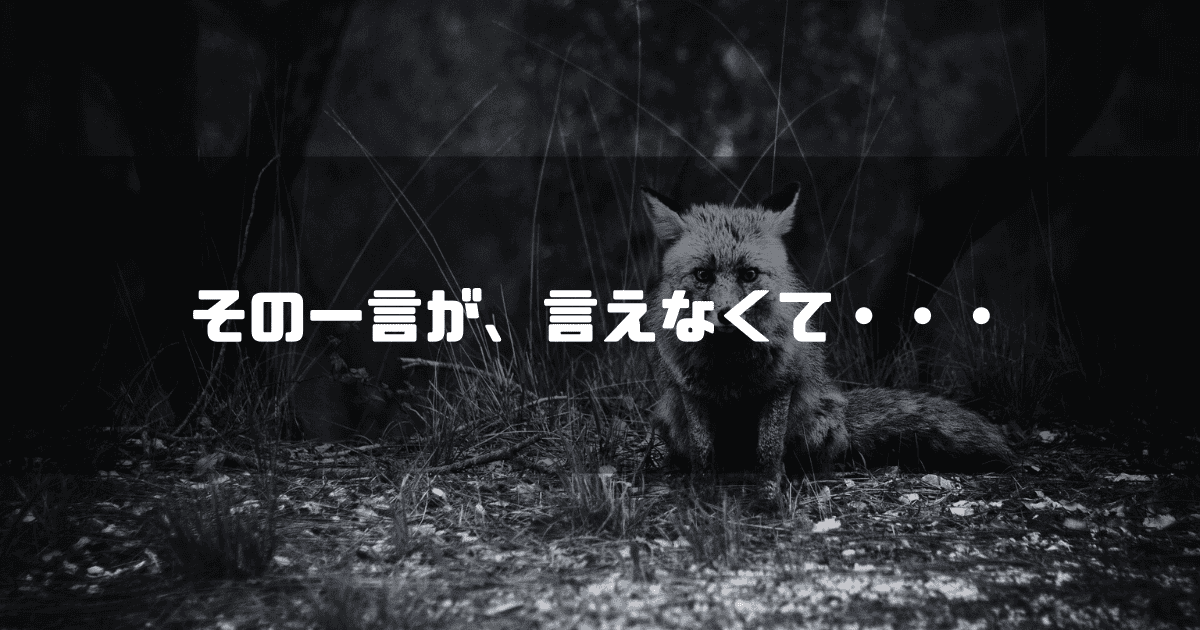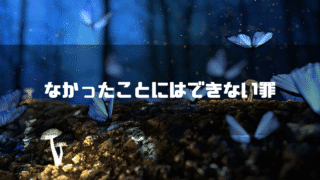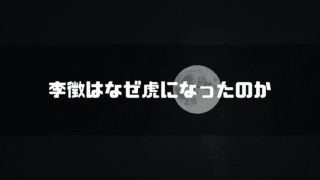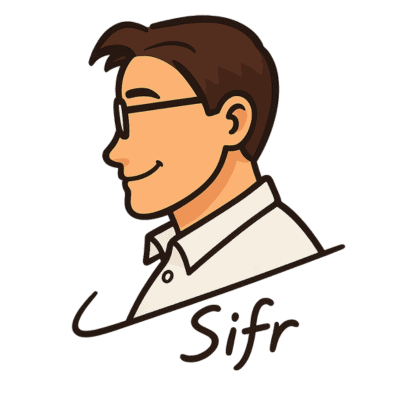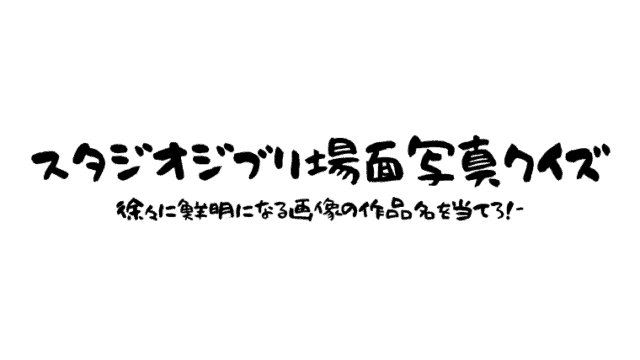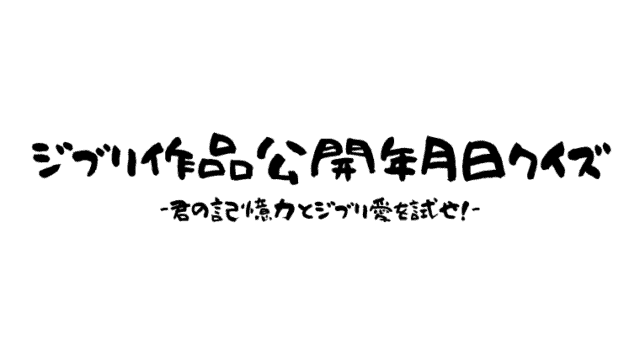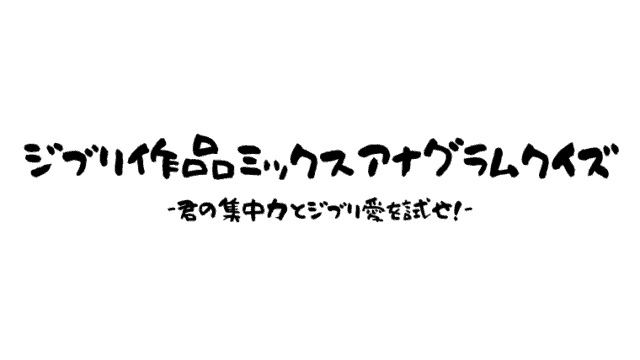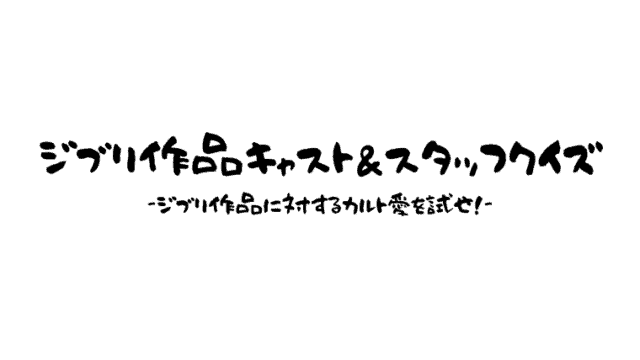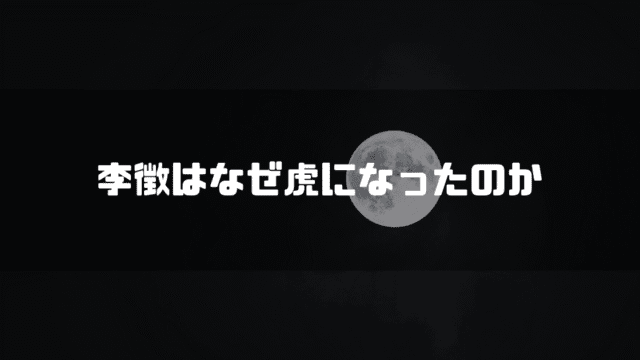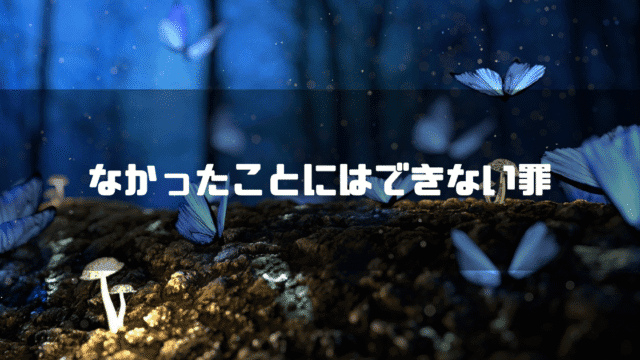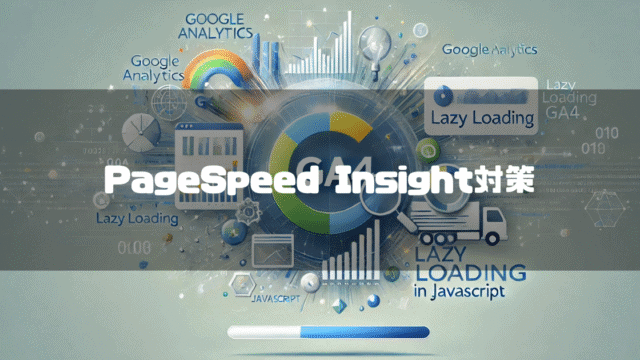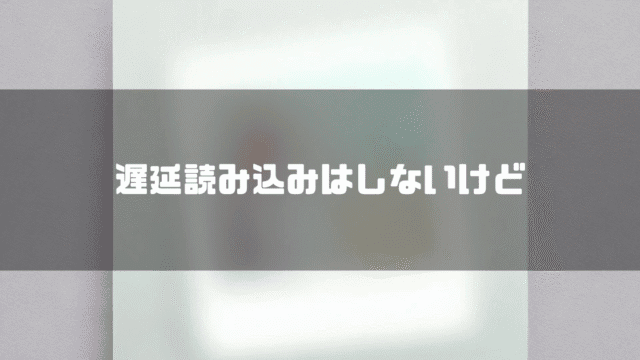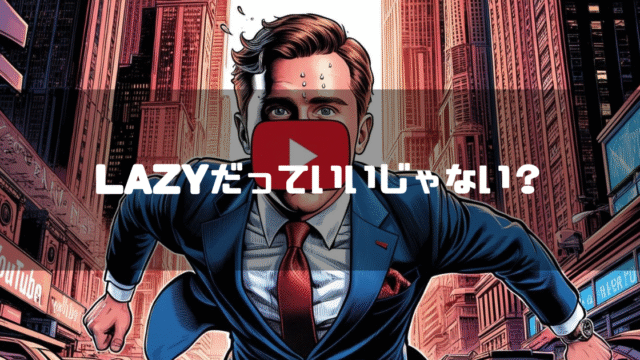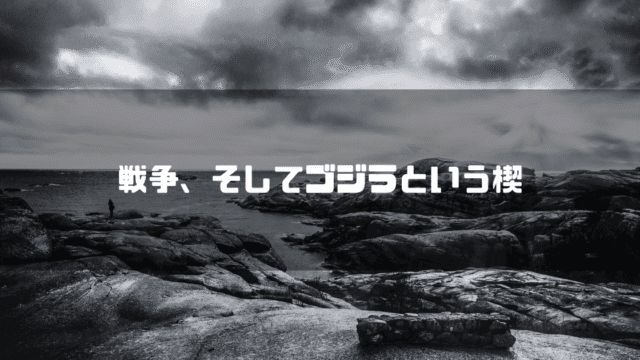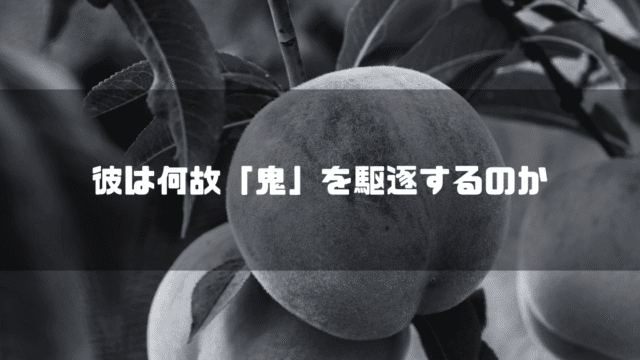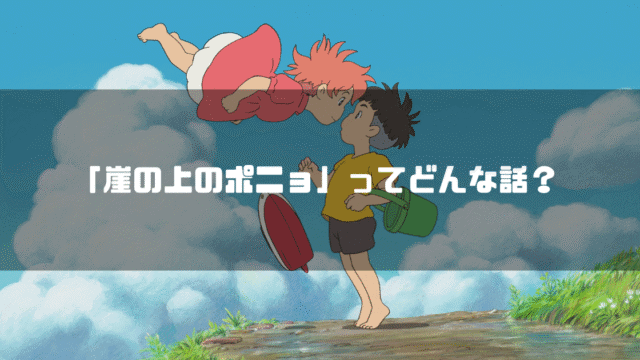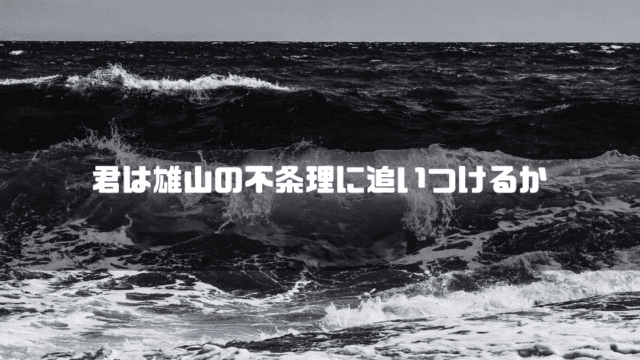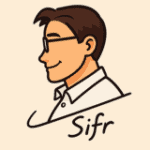「ごんぎつね(ごん狐)」は新美南吉(にいみなんきち)による児童文学作品である。wikipedia情報によると、著者が18歳の頃の作品で、1932年には「赤い鳥」という雑誌に掲載されている。物語の舞台は江戸時代末期から明治初期。まだ著者にとっては地続きの時代だっただろうか。
そんな「ごんぎつね」だが、おそらく多くの人が小学4年生の頃に教科書で読んだ作品であると思われる。私もその頃に読んだはずで、「ごん、お前だったのか。いつも栗をくれたのは」というセリフで締めくくられる物語に、子供ながらにやられてしまったことを覚えている。
今回は、そんな思い出の作品のあらすじを振り返り、その教訓として引き出せるものを考えていこうと思う。結局「ごんぎつね」はどういう話として噛みしめるべきなのだろうか?
- 「大切なことは言葉にしなければ伝わらない」
「ごんぎつね」の悲劇の本質は「言葉にしないと思いは伝わらない」というある意味当たり前の事実であり、言葉での意思疎通の重要性が浮き彫りになる。ごんが兵十に伝えられなかった思いが物語の衝撃的なラストを作り出す。 - 因果応報ではない
ごんの射殺は「因果応報」という単純な解釈だけでは説明できない。ごんが「いたずら狐」とされるのは人間の視点であり、実際にはごんの行動には根源的な罪は存在しない。 - 動物による物語の受け入れやすさ
「ごんぎつね」の物語は、動物が登場することでメッセージが過度に露骨にならず、受け入れやすくなる。人間の物語にすると直截的なメッセージとなり、読者の心に響きにくくなるが、狐というキャラクターによって柔らかく伝わる。
「ごんぎつね」のあらすじ
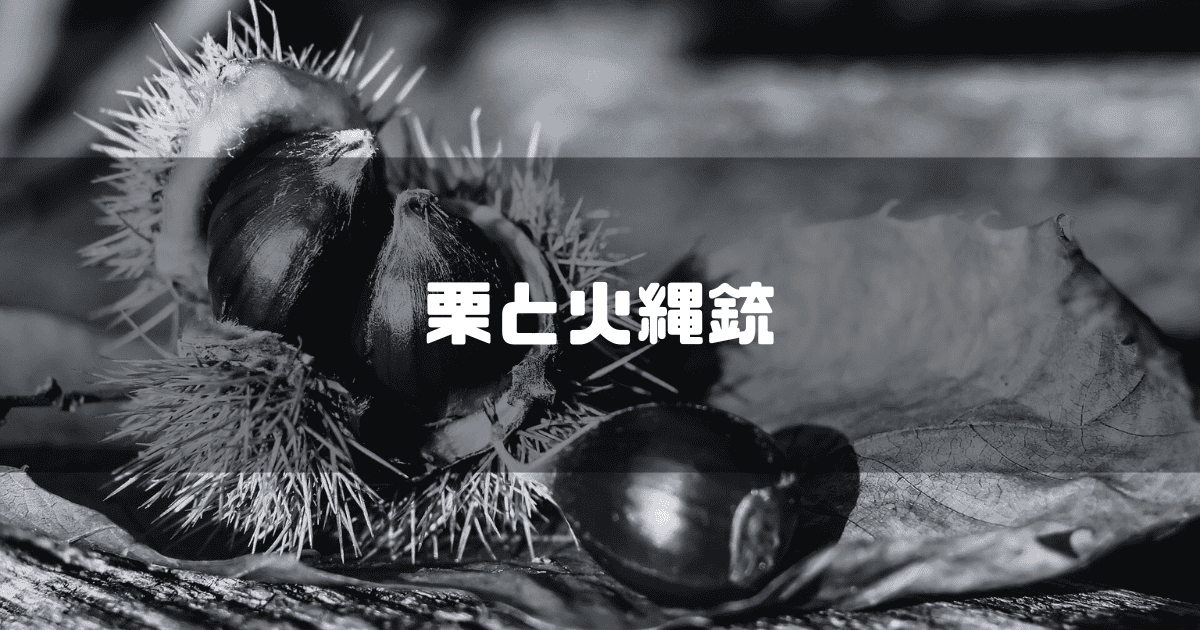
- ごんのいたずらと自責
ごん狐はいたずら好きで、村の人々を困らせていたが、ある日、兵十の母親の死を知り、自分が兵十の大切なものを奪ってしまったことを自責の念で悔やむ。その後、ごんは償いのために兵十に光るイワシや栗、松茸を届け続けるが、最終的に兵十に火縄銃で撃たれることになる。 - 兵十の誤解とごんの最期
兵十は最初、ごんが自分に栗を届けることに気づかず、恨みを晴らすために撃ってしまう。しかし、撃たれた後にごんが栗を落としたことにより、兵十は初めてごんの優しさと償いを悟り、悲しみながらその死を悼む。
ここからはもう少し詳しく「ごんぎつね」のあらすじを見ていこう。
うなぎ事件
物語は、その語り部が村の「茂平(もへい)」というおじいさんから聞いた話として始まる。
むかし、村から少し離れた山の中に「ごん狐(ごんぎつね)」という一人ぼっちの小狐がいました。ごんは近くの村に出没しては、いたずらをして村の人々を困らせていたのです。
そんなある秋の日、三日続いた雨があがり、ごんが村の近くの川辺まで出てくると、三日間の雨で増水した上に黄色く濁ったその川で「兵十(ひょうじゅう)」という男を見つけました。
兵十はそんな状況の川で「張り切り網」を使って魚をとっているようでした。ひとしきりの漁を終えると、兵十は魚籠(びく)の中に木切れもろとも網の中身を入れ、水の中に入れたのでした。
兵十はその場を離れたのですが、それを見ていたごんは、何やらいたずらをしたくなり、魚籠の中身を川の中に投げ込んでしまったのです。
ところが魚籠の中にいたうなぎが絡みつき、ごんは少々怯んでしまいます。戻ってきた兵十は「ぬすっと狐め!」とごんを追い立てますが、ごんはなんとか住処まで逃げ切り、絡みついていたうなぎの頭をかみくだいて、草の葉の上に載せておいたのでした。
兵十の母の死と光るいわし
それから十日ほどたったある日、ごんは村で兵十の母親の葬儀が行われていることを知りました。いつもとは打って変わってしおれた姿の兵十を見たごんは「兵十はきっと母親のためにうなぎをとっていなのだ、そのうなぎを自分は奪ってしまったのだ」と自責の年に駆られるのでした。
また別の日、ごんは一人寂しく麦をといでいる兵十の姿を目にしました。一人ぼっちになってしまった兵十に自分を重ねたごんは、近くに来ていたいわし屋のかごから光るイワシを取り出して、兵十の家に投げ込みました。ごんなりの償いだったようです。
いい気分のごんは、次の日には栗を兵十に持っていってやりました。ところがそこで、いわしの盗人扱いをされて殴られた兵十の姿を目にします。その姿を見たごんは、そっと栗を置くと、それから数日栗を兵十に届け続けました。しまいにはまつたけも持っていったのでした。
青い煙
そんなある日、ごんは兵十が加助(かすけ)という百姓と話している場所に出くわします。2人の会話に聞き耳を立てていると、どうやら2人は栗や松茸を兵十に与えているのは「神様」という結論に達したようでした。
ごんは不満でしたが、結局その次の日も兵十に栗を持っていってやりました。
しかしその日、裏口から家に入るところを兵十に見つかってしまいます。何も知らない兵十は、うなぎを奪われた恨みを晴らすべく、火縄銃でごんを撃ってしまったのです。
倒れたごんの手元から落ちた栗を見た兵十は「ごん、お前だったのか。いつも栗をくれたのは」とすべてを悟りました。
ぐったりと目をつぶる兵十がとり落とした火縄銃からは、青い煙が細く出ていました。
「ごんぎつね」の教訓

因果応報?
「ごんぎつね」という作品の教訓としてもっとも短絡的なものは「因果応報」であろう。兵十によってごんが射殺されるという事実を「結局はいたずらをしたごんにバチが当たっただけ」と考える立場である。もっと単純に言うと「悪いことをしてはいけないよ」というメッセージと捉える立場である。
もちろんそれで構わないのだけれど、これには重要な視点がかけているように思われる。つまり、「ごんぎつね」という物語は人間が語り部であって、ごんが「いたずら狐」であるという事実は人間の勝手に過ぎないのである。
うなぎを盗んだことだって、狐からすれば川にあった魚籠(びく)の中にあったうなぎただただ自然に頂いただけある。盗みかどうかは人間の主観が入るかどうかの問題に過ぎない。
このようにそもそもの「罪」がそれほど根源的なものになっていないので、「因果応報」と考えるのはあまりにも身勝手だろう。
大切なことは言葉にしなければ伝わらない
「ごんぎつね」という作品が衝撃的なラストを迎えるたった一つの理由は、「ごんが狐である」ということになるだろう。つまり、ごんは兵十と言葉を用いた意思疎通が出来ない存在になっている。
逆に言うと、たった一言ごんが兵十に「うなぎを盗んで悪かった」といえば終わった物語でもある。
ところがごんは狐であるが故にその一言を告げることが出来ず、栗、いわし、松茸を兵十にあたえるという「行動」しか出来なかったのである。物語を神の視点で見ている我々は、そんなごんの健気な思いが分かるのだが、そんなもの兵十には分からない。
それでもなお我々は衝撃のラストに「兵十なんで分かってあげられなかったんだ!」と心が揺さぶられてしまうわけである(うまいこと出来とる)。
結局の所「ごんぎつね」という物語から得られる教訓があるとすれば「大切なことは言葉にしなければ伝わらない」だろう。
これは別に「悪いことをしたら誤りなさい」ということではなく、より一般に自分が思っていることは言葉にしなくては伝わらないということである。言葉で伝えるというのは非常にストレスがかかることなので、我々はごんのように「行動」に移そうしてしまうのだが、そんなことよりもまず「言葉にする」ということが大切なことである。
そして「言葉にする」という初めの一歩を間違ってしまうと、その後にどんなことをしても状況は好転しないし、概ね悪化していく。このように考えると「初めの一歩を間違うな!」というメッセージも込められているのかもしれない。
いずれにせよ、青い煙が立ち込める前に、大事なことは言葉にしてみましょう。我々は小学生のころに「ごんぎつね」を読んだのですから。
おまけ:「ごんぎつね」に関するあれこれ

ここからは「教訓」にこだわらずに「ごんぎつね」に関するあれこれを考えようと思う。まずは何故、狐という動物が登場するのかということについて考えてみよう。
なぜ動物の物語なのか?
「ごんぎつね」に限らず、世界中に擬人化された動物が登場する物語が存在する。何故そのような「工夫」が必要になるのだろうか?
ひとつ考えられるのは、我々はどうしようもなく動物がすきだとうことだろう。動物は我々にとっては縄張り争いを今なお続ける存在であると同時に、何やら愛らしい存在でもあるし「ああ、動物と話してみたい」とその存在に思いを馳せる存在でもある。このような思いが、物語の中に動物を登場させる1つの理由にはなっているだろう。
しかし重要なのはもう一つのほうで、「動物の存在によって、物語を受け入れ可能なものにする」ということだと私は思う。
例えば「ごんぎつね」のメッセージが「大切なことは言葉にしましょう」だったとして、これは本来「人間の物語」である。狐のごんではなく、人間の権助あたりの物語に登場しなくてはならない。つまり、
ある秋の日に、権助がいたずらごころでうなぎを奪うが、それを兵十に告げられずに密かに贈り物をする。そんなことを続けていた権助だが、ある日兵十に見つかってしまい、盗人と間違えられた権助は殴り殺されてしまう。
というくらいの物語になるべきなのだが、こんな話読んでられないよね。そして何より「大切なことは言葉にしないと伝わらない」というメッセージが露骨に描かれすぎて「そんなこと分かってるよ」と思われて終わってしまう。本来はこういう露骨な物語になってしまうものを、動物に登場していいただくことによって、メッセージをぼかして「受け入れ可能なもの」にしているではないだろうか。
皆さんはどう思いますか?
教材としての「ごんぎつね」
おそらくほとんどすべての日本人は、「ごんぎつね」という作品を小学校の教科書で読んだと思うが、「教材としての『ごんぎつね』」を皆さんは覚えているだろうか。
正直に言うと私は完全に忘れている。
なにかしら授業をしてもらったはずなのだが、覚えているのは物語の内容であって授業ではない(先生ほんとにごめんなさい)。
ただ、自分なら教材としての「ごんぎつね」をどう扱うかと考えてみたくもなった。
私が思うに「視点の変更」が教材そしての素材になるのではないかと思う。つまり、ついつい我々はごんに感情移入しがちだが「ごんぎつね」を兵十目線の物語として再構成したらどうなるか?ということを考えさせるような教材になりうると個人的には思う。
それは「物事を一面的に見ない」ということを学ぶことでもあるし、何よりも兵十を許してやれることになるのではないかと思う。
実際はどういう教材として使われているのだろうか?本当に忘れてしまった。
この記事を書いた人
最新記事
- 2025年7月13日
【GQuuuuuuX(ジークアクス)】エンディング後の世界を考察-シャリア・ブルはシャアになり、セイラはハマーンになる- - 2025年7月3日
【GQuuuuuuX(ジークアクス)】シュウジの謎とアムロ・レイの所在を考察-違和感から読み解く作品の意図- - 2025年6月26日
【火垂るの墓】清太と節子はなぜ幽霊となって存在し続けているのか-こちらを見つめる清太が伝える物語のメッセージ- - 2025年5月29日
アシタカの「生きろ、そなたは美しい」と「ブスは死ね」をめぐって-集合論的(数学的)に徹底分析を試みる- - 2025年5月9日
【紅の豚】マダム・ジーナは何故ドナルド・カーチスを袖にしたのか-過去3回に渡る結婚の謎を考察-