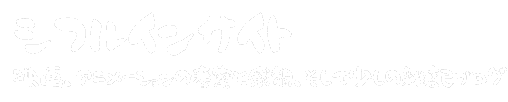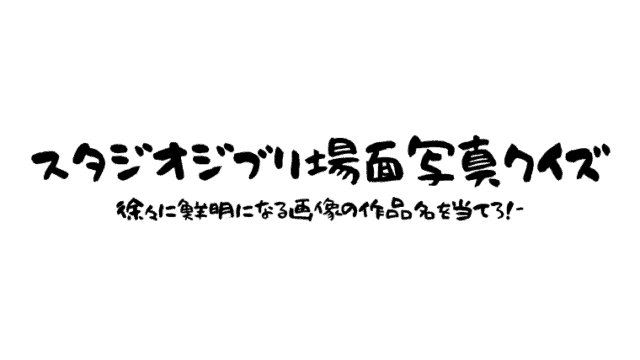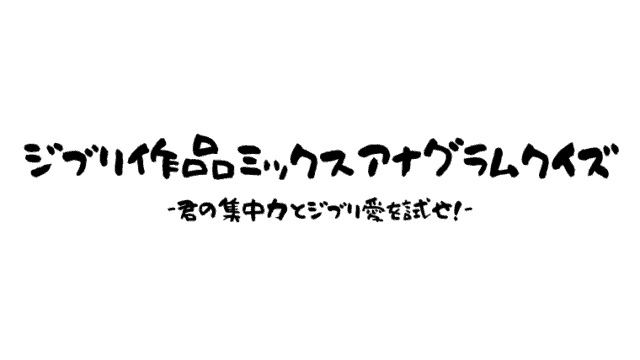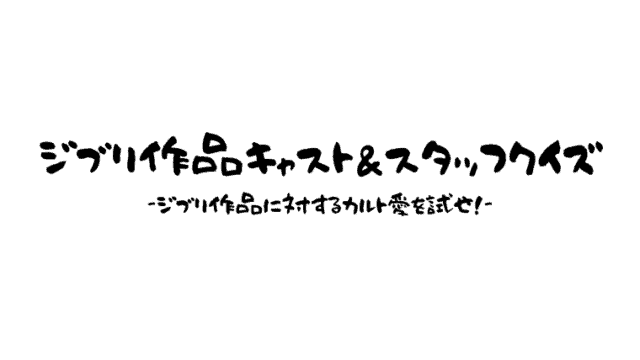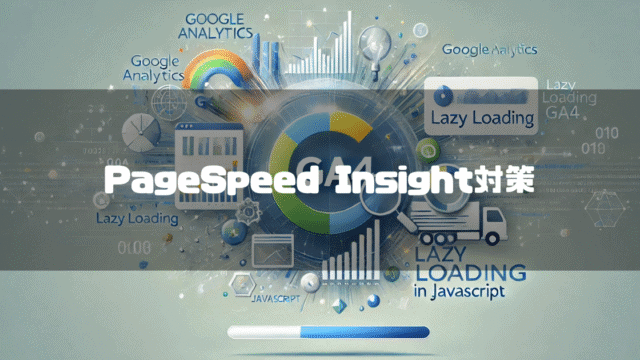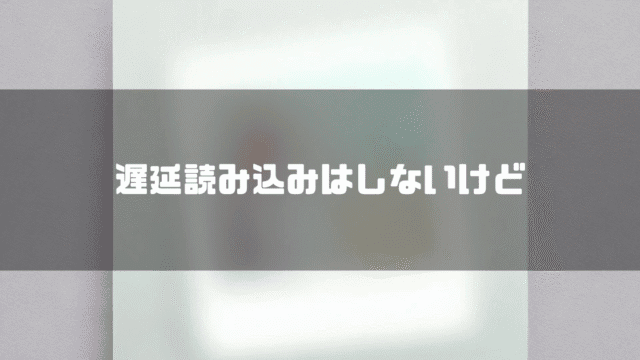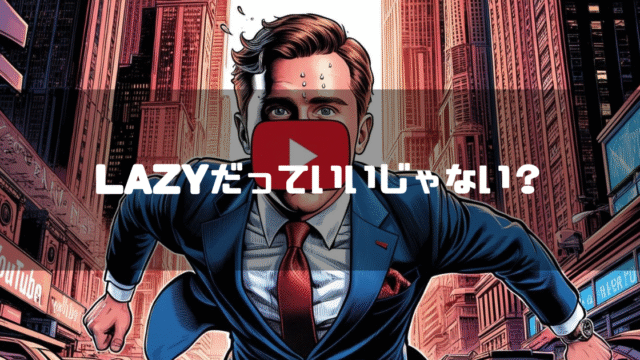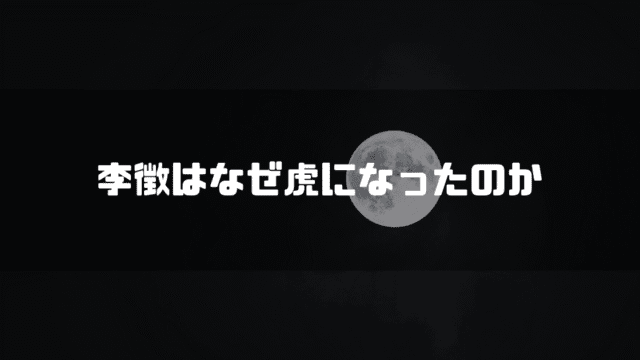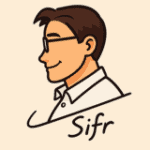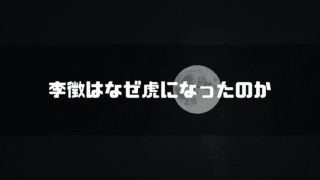「桃太郎(ももたろう)」は室町時代後期から存在するとされる昔話・おとぎ話である。
日本人の多くが、幼少期にこの物語に触れた経験があるだろう。私の場合は、幼稚園での読み聞かせや「まんが日本昔ばなし」だった。また、多くの昔話がそうであるように、現状我々が知る形になったのはどうやら明治期以降のようである。
必要はないと思うが、我々の知る「桃太郎」の大体のあらすじは以下の様なものであると思う:
昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。
おばあさんが川で洗濯をしていると、大きな桃が流れてきました。
その桃を持ち帰り、おじいさんと二人その桃を切ってみると、中から赤ん坊が元気に飛び出してきました。
子供のいなかった二人はその子に「桃太郎」と名付け大切に育てました。
みるみるうちに大きくなった桃太郎は、村を襲う鬼を退治する旅にでます。
大切な子供を心配しつつ、おばあさんの作ったきびだんごを持たせ、二人は桃太郎を送り出しました。
旅の途中、桃太郎はイヌ、サル、キジを仲間にし、鬼の居城「鬼ヶ島」に向かいました。
桃太郎たちは力を合わせて鬼を退治し、鬼ヶ島にあった金銀財宝を村に持ち帰ったのでした。
おしまい
物語の細部に関しては個々人で記憶しているものに差はあるだろうが、基本的には「英雄桃太郎が鬼を駆逐する物語」となっているだろう。
私にとっては何ら違和感のない物語であるが、時代は巡るもので、この物語における問題解決の暴力性に問題を感じる人もいるようである。
今回はそれでもなお「桃太郎」は暴力によって鬼を駆逐しなくてはならないのだという個人的な見解について述べようと思う。
ただ、色々考えてみると「暴力的で良くない」という意見と「暴力的でなくてはならない」という私の意見には本質的に差はないように思えてきた。表面上は真逆に思える主張ではあるのだが、これはいずれも日本人が持ち合わせているある種の優しさに端を発しているものだと思う。
ポイントは「物語を体験することの意味」と「鬼の本質と擬人化」だと思われる。
結局「桃太郎」とはどういう話だったのだろうか?
- 「鬼」の擬人化がもたらす暴力性への違和感
桃太郎一行による鬼退治の暴力性が問題視されるのは、鬼が人間のように意思や生活を持った存在として描かれているためである。話し合いによる解決を望む声もあるが、それが通じない「災厄」としての鬼を想定すると、暴力的解決にも一定の必然性が生じる。 - 「鬼」は自然災害などの擬人化である
桃太郎における鬼は、地震・疫病・台風など、人知を超えた「どうしようもない災厄」の象徴であり、これらに話し合いは通じない。ゆえに桃太郎の行動は「鬼を殺す」のではなく「鬼を祓う」行為として理解されるべきだと筆者は考えている。 - 物語体験は「心の塚」を築く行為である
桃太郎のような物語を読むことは、「振り返った時に自分の選択を問い直す」ための疑似体験であり、その中で「別の手はなかったか」と悩むこと自体が、人間的な深みや倫理観を育む営みである。実在しない存在だからこそ、暴力を描きつつも内省が可能となる。 - 桃太郎という物語の「再構築」の必要性
明治期に標準化された「桃太郎」は、現代社会の価値観との乖離を見せている可能性がある。だからこそ、原初的なバリエーションを掘り起こすか、現代的文脈で再解釈することで、より有意義に物語と向き合う必要があると筆者は提案している。
「桃太郎」という物語の意味と読み方

ここからは「桃太郎」がどういう物語だったのかを考えながら私の個人的な結論にたどり着きたいのだが、まずはなぜ「暴力性」が問題になるのかを考えていこう。
問題の本質:擬人化される「鬼」
「桃太郎」において主人公一団の暴力性が問題になる根源は「鬼が擬人化されている」という事実だろう。少なくとも、「命あるもの」として描かれていることにある。
彼らには角があるかもしれないし、我々とは肌の色が違うかもしれないし、体格も違うかもしれない。
それでもなお彼らにそれぞれに意思があり、悩みがあり、生活があり、家族がある。彼らの収奪にもなにか理由があるのかもしれない。
彼らの暴力性を肯定することはできないが、それを再び暴力によって解決しては負の連鎖である。そして何より「桃太郎」という物語を読む子どもたちに最初に教えるべき問題解決方法は「暴力」ではなく「話し合い」であるべきだ。
このように考えるのも無理からぬことである。なぜなら「鬼」たちにはきちんと人格があり説得可能と考えるからだ。なんとも人間らしく、そして日本人らしいやさしさにあふれる美しい態度、あるいはものの考え方である。
ところが、何故かこのような物の考え方を全面的に(あるいは素直に)受け入れられない自分がいる。それはなぜか?きっとそれは、私にとっての「鬼」はそんな生易しいものではないからだと思われる。
「桃太郎」における鬼とはなにか?
「桃太郎」における「鬼」だけであなく、我々日本人にとっての「鬼」とは結局、疫病、地震、台風、飢饉といったどうしようもない災厄の象徴であろう。
我々は未だにこれらの災厄に対する根本的な対抗策を持ち得ていない。疫病に関しても、事前に準備されたワクチンなど存在するはずもなく、新たな疫病で多くの人がなくなったあとに対応がなされるのである。
しかもそれ以外の災厄の場合は、本当にただ待つことしかできないし、ある意味出てしまった被害を「仕方のないこと」と諦めて状況回復に努める以外にない。科学技術の進歩は未だに我々から災厄を取り払っていないのである。
「桃太郎」においても、村の人々を襲っている「鬼」とはそういう「どうしようもない災厄」であり、だただ祈りながその災厄が通り過ぎることを待つしかなかったのである。
しかしそこに英雄桃太郎が現れた。
彼が打ち破ったものは今なお我々が対応不可能な「どうしようもない災厄」であり、そういう痛快さが本来「桃太郎」という物語の面白さであり物語が残り続けた理由だと思う。そして桃太郎が打ち破ったものが「災厄」だとしたら、彼は「鬼を殺した」のでは無く「鬼を祓った」のである。
では、彼らと「話し合い」をして祓うことはできるのだろうか?
災厄にはそもそも人格が無く、我々の生活を脅かすことについても何も感じていない。悪意も善意もない。ただそこにそのように存在しているにすぎない。そんな対象を象徴する「鬼」と「話し合い」をして状況を変えるなんてなんとも荒唐無稽すぎる話である。
したがって、どうしても「桃太郎」はある種の「暴力性」をもって描かれなくてはならないと私は考えてしまうのである。
ただ・・・ここで話を終えることはできない。結局私は「非暴力」を訴える同じ思考を辿ることになる。
物語体験とは「心の塚」を築くこと
前節で述べたように、「桃太郎」とは「どうしようもない災厄」を祓う物語であると私は思っている。ただ、そういう物語が「擬人化された災厄としての鬼」を用いて描かれていることは、結局は私の心にくさびのように残り続ける。
つまり、降りかかる火の粉は払わねばならないが、「自分が肯定してしまった桃太郎の行動は本当に正しかったのだろうか?」ともやはり考えてもしまう。本当は別の方法があったのではないか?
その瞬間その瞬間に我々は懸命に生きるのだけれど、振り返った時に自分の行動に疑問を持つことはあるだろう。歴史的に見るとそういう時に日本人は神社や塚を築いて、自分たちが振り切ってしまったなにかを追悼してきたのだろうと思う。日頃はそのなにかを忘れて生きているしそのようにするしかないのだけれど、そういった記念碑を目にする度に「別の手はなかったのか」と思い起こすのである。
「物語を体験する」ということはまさにこういう思いを擬似的に感じることなのではないだろうか?
「桃太郎」でいうなら、日々怯えて暮らす村人にとっての「鬼」とは「降りかかる火の粉」である。その生活を守るためにも払えるものなら払いた。その思いは切実なものである。しかもなおその「鬼」達は基本的に話し合いなどに応じない。そんな「鬼」を英雄桃太郎が暴力によって祓うのだけれど、一度平安を手にしたとき「それ以外の手はなかったのだろうか?」と思い悩むのである。
重要なポイントの一つは、被害者としての村人も鬼も、そして加害者としての村人(桃太郎)も鬼も存在してないということである。実在する対象なら思い悩んでいる暇はないのかもしれないが、彼らはそもそも存在していない。だからこそ暴力性を描くことができるし、思い悩んでもいられる。
そしてそのような形で「他にも手はあったのではないだろうか?」と思い悩むことそのものが、心の中に「神社」や「塚」を築くことであり、一面的ではない人間性を育むことになるのではないだろうか。
以上のことが大体私が「桃太郎」について思うところであるが、そもそも論に戻るなら「桃太郎」という物語にそろそろ限界が来ているということなのかもしれない。
我々が知る「桃太郎」は明治期に教科書に載せるために標準化されたものであろうし、そんなものを後生大事にするくらいなら、より古く原初的な桃太郎を発掘し切ることによって「歴史的遺物としての桃太郎」を楽しんだ方がより良いのかもしれない。
ただ、本文で述べたように、結局のところ絶対的なものの見方どないだろうから、「桃太郎」という物語の扱い方についても思い悩むほかないのだろう。
おまけ:桃太郎のお供の順番問題
桃太郎のお供といえば、イヌとサルとキジだろう。これについては概ね同意してもらえるのではないだろうか。ところが、どの順番でお供になったかとなると少々話が変わってくるかもしれない。
私にとってその順番は、イヌ、サル、キジの順番である。かつての私にとってこの順番は普遍的なものであり、日本中の人々にとって共通のものと信じていた。いや、「信じる」という感覚さえ必要のない常識であった。
ところがどうもそうではない言う事を知ったのは、アマゾンプライムで偶然見た「まんが日本昔ばなし」の「桃太郎」であった。そこではお供になる順番が、サル、イヌ、キジとなっていたのである。
全くもってどうでもいいことであるが、私にとっては十分に衝撃的なことだった。
皆さんの記憶にある「桃太郎」ではどの順番であの三匹がお供になったでしょうか。お時間があればアンケートに答えていただければと思います:
この記事を書いた人
最新記事
- 2025年7月3日
【GQuuuuuuX(ジークアクス)】シュウジの謎とアムロ・レイの所在を考察-違和感から読み解く作品の意図- - 2025年6月26日
【火垂るの墓】清太と節子はなぜ幽霊となって存在し続けているのか-こちらを見つめる清太が伝える物語のメッセージ- - 2025年5月29日
アシタカの「生きろ、そなたは美しい」と「ブスは死ね」をめぐって-集合論的(数学的)に徹底分析を試みる- - 2025年5月9日
【紅の豚】マダム・ジーナは何故ドナルド・カーチスを袖にしたのか-過去3回に渡る結婚の謎を考察- - 2025年5月1日
【君たちはどう生きるか】青サギ(サギ男)のモデルとなった鈴木敏夫のおもしろ「サギ」列伝-スタジオジブリを支えた辣腕の歴史-