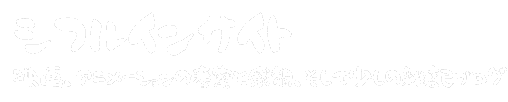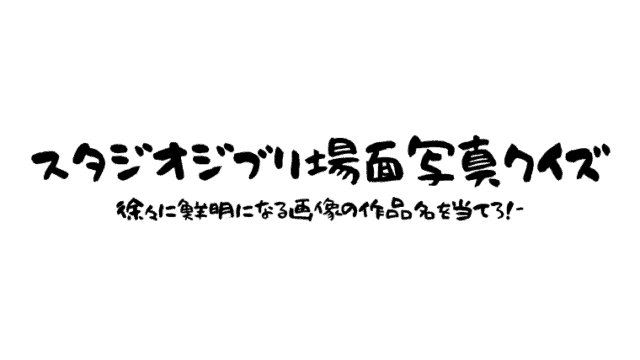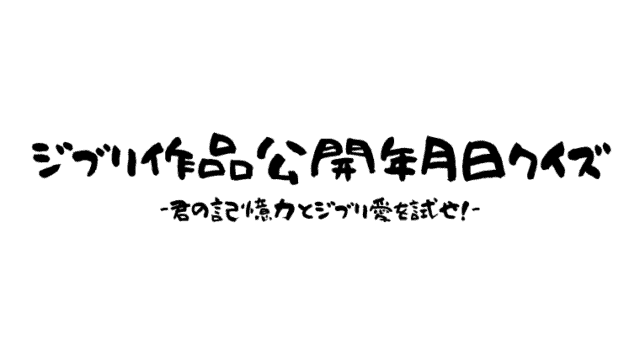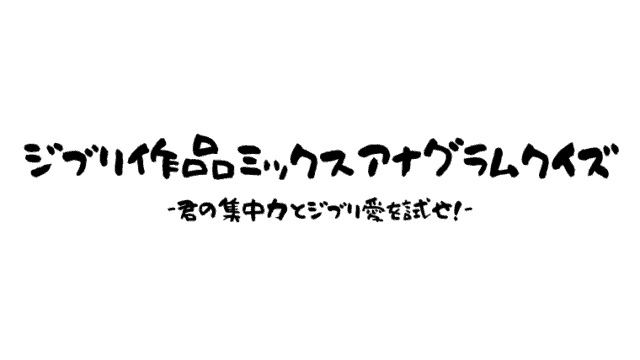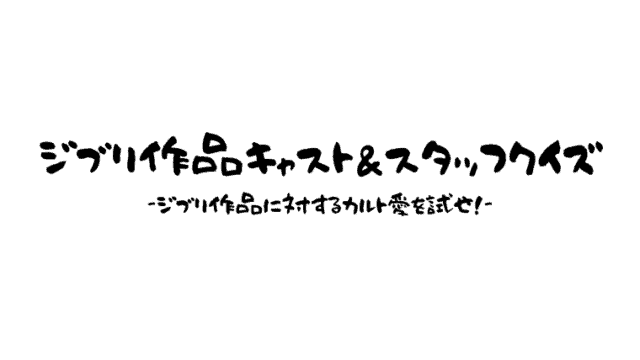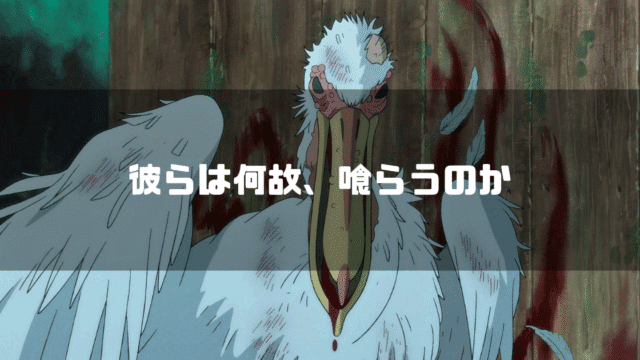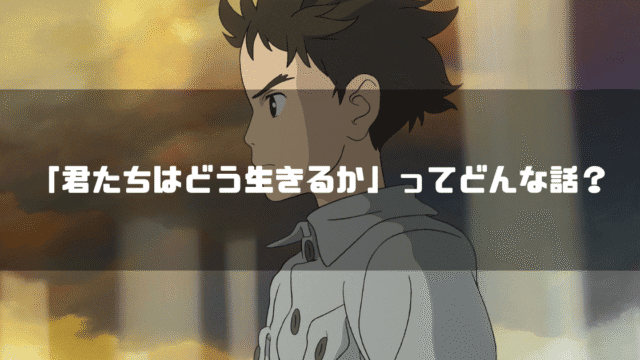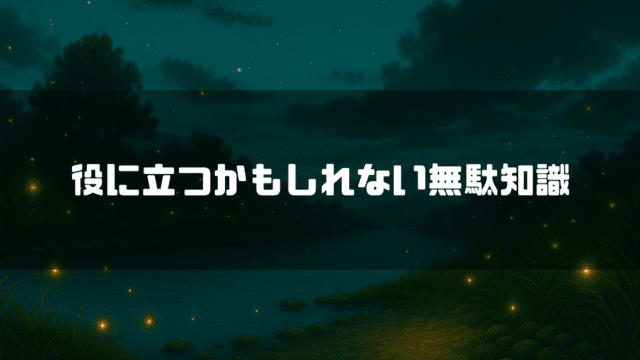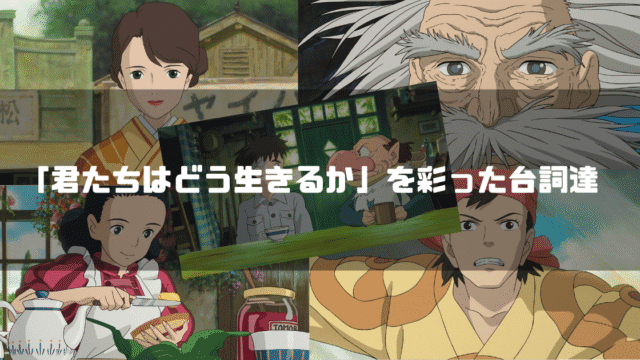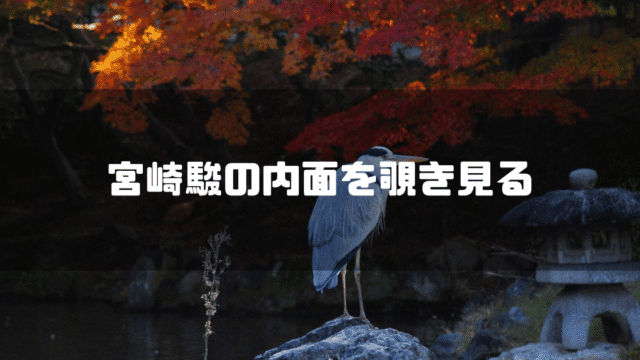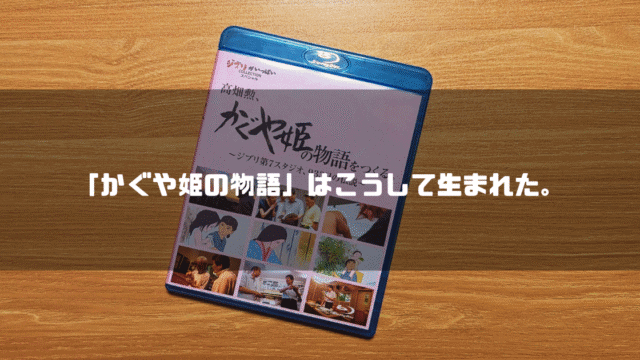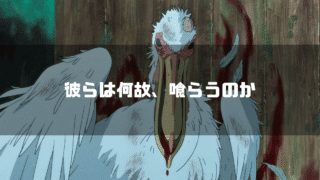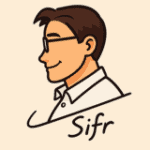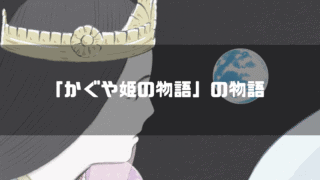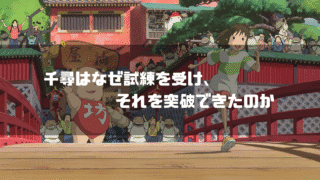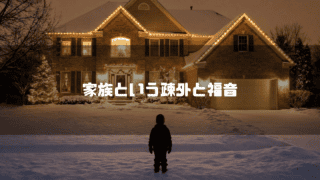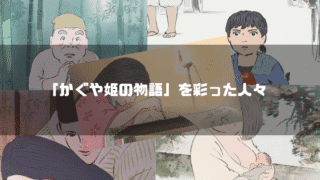【君たちはどう生きるか】冷たい8個の石と13個の石は何を意味するのか-「8」と「13」の数字に込められた思いを考察-
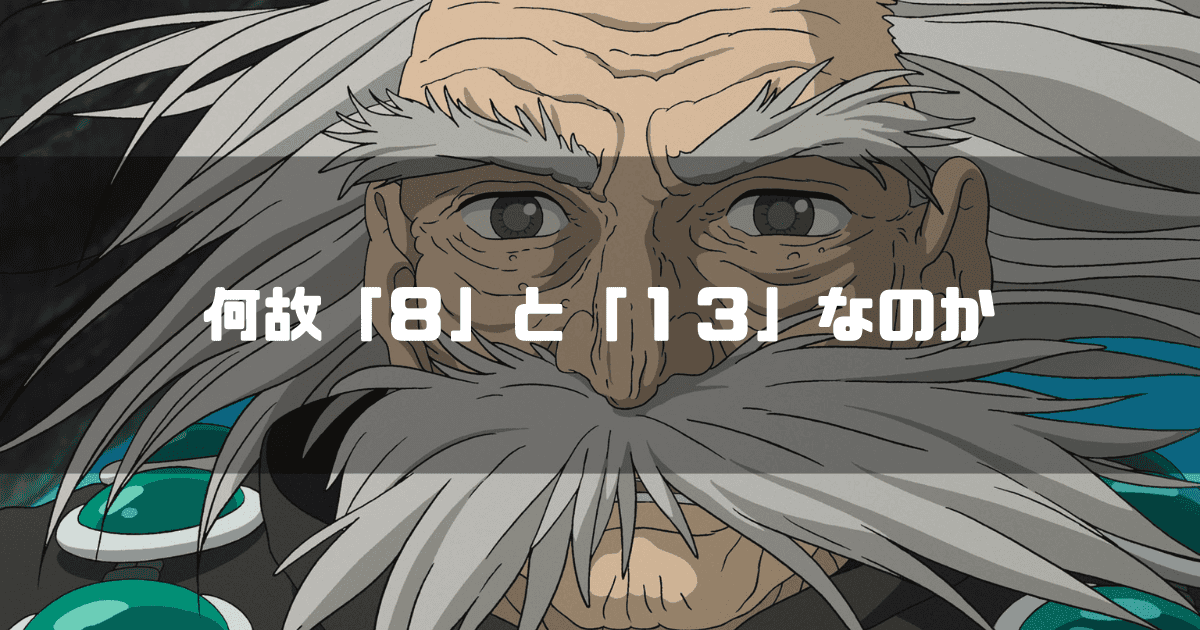
「君たちはどう生きるか(スタジオジブリ公式)」は2023年に公開された宮崎駿監督による劇場用アニメーションである。
今回は映画本編で描かれた「冷たい石」の意味について考えていこうと思う。
プロデューサーの鈴木敏夫さんがいろんなところで発言しているように、この作品は宮崎監督の自伝的作品である。そして本編の流れを考えれば、「冷たい13個の石」が表しているのは宮崎監督が作り上げてきた作品たちであることはほぼ明らかなように思われる。
基本的にはそれで終わりで十分なのだけれど、どうしても気になるのは「8」と「13」という数字である。「『8』ってなんのことだ?」と思うかも知れないが、物語のラストで13個の石を大伯父が眞人に見せているシーンで、大伯父本人がすでに積み上げた「崩れそうな石」が映し出されるが、そこで積まれている石の数が8個となっている。
たかだか数字なのだが、これが意外と厄介で、ジブリ作品や宮崎作品、そして高畑作品をいろんな観点から数えてみても、なかなかうまく「8」と「13」になってくれない。ただ、ある観点に立つとこの数字に合致させられることが分かる。
今回はこの「8」と「13」という数字が何を意味していたのかを解き明かしていこうと思う。そのためのヒントとなるのは「大伯父」のモデルである高畑勲と宮崎駿との人間関係である。まずはそこを振り返ろう(なお、作品全体のあらすじや、大伯父・父・母の象徴、インコとペリカンの謎など、他の考察については「『君たちはどう生きるか』あらすじ・考察まとめ」で解説している)。
この記事の内容を、AIが対話形式(ラジオ形式)で分かりやすく解説してくれます。
-
大伯父と冷たい石―苛烈な創作現場の象徴
大伯父は高畑勲と宮崎駿の双方を投影した存在であり、塔と下の世界はスタジオジブリおよび宮崎駿の脳内を象徴する。冷たい石は、過酷な制作過程で築かれた過去作品そのものである。 -
「8」と「13」の数字―共作と単独作を分かつ境界
8個の石は高畑勲と協働した8作品、13個の石は高畑が関与しなかった13作品を示す。石を積む行為は創作の功績と重荷を可視化する装置である。 -
眞人の拒絶とインコ大王―自己批判からの再出発
眞人が13個の石を拒絶する場面は宮崎駿による過去手法への自己批判と観ることができるが、最終的に石を持ち帰る行為は「終わらない人」宮崎駿の新たな創作決意を示すものである。
冷たい8個の石と13個の石の数字の意味の考察
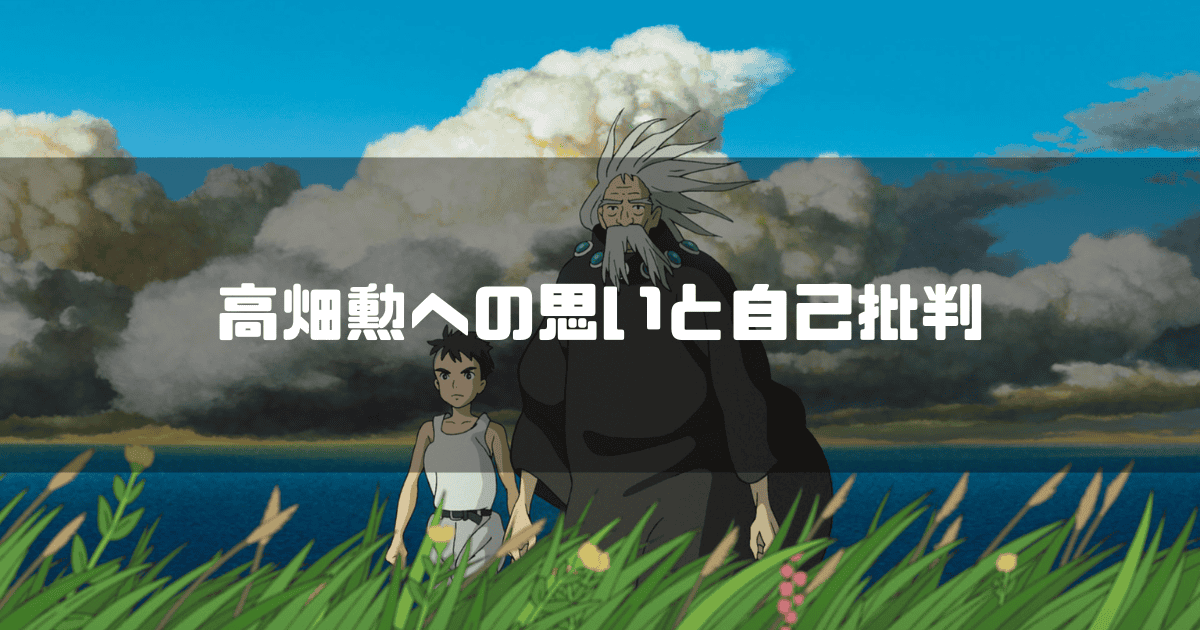
大伯父が象徴するもの-宮崎駿と高畑勲の関係と制作年表-
大伯父と塔のモデル
冷たい石の数が意味するところを考えるためには「大伯父」そして「下の世界」がどういったものを象徴しているかを考える必要があるが、その点に関しては「大量のインコとペリカンは何を意味するのか#大伯父の塔と下の世界-作品理解の準備- 」に、ドキュメンタリーでの発言やインタビュー内容を引用し詳しく書いているが、内容をまとめると以下のようになる。
「君たちはどう生きるか」は宮崎駿監督の自伝的要素が強い作品であり、
- ジブリの鈴木敏夫プロデューサーは「塔」を「ジブリ」に例えており、作品全体が宮崎駿の脳内や創作世界を象徴していると考えられる。
- 主人公・眞人は宮崎駿の分身(なりたかったもう一人の自分)として描かれている。
作中の「大伯父」は、モデルが高畑勲監督であると明言されているが、
- 単なるモデルではなく、宮崎駿自身も投影されている。
- 「創作」という要素を背負う以上、大伯父には宮崎駿の人生観や葛藤も重ねられている。
宮崎駿と高畑勲の関係性は以下のように整理できる:
- 高畑勲は宮崎駿の才能を見出した「師匠」であり、若い頃から共同作業を行ってきた。
- 互いに尊敬の念を抱きながらも、それぞれの創作理念には違いが生まれていき、お互いに強く批判することもあった。
これらを踏まえると、「君たちはどう生きるか」で描かれる「大伯父」は、単なる高畑勲の投影ではなく、宮崎駿自身と彼の創作人生をも象徴する存在であると理解できる。
更に、「大量のインコとペリカンは何を意味するのか#ドキュメンタリーでの宮崎駿の発言」でまとめたように、宮崎駿のアニメーション制作現場は過酷なものであり、その結果として「友達を失った」と宮崎駿が感じるほどである。
また、高畑勲の制作現場も過酷なものであり、鈴木敏夫は「ジブリの教科書19 かぐや姫の物語(PR)」で次のような強烈な事を語っている(『耳をすませば』の監督 近藤喜文さんの回想として):
最初で最後の監督作となった『耳をすませば』のキャンペーンで仙台を訪れた日の夜、高畑さんのことを話しだしたら、止まらなくなりました。「高畑さんは僕のことを殺そうとした。高畑さんのことを考えると、いまだに体が震える。」そういって二時間以上、涙を流していました。
この文章だけを引用するのはまさに「切り抜き」なので、高畑監督に関する情報を色々調べてほしいのだが、それでもなお高畑勲のアニメーション制作現場の苛烈さの一端は分かると思う。
しかし、高畑勲と共に仕事をした人々の思いの一側面は捉えていると思う。
以上のことを前提にすると、大伯父が積み上げた石や、集めた石がなぜ「冷たい」と表現されていたのかが分かるだろう。優れた美しい作品ではあったが、そこに至る道は極めて苛烈なものであったということになる。
そして、宮崎駿はそんな人と一緒に仕事をしていたのである。本当のことを言うともう少し準備が必要な気もするのだが、ここまでくればある程度私の考えを分かってくれると思う。
高畑勲と宮崎駿の作品制作年表
上で振り返った宮崎駿と高畑勲の人間関係の補完資料として、2人の制作年表を振り返る。
| 公開年 | 作品 | プロダクション | 宮崎駿の役割 | 高畑勲の役割 |
|---|---|---|---|---|
| 1968年 | 太陽の王子 ホルスの大冒険 | 東映動画 | 原画・美術設定・場面設計 | 監督 |
| 1972年 | パンダコパンダ | Aプロダクション | 原案・脚本・場面設定・原画 | 監督 |
| 1973年 | パンダコパンダ 雨ふりサーカスの巻 | Aプロダクション | 原案・脚本・場面設定・原画 | 監督 |
| 1974年 | アルプスの少女ハイジ | ズイヨー映像 | 場面設定・画面構成 | 演出・監督 |
| 1976年 | 母をたずねて三千里 | 日本アニメーション | 場面設定・レイアウト | 演出・監督 |
| 1978年 | 未来少年コナン | 日本アニメーション | 原作・脚本・絵コンテ・監督 | ? |
| 1979年 | ルパン三世 カリオストロの城 | 東京ムービー新社 | 監督・脚本 | ? |
| 1979年 | 赤毛のアン | 日本アニメーション | 場面設定・画面構成 | 監督 |
| 1984年 | 風の谷のナウシカ | トップクラフト → ジブリ準備室 | 原作・脚本・監督 | プロデューサー |
| 1986年 | 天空の城ラピュタ | スタジオジブリ | 原作・脚本・監督 | プロデューサー |
| 1988年 | となりのトトロ | スタジオジブリ | 原作・脚本・監督 | ? |
| 1988年 | 火垂るの墓 | スタジオジブリ | ? | 監督・脚本 |
| 1989年 | 魔女の宅急便 | スタジオジブリ | 脚本・監督 | 音楽演出 |
| 1991年 | おもひでぽろぽろ | スタジオジブリ | 製作プロデューサー | 監督 |
| 1992年 | 紅の豚 | スタジオジブリ | 原作・脚本・監督 | ? |
| 1994年 | 平成狸合戦ぽんぽこ | スタジオジブリ | 企画 | 監督・脚本 |
| 1995年 | 耳をすませば | スタジオジブリ | 企画・脚本・絵コンテ・製作プロデューサー | ? |
| 1997年 | もののけ姫 | スタジオジブリ | 原作・脚本・監督 | ー |
| 1999年 | ホーホケキョ となりの山田くん | スタジオジブリ | ? | 監督・脚本 |
| 2001年 | 千と千尋の神隠し | スタジオジブリ | 原作・脚本・監督 | ? |
| 2004年 | ハウルの動く城 | スタジオジブリ | 監督・脚本 | ? |
| 2008年 | 崖の上のポニョ | スタジオジブリ | 原作・脚本・監督 | ? |
| 2011年 | コクリコ坂から | スタジオジブリ | 企画・脚本 | ? |
| 2013年 | 風立ちぬ | スタジオジブリ | 原作・脚本・監督 | ? |
| 2013年 | かぐや姫の物語 | スタジオジブリ | ? | 監督・脚本 |
| 2023年 | 君たちはどう生きるか | スタジオジブリ | 原作・脚本・監督 | ? |
2人の関係は東映動画に始まるが、スタジオジブリで制作された「おもひでぽろぽろ」以降はお互いの関与が極めて希薄になっていることが分かると思う。少なくとも、映画製作という観点での「主要スタッフ」としてはお互い参加していないように思われる。
ここからはいよいよ「8」と「13」という数字の意味を考えていこう。
「8」と「13」という数字の意味
上でまとめた宮崎駿と高畑勲の関係性を前提として、「8」と「13」という数字が何を意味していたのかを考えていこうと思う。まずは私がたどり着いた結論から。
結論-高畑勲との共作とそうでない作品の数-
まずは結論をまとめると、8個の石は以下の8作品:
| 作品名 | 公開年 | 宮崎駿の役職 | 高畑勲の役職 |
|---|---|---|---|
| 太陽の王子 ホルスの大冒険 | 1968年 | 原画・美術設定・場面設計 | 監督 |
| パンダコパンダ | 1972年、1973年 | 原案・脚本・場面設定・原画 | 監督 |
| アルプスの少女ハイジ | 1974年 | 場面設定・画面構成 | 演出・監督 |
| 母をたずねて三千里 | 1976年 | 場面設定・レイアウト | 演出・監督 |
| 赤毛のアン | 1979年 | 場面設定・画面構成 | 演出・監督 |
| おもひでぽろぽろ | 1991年 | 製作プロデューサー | 監督 |
| 風の谷のナウシカ | 1984年 | 原作・脚本・監督 | プロデューサー |
| 天空の城ラピュタ | 1986年 | 原作・脚本・監督 | プロデューサー |
「パンダコパンダ」については、1972年公開の「パンダコパンダ」と1973年に公開された「パンダコパンダ 雨ふりサーカスの巻」をひとつとして扱っている。
13個の石は以下の13作品:
| 作品名 | 公開年 | 宮崎駿の役職 |
|---|---|---|
| 未来少年コナン | 1978年 | 原作・脚本・絵コンテ・監督 |
| ルパン三世 カリオストロの城 | 1979年 | 監督・脚本 |
| となりのトトロ | 1988年 | 原作・脚本・監督 |
| 魔女の宅急便 | 1989年 | 脚本・監督 |
| 紅の豚 | 1992年 | 原作・脚本・監督 |
| 耳をすませば | 1995年 | 企画・脚本・製作プロデューサー |
| On Your Mark | 1995年 | 原作・脚本・監督 |
| もののけ姫 | 1997年 | 原作・脚本・監督 |
| 千と千尋の神隠し | 2001年 | 原作・脚本・監督 |
| ハウルの動く城 | 2004年 | 脚本・監督 |
| 崖の上のポニョ | 2008年 | 原作・脚本・監督 |
| コクリコ坂から | 2011年 | 企画・脚本 |
| 風立ちぬ | 2013年 | 原作・脚本・監督 |
上の作品群には「平成狸合戦ぽんぽこ」と「かぐや姫の物語」の2作品が入っていないが、その理由も込めて上の表のようになる理由を解説していく。
解説-眞人の決断とインコ大王が意味するもの-
「8」と「13」の数字を考えた時、重要なことのひとつは「大伯父」には高畑勲だけではなく、宮崎駿も投影されているということだろう。
「大伯父」を高畑勲だけ、宮崎駿だけ、と考えると冷たい石の数字の意味が分からない。
結局上で挙げた8作品は「宮崎駿が高畑勲と共に作った作品」であり、13作品は「高畑勲が関わらなかった作品」ということになる。厳密なことを言うと「未来少年コナン」は高畑勲の「ヘルプ」が入っていたという話があるし、「魔女の宅急便」は音楽演出として高畑勲が関与してはいるが、担当が「音楽」ということなので今回は外している。
「高畑勲と共同で作った」という観点では、実写ドキュメンタリーの「柳川堀割物語(1987年、監督高畑勲、制作宮崎駿)」もあるが、実写作品ということで排除している。
また、「13個の石」の中には必ずしも宮崎駿が監督をしていない作品が入っているが、それは「8個の石」の中に高畑勲が監督していない作品が入っているのと同じ状況である。また、「耳をすませば」は絵コンテまできっているし、「コクリコ坂から」も脚本という重要な役割を担っているので、宮崎駿が関わった作品として考慮しないほうが問題とも言えると思う。
さらに、「平成狸合戦ぽんぽこ」と「かぐや姫の物語」は、高畑勲監督作品であるものの、宮崎駿の関わりが希薄であることから「8」と「13」の候補から外れている。
大伯父が積み上げた「冷たい石」としてラスト付近で描写されるのは8個の石だが、その前に描写されたテーブルの上にある石を数えると全部で10個となっている。それが「平成狸合戦ぽんぽこ」と「かぐや姫の物語」と観ることができると思うのだが、場面によっては9個にも見える場合があり、大伯父が積み上げた石の数についてはけっこう微妙なところがある(「下の世界」の崩壊が始まって散らばった石は全部で11個だった)。
さて、「冷たい石」が苛烈な現場で懸命に作り上げてきた作品群であることはなんとなく見て取れると思うが、問題はそれを「8個」と「13個」に分けたことである。
その分割を理解するヒントとなるのは、大伯父が集めてきた13個の石を眞人に渡そうとし、それを眞人が拒絶、最終的にはインコ大王がそれを積み上げるという描写だろう。
インコ大王についても鈴木敏夫は「SWITCH Vol.41 No.9 特集 ジブリをめぐる冒険」におけるインタビューで鈴木敏夫は以下のように証言している:
宮さんは「インコ大王は自分だ」と言う。そして「なりたかったもう一人の自分が眞人だ」と言っていました。
宮崎駿の分身であるインコ大王がそれを積み上げたのだから「13個の石」は宮崎駿が作り上げた作品群であり、眞人が石を拒絶したということは、その13作品を作り上げたその状況や手法に対する自己批判という事になるだろう。
そして、「8個の石」を積み上げたのは大伯父であり、大伯父には宮崎駿と高畑勲の両方が投影されているとすると、それは共同で作った作品群ということになると思う。
最終的に眞人はその「冷たい石」を拒絶しつつも現実世界に持ち込んでしまっている訳だが、その意味は、「新たな形の作品づくりの決意」と観ることができるのではないだろうか。
「君たちはどう生きるか」は宮崎駿の自伝的作品であり、多くの自己批判も見て取れる。しかし、最終的には新たな出発点となっており、まさに「終わらない人 宮崎駿」を象徴する作品となっていたのだと思う。
以上が私の考えた「冷たい石」の「8」と「13」という数字の意味でございます。まず数字が先にあって、それに合わせるために色々考えたので、異論はあるとは思います。ただ、そんなに的外れとも言えないのではないかとも思います。
皆さんは「8」と「13」という数字の意味をどのように考えたでしょうか。
なお、本作の詳細なあらすじや、もう一つの大きな謎である「インコとペリカンは何のメタファーなのか」など、作品全体については「『君たちはどう生きるか』あらすじ・考察まとめ」で網羅的に解説しています。
この記事で使用した画像は「スタジオジブリ作品静止画」の画像です。
この記事を書いた人
最新記事
- 2025年12月23日
「美しい物語」ではなかった羽衣伝説-日本各地の天女伝承とその結末- - 2025年12月21日
【ホーム・アローン2】雑学&豆知識集-裏話や制作秘話を紹介- - 2025年12月19日
【ホーム・アローン(1作目)】雑学&豆知識集-裏話や制作秘話を紹介- - 2025年12月18日
「未来のミライ」と「となりのトトロ」に見る共通点 -孤独が生んだ”夢だけど夢じゃなかった”世界- - 2025年12月14日
「未来のミライ」のあらすじ(ネタバレあり)-結末までのストーリーを解説・考察-