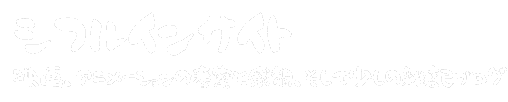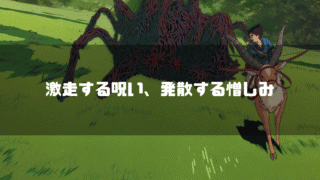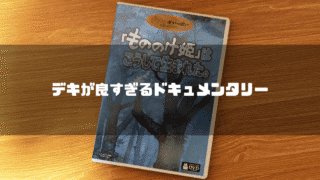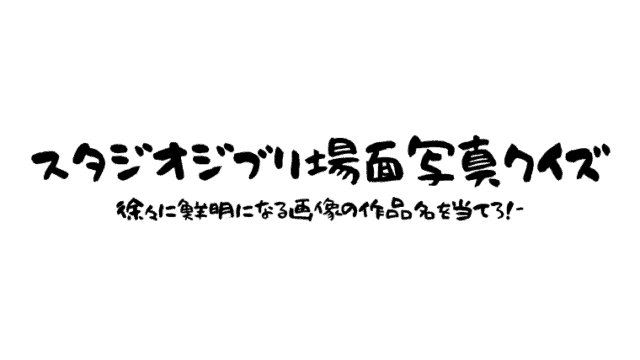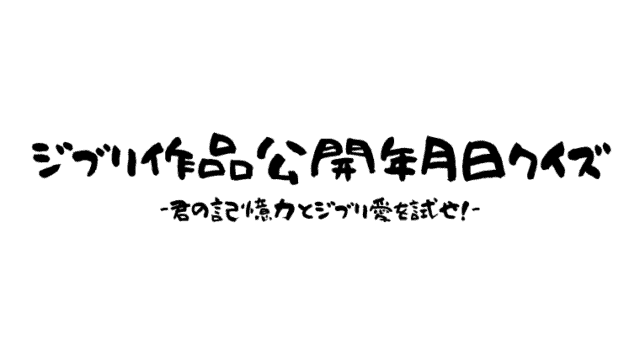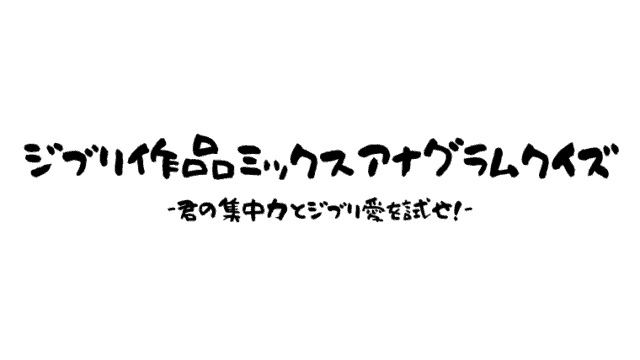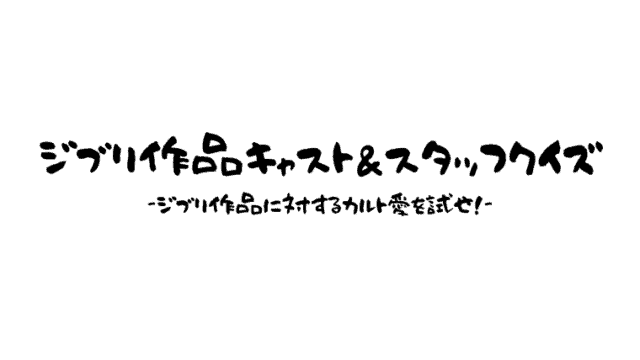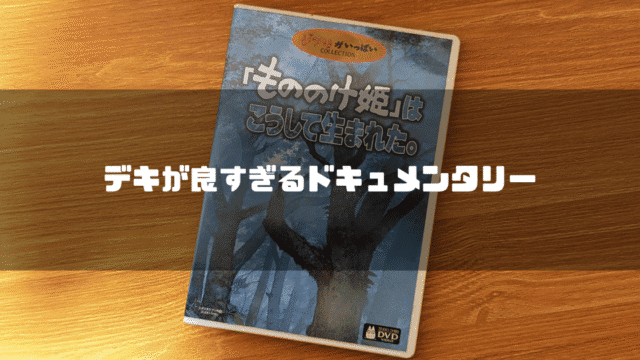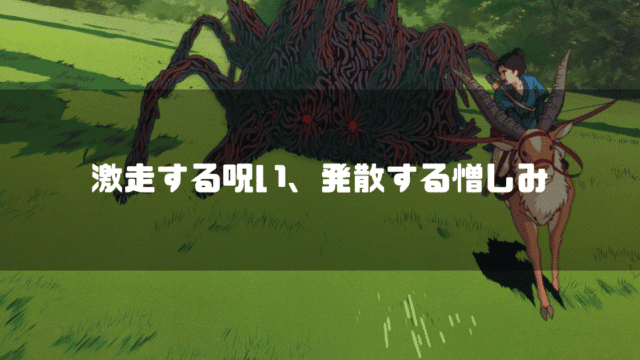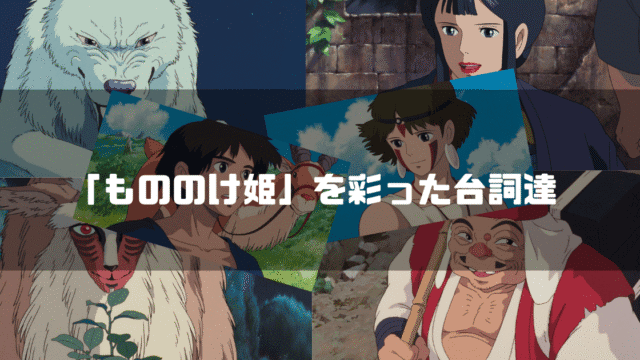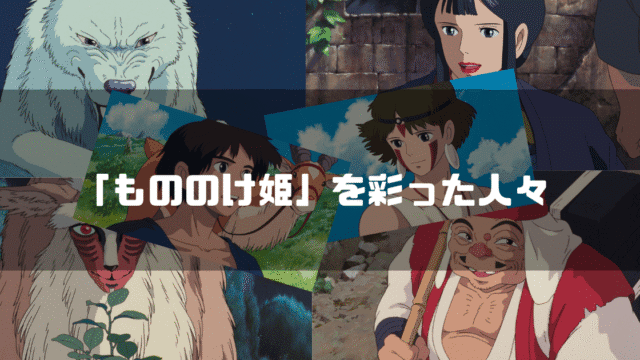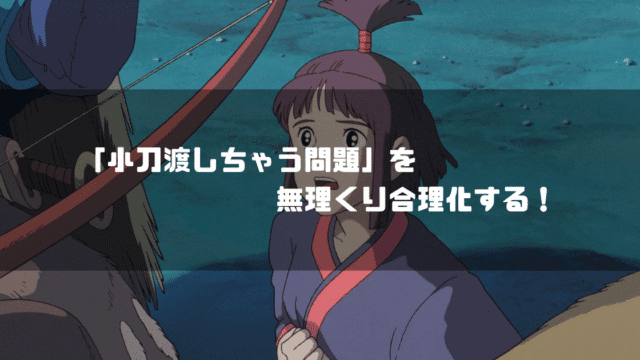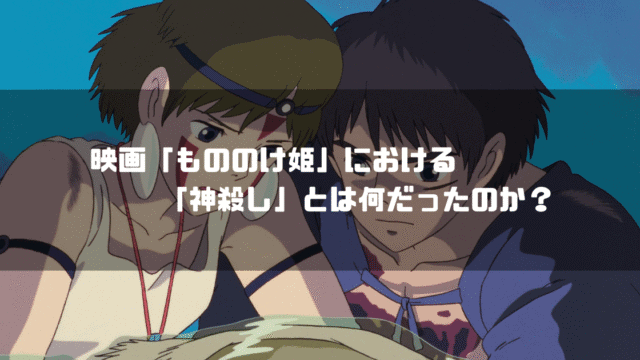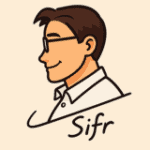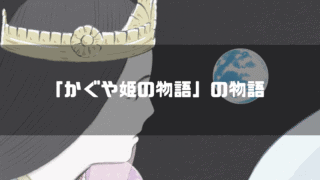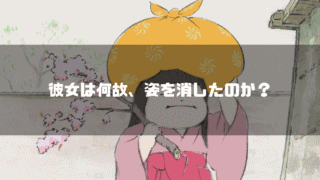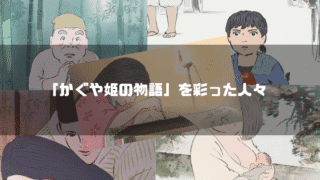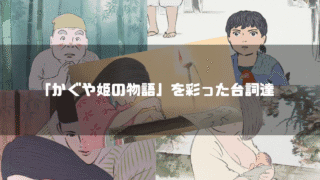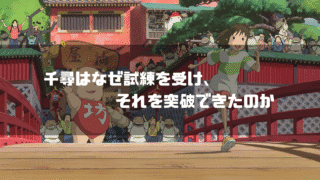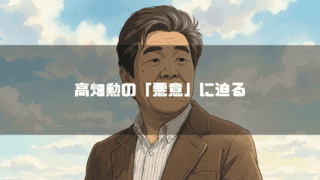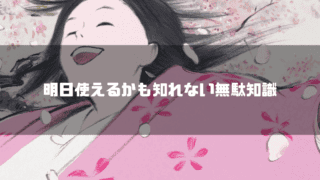【もののけ姫】「シシ神は死なないよ、命そのものだから」とはどういう意味だったのか?

「もののけ姫(スタジオジブリ公式)」は1997年に公開された宮崎駿監督による劇場用アニメーション作品である。
今回は、物語のラスト、アシタカがサンに投げかけた「シシ神は死なないよ。命そのものだから。生と死、二つとも持っているもの」という言葉の意味について考えていこうと思う。
宮崎駿一流の演出によって「なんとなく分かるが、決定的にはわからない、でも・・・それでいい気がする!」と我々は思わされるので、アシタカの言葉について考えることをやめてしまう。
考えることをやめることは別に悪いことではないのだが、今回はそれをやめずに突き進んでいこうと思う。
一つ重要なポイントと思われることは、エボシ御前たちがシシ神に近接した際、何故かシシ神はデイダラボッチになることをやめなかったことである。
皆さんも初めて「もののけ姫」を見た時に思わなかっただろうか、「エボシ達への対応をした後に、ゆっくりとデイダラボッチになればよいのに」と。
個人的にはこの違和感が、ラストのアシタカの台詞を理解するためのヒントになっていると思われる。
この記事では上の「違和感」をフックとする「シシ神の性質変化としての解釈」をまず述べて、その後に、それとは全く別の解釈について述べる。アシタカの言葉の意味を完全に決定する描写や資料は確認できていないので、どちらの解釈も私にとっては平等にあり得ることだし、どちらの意味も同時に込められていると考えることもできる。
まずは「シシ神の性質変化としての解釈」を考えるために、宮崎駿監督の証言を振り返っていこう(なお、作品全体のあらすじや、カヤの小刀、神殺しの意味など、他の考察については「『もののけ姫』あらすじ・考察まとめ」で解説している)。
この記事の内容を、AIが対話形式(ラジオ形式)で分かりやすく解説してくれます。
-
シシ神の「死」と「上級神」への変化
宮崎駿監督の証言を基にすると、シシ神は「下級の神」であり、ラストで姿を消したのは死ではなく、人々が畏怖や信仰を抱く目に見えない「上級神」へ変化したと解釈できる。「生と死」とは、自然がもたらす恵みと脅威の二面性を象徴している。 -
生きる支えを失ったサンへの励まし
アシタカの言葉は、生きる支えであるシシ神の森を失ったサンに向けられたものでもある。「君が守ってきた森は、生と死を司るシシ神の力で必ず復活する」という、絶望するサンを力づけるための希望に満ちたメッセージも込められていると考えることができる。 -
癒えぬ呪いを抱えたアシタカ自身の叫び
呪いの痣が完治しなかったアシタカにとって、シシ神は自身を癒す最後の希望である。そのため、この言葉はサンへの励ましであると同時に、「不条理」を背負いながらも生き抜こうとするアシタカ自身の切なる願いや魂の叫びとも捉えられる。
アシタカの言葉の意味①:シシ神の「神としての性質の変化」としての解釈
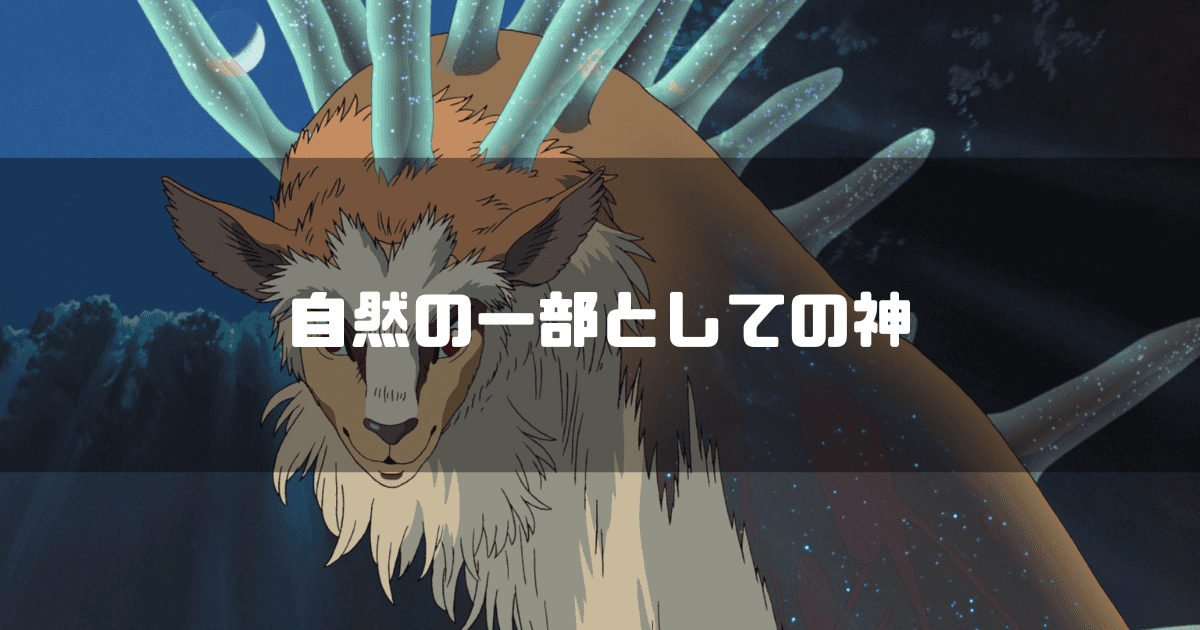
宮崎駿の「シシ神」に関する証言
「折り返し点: 1997~2008(PR)」に収録されている梅原猛(哲学者)との対談の中で「シシ神というのはなんですか。」というド直球の質問に対して以下のように答えている:
「いや、苦し紛れなんです。『夜』なんですけどね。歩き回って森を育てている。昼間は消えて、一つの生き物としてそこにいるんです。鹿の角をはやした、人面と鳥の足と山羊の身体を持ったような、いい加減なものです。・・・実はこのシシ神も、うんと下級の神様として描いたんです。それ以上はもう描けなくて、結局それを最終的に『森の神』ということにしてしまった。もう少し上級神がいるんだろうと思いながら。」
歩くたびにその足元から草が生え、命を吸い取り、デイダラボッチに変身するような「シシ神」は、実のところ「下級の神様」であるという。
この記事は結局のところ、宮崎駿の言う「下級の神様」という言葉の意味を探ることが目的になると思われるのだが、この発言を理解するために、もう一つの発言を引用する。
「ジブリの教科書10 もののけ姫(PR)」に収録されている「海外の記者が宮崎駿監督に問う、『もののけ姫』への四十四の質問」で、「アニミズムについて伺いたいんですが、宗教に対してはどのようにお考えですか?」という質問に以下のように答えている:
「今でも多くの日本人の中に宗教心として強く残っている感情があります。それは自分たちの国の一番奥に、人が足を踏み入れてはいけない非常に清浄なところがあって、そこには豊かな水が流れ出て、深い森を守っているのだと信じている心です。そういう一種の清浄感があるところに人間は戻っていくのが一番素晴らしいんだという宗教感覚を、僕は激しく持っています。それには聖書もなければ、聖人もいないんです。ですから世界の宗教レベルでは、宗教として認められないけれども、日本人にとっては、非常に確かな宗教心なんです。」
以上の発言をヒントに、アシタカの台詞の意味を考えていこうと思う。
シシ神は、デイダラボッチになることを止められない存在-自然の一部としての神-
アシタカの言葉の意味を理解するために、まずは、多くの人が感じたであろうシシ神の違和感について考えてみよう。
自らの首を狙う連中に囲まれていたのに、何故シシ神はデイダラボッチになることをやめなかったのか?実際問題として、それをやめなかったことが原因でエボシに首を撃ち抜かれた挙げ句に奪われてしまったわけである。
この違和感を「下級の神様」という言葉をヒントにして考え直してみると、「シシ神はデイダラボッチにならないということができない」と見るのが自然ではないだろうか。
シシ神にとっての「デイダラボッチ化」は、我々にとっての睡眠のように、抗うことのできない自然現象(生理現象)であり、自分の力でどうこうできることではないということである。
そのように考えてみると、シシ神と我々人間は割と地続きな存在と思えてくる。もちろんシシ神はどう考えても超越的な力を持っており、我々と異なる存在ではあるのだが、「超自然的存在(あるいは自然を統べる存在)」というよりは「我々と同じ自然の一部」と見たほうがよい存在と思える。
宮崎駿が言うところの「下級の神様」とはこういう意味だったと思われる。
形のない、清浄な「何か」としての「上級神」-宮崎駿が具現化できなかったもの-
シシ神が「下級の神様」であるということが上で述べたことだったとして、宮崎駿が想定していた「上級神」とはどういう存在だったのだろうか。
引用した対談での発言の中で「苦し紛れなんです。『夜』なんですけどね。」という表現があるが、それはつまり「本当は『上級神』を描きたかったがそれができなかったので苦し紛れにシシ神となった」ということだと思う。
そしてそうなると、「苦し紛れ」にはなってしまったが、その有り様の中に「上級神」のヒントはあるだろう。
注目すべきは「『夜』なんですけどね。」という発言と思われる。「『もののけ姫』はこうして生まれた。(PR)」というドキュメンタリーの中でもデイダラボッチについて「夜の闇そのもの」を象徴するものであると言及されている。
思えば、暗闇の中に「何か」を感じたり、何故か夜の闇に恐怖を覚えた経験があるが、多くの人が経験したことだと思う。
それはもちろん、我々の中に残った「外敵から自分を守る野生の本能」と見ることが自然なのだろうけれど、闇夜に感じる「怖れ」がある種の信仰を生むことも事実ではないだろうか。
そしてそれは結局、「地震」、「台風」、「洪水」といった脅威から生まれる「自然」に対する「畏怖」と地続きなものであり、素朴な「自然信仰」を生み出すものだと思う。そしてそういった「畏怖」の対象としての「自然」は、これと言った明確な姿を持たないということが重要だろう。
現代的に我々は、「地震」、「台風」、「洪水」という現象の発生原理についてはある程度理解できてはいるのだが、「自然信仰」というのはそういった具体的な現象に対する「畏怖」というよりは、その背後に隠れ、現象を引き起こしている「何か」に対する信仰なのではないだろうか。
このように考えてみると、宮崎駿はそういった目に見えない「何か」を描こうとしたのではないかと思われる。
ただし、その「何か」をわかりやすく人間の形にはしたくなかった。それは上で引用したインタビューでの「それには聖書もなければ、聖人もいないんです。」という発言にも現れていると思う。人間の形にしてしまっては、それに反してしまう。
しかも、宮崎駿が排除したかったのは別に「西洋的神」あるいは「キリスト教的神」のイメージだけではないことも分かる。我が国の神話においても神は人間の形をしているのだから、宮崎駿はそれをも否定したかったということになるだろう。
そして苦心の末に生み出したのが「シシ神」であったのだが、本人としては不満であったということになる(「苦し紛れ」だったのだから)。ただし、あの「シシ神」のデザインは私のような凡人としては十分に素晴らしいもので、「苦し紛れ」などと表現するようなものではない。
結局のところ、宮崎駿が想定している「上級神」とは「自分たちの国の一番奥に、人が足を踏み入れてはいけない非常に清浄なところがあって、そこには豊かな水が流れ出て、深い森を守っているのだと信じている心」が感じている「何か」であり、それを表現しきれなかったがためにシシ神を「下級の神様」と評したのだろう。
では、そのシシ神が「もののけ姫」のラストのような状態で姿を消すとはどのような意味を持っていたと考えられるだろうか?
アシタカの言葉の意味-姿を消したシシ神はむしろ「上級神」となった-
ここからはようやくアシタカの言葉の意味を考えようと思うのだが、「もののけ姫」本編では明確に描かれていない事実を仮定する必要があるので、それを明確にしようと思う。その仮定とは、
物語の終結後、シシ神の姿を見たものはいない。
こんなもの「仮定」ではなくて、そうであるに決まっているのだが、強調する意味も込めて「仮定」としてみた。
さて、シシ神が姿を消したあの森はその後どうなったのだろうか?映画本編では僅かな復活を遂げただけだったが、長い時間を掛けて再び鬱蒼とした森にはなったと思われる。
しかしそのような森で「シシ神伝説」が残ったと見るのが自然ではないだろうか?
そもそもが「シシ神の森」と呼ばれる場所であり、多くの人間が経験した壮絶な事件が発生したのだから、その事実が語り継がれたと考えるのはおかしなことではないだろう。
しかし、人々は決してシシ神の姿を見ることができない。映画本編では確かに存在し、石火矢でダメージを与えることすら出来た存在を、人々は決して見ることがないのである。でも「シシ神伝説」は残る。もしかしたら「シシ神の森」という名前だけは残ったかもしれない。
そして、森の中で「何か」の気配を感じればそれをシシ神の気配と感じるかもしれない。森の中、あるいは森の近くで何か不可解な事件が起こればそれはシシ神の祟りと言われるかもしれない。「台風」、「地震」、「洪水」が起こればそれはシシ神の引き起こしたこととされるかもしれない。さらに、そんなことが発生しない平穏な日々に対しても「シシ神様の思し召し」と思うかもしれない。
でも、人々はシシ神の姿を決して見ることはない。
これはまさに、様々な災害の背後に隠れ、その現象を引き起こしている「なにか」そのものとなっていると考えることができるし「人が足を踏み入れてはいけない非常に清浄なところ」の象徴となっていると言えるのではないだろうか?
つまり、アシタカの言葉の意味は以下のように解釈することができるのではないだろうか:
シシ神はその姿を消したことによって、人々が素朴に感じる「怖れ」と「清浄」の対象となった。それはむしろより高位の存在となったということなのだから、シシ神は死んではいない。そして、「怖れ」と「清浄」という性質は、人々を死に追いやるかもしれない「脅威」とその生活を育む「恵み」という「生と死」の二面性を象徴しているものである。
続いては、これとは全く異なった解釈について考えていこうと思う。
アシタカの言葉の意味②:サンへの思いと、自らの希望を込めた言葉としての解釈
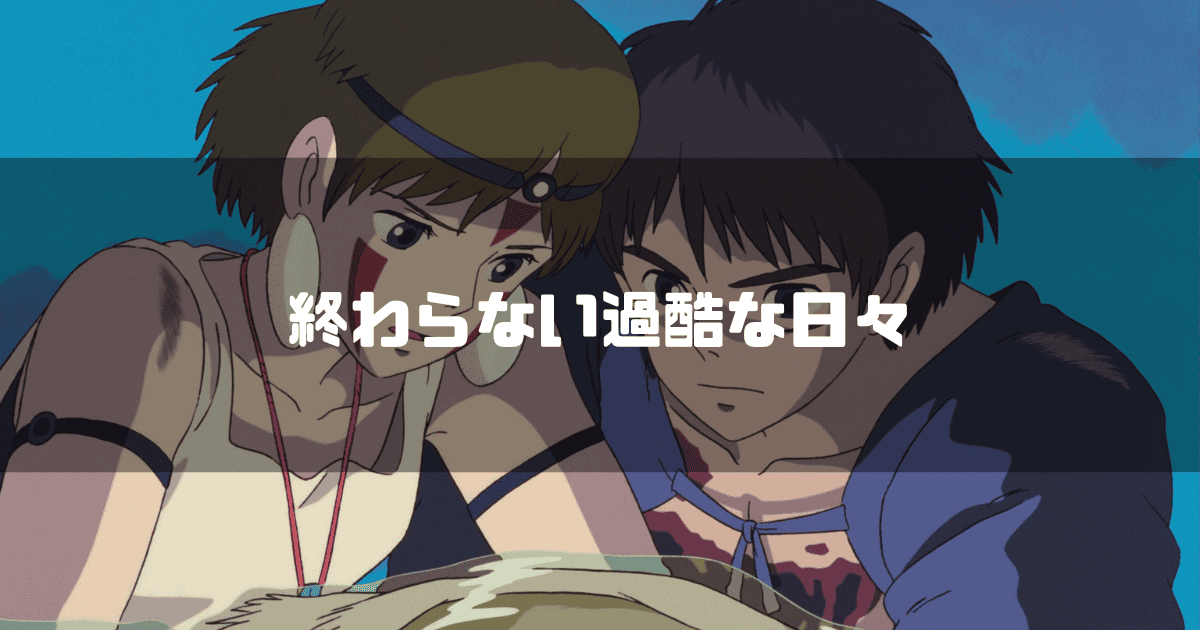
サンの生きる縁(よすが)としての「シシ神の森」
これまでの考察で、完全に抜け落ちている視点がある。それは、「アシタカはあの言葉を誰に投げかけたか」という視点である。
もちろんそれはサンなのだが、それを認識したうえで重要なことは、首を失ったシシ神(デイダラボッチ)の影響で森が失われてしまっているという事実である。
それはつまり、サンがその生きる縁としていたものを失ったことを意味している。
赤ん坊の頃に親に捨てられたサンは、どう見たって人間にしか見えない姿をしていながら自らを「山犬」と称している。「人間でありながら山犬として生きる」という矛盾に満ちた状況を根本的に支えていたものが「シシ神の森を守る」という強い意志であった。
それを失った、少なくとも失ったと感じているサンに、あのタイミングでアシタカが掛けてあげられる言葉があるとすれば「シシ神は死なない」という言葉しかなかったのではないだろうか。つまり、この文脈におけるアシタカの言葉の意味は、
サン、シシ神が死ぬわけないじゃないか!君が命をかけて守り続けた「シシ神の森」は再び「シシ神の森」として復活するよ。シシ神は生と死2つの性質を持っているんだからね。モロの君も言っていただろ、シシ神は命を与えもするが奪いもすると。
さて、基本的にはここで終わってよいのだが、もう少しだけ考えを進めてみようと思う。
シシ神の存在はアシタカにとっても希望であった
最後にアシタカ本人に目を向けてみようと思う。
「もののけ姫」は、不条理な呪いを受けたアシタカの当てのない西への旅として始まり、ジコ坊の導きによって「シシ神」という希望を見出したものの、その呪いを癒やしてはくれないという絶望に直面するが、サンという新たな生きる意味を見出し、最終的にはタタラ場という新天地を見出すという物語となっている。
そして結局のところ、アシタカの呪い(痣)は完全には消えることがなかった(大分薄くはなったけど)。
ラストのアシタカは、何やらつきものが落ちたような健やかさを取り戻しているように見えるけれども、痣が消えていないという事実を抱え続けることになる。
その痣、あるいは呪いも自分の一部であると受け入れていると見ることもできるのだけれど、心の何処かに何かが引っかかり続けるということだって十分ありうるし、個人的にはそのような可能性の方が高いと思う。
その一方で、アシタカの呪いを完全に取り除ける可能性を持った超越的な存在は結局のところシシ神しかいない。
このような文脈の中でアシタカの言葉の意味を考えると以下のようになるのではないだろうか:
シシ神は死なない、いや、死んでいいはずがない。俺の呪いは完全には癒えていないじゃないか!シシ神は必ず俺の呪いを癒やしてくれるはずだ!
もはや魂の叫びというべきものであり、なんとも悲痛な思いである。物語のラストにこんなことを思っていたと考えるのは少々悲しいのだが、「不条理」や「解決不能な課題」が「もののけ姫」のテーマの一つであるということを考えると、実のところそこまでおかしなことでもない。「はい!全部解決しました!」という物語ではないのである。
さて、これまでアシタカの言葉について3つの可能性を考えてきたが、これらはそれぞれ特段矛盾するものではない。むしろ、彼の言葉にはこれらのことが複合的に含まれていたと考えるのが自然と私は思う。
皆さんはアシタカの「シシ神は死なないよ。命そのものだから。生と死、二つとも持っているもの」という言葉の意味をどのように考えるだろうか?
この記事ではアシタカの最後の言葉の意味について考察したが、本作の詳細なあらすじや、もう一つの大きな謎である「アシタカがカヤの小刀をサンにあげた理由」など、作品全体の解説については「『もののけ姫』あらすじ・考察まとめ」で網羅している。
この記事で使用した画像は「スタジオジブリ作品静止画」の画像です。
この記事を書いた人
最新記事