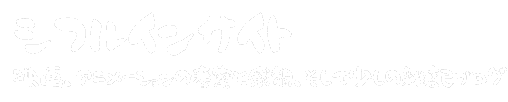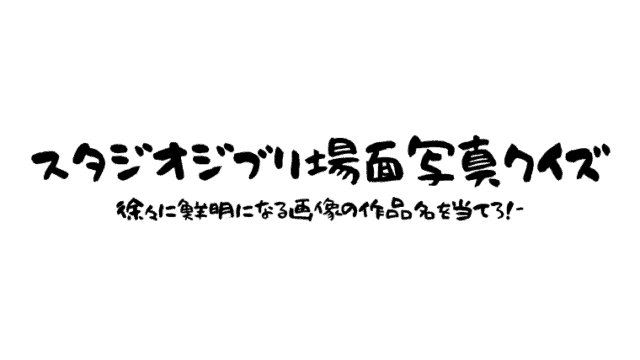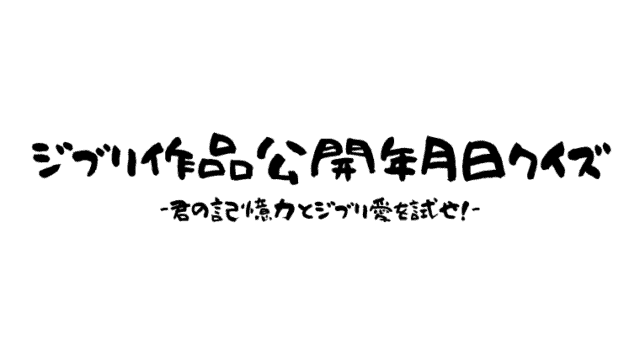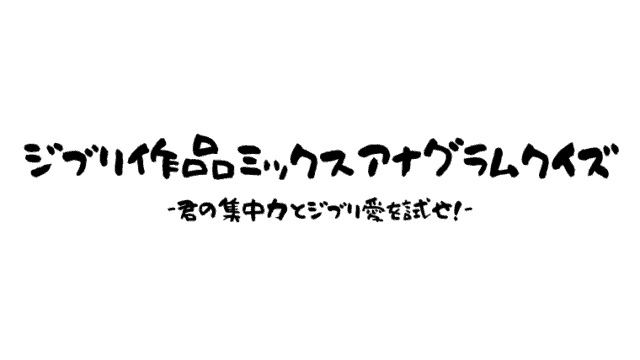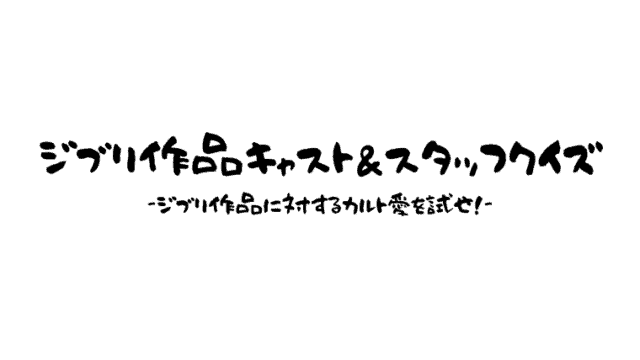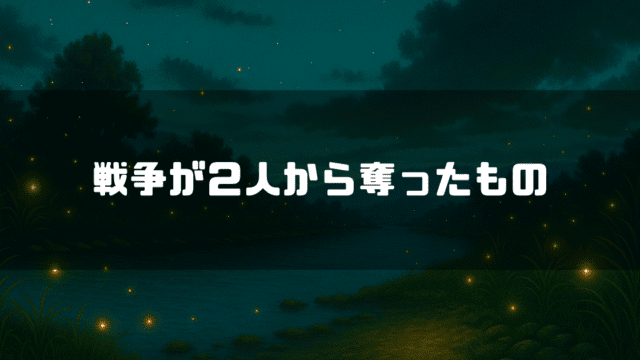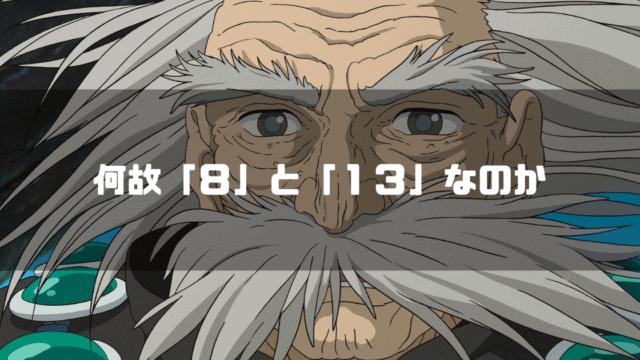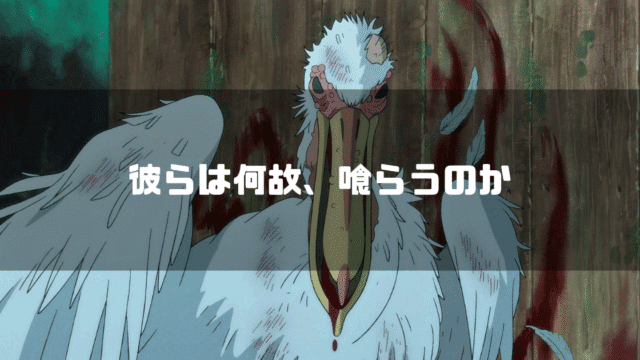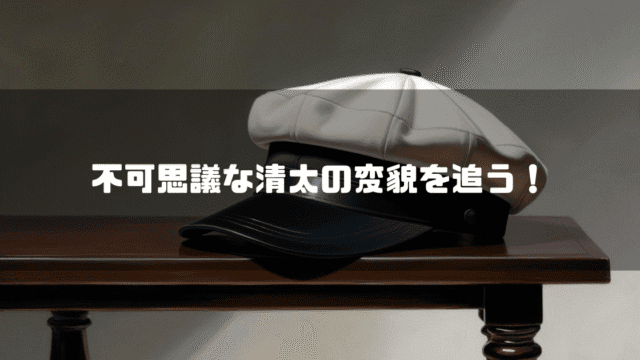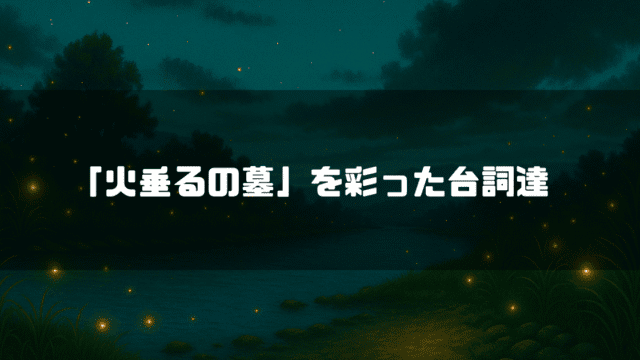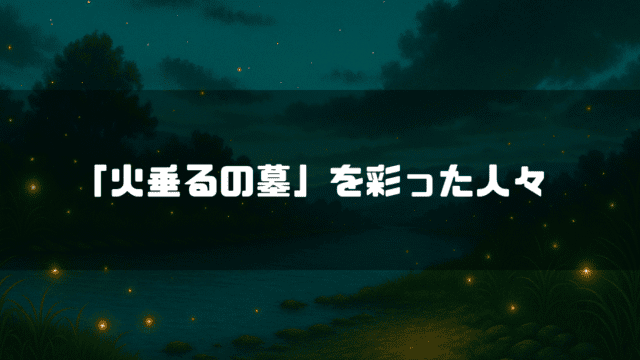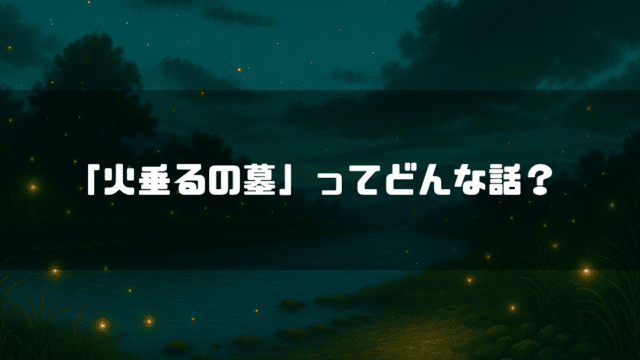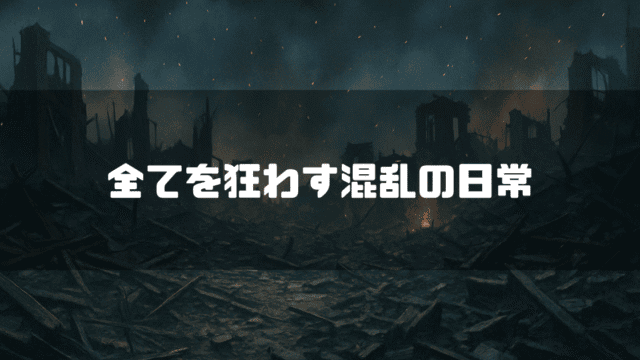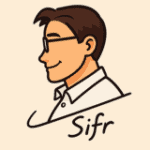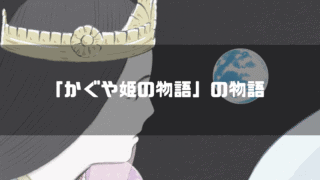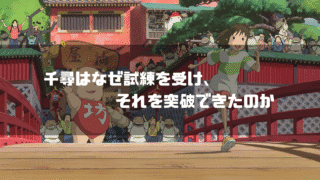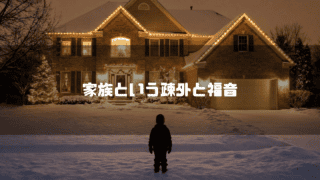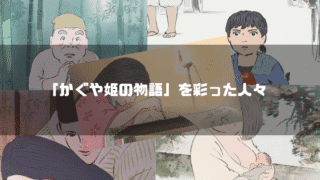【火垂るの墓】雑学&豆知識集-裏話や制作秘話を紹介-
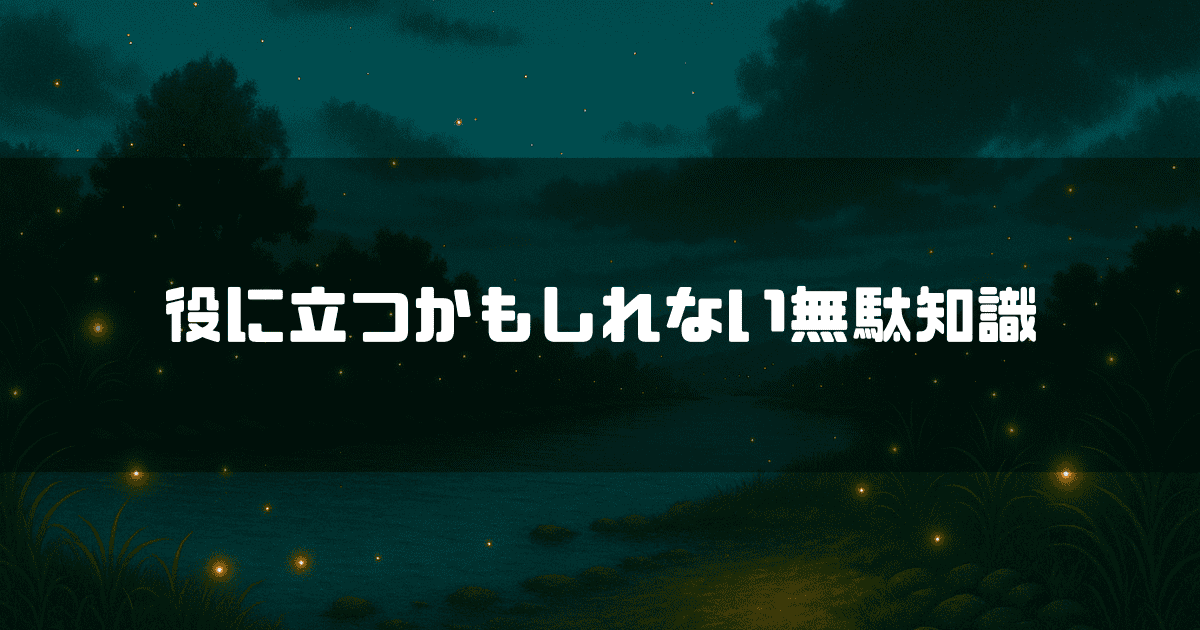
「火垂るの墓(スタジオジブリ公式)」は1988年に公開された高畑勲監督による劇場用アニメーション作品である。
今回は「火垂るの墓」に関する雑学、豆知識をまとめていこうと思う。必ずしも本編の理解を深めるために必要なものではないが、なかなか興味深いものも含まれていると思う。
この記事の内容を、AIが対話形式(ラジオ形式)で分かりやすく解説してくれます。
「火垂るの墓」の雑学&豆知識集

「火垂るの墓」は「となりのトトロ」と同時上映だった。
映画「火垂るの墓」は1988年に公開されているが、「となりのトトロ」と同時上映となっていた。
あまりにも雰囲気の異なるこれらの映画が同時上映ということで、現代的な視点から見ると「どういう順番で上映されたのか?」ということが気になるところかもしれない。
しかし、実のところ「『火垂るの墓』を先に見た人もいれば、『となりのトトロ』を先に見た人もいた。」が正解となる。これは映画館によって順番が異なっていたということではなく、「火垂るの墓」が公開された頃の映画の上映方法のために発生したことである。
現代の映画館(シネコン)は「全席指定かつ入れ替え制」を取っている。しかし、「火垂るの墓」が公開された当時は「指定席」でもなく「入れ替え制」でもなかった。チケットさえ持っていれば、いつ入ってもいいし、どこに座ってもいいし、いつまでいても構わなかった。そして同じものが延々と上映されていた。私自身も幼少期にギリギリこのような「非シネコン的映画体験」をしているが、小学校高学年になることにはシネコンの波が押し寄せて、現代と同じように映画を見ていた。
そして、「火垂るの墓」の公開当時に見た人は、そのタイミングによって「となりのトトロ」から見たり「火垂るの墓」から見るという状況になった。当然ながら、どちらを先に見るかでその映画体験は全く異なることになるわけだが、「火垂るの墓」のBlu-ray(PR)に収録されている高畑勲監督のインタビューによると、「となりのトトロ」から見てしまった人の中には「火垂るの墓」を最後まで見られなかった人もいたようである。
公開当時の時代性が反映された現象ではあるが、実のところ公開当時にはもっと重要なことが発生していた。
- 「火垂るの墓 Blu-ray(PR), 特典映像」
公開当時彩色されていないシーンがあった。
「火垂るの墓」と同時公開であった「となりのトトロ」の制作は順調に進んだのだが、「火垂るの墓」の制作は遅れに遅れた。
もともと高畑勲という人物は、映画のクオリティに徹底的に拘る人間であり、東映動画時代の「太陽の王子 ホルスの大冒険」に始まり、スタジオジブリ作品の「おもいでぽろぽろ」、「平成狸合戦ぽんぽこ」、「ホーホケキョとなりの山田くん」、「かぐや姫の物語」の制作はすべて遅れに遅れている。
公式に「公開日延期」となったのは「かぐや姫の物語」だけだと思われるが、例えば「平成狸合戦ぽんぽこ」については、公開日に間に合わせるために最終局面の絵コンテが大幅にカットすることによって10分削減されている。
そして「火垂るの墓」でも同様の困難が発生しており、鈴木敏夫(当時「アニメージュ」編集長)をはじめ、プロデューサーの原徹、新潮社(制作)の佐藤亮一らは、高畑勲に対してなんとか制作を早めるように要請したが「公開を延期してください」の一点張りで譲らなかった。
そんな中、高畑勲が最後に出してきた提案が「2つのシーンの色を塗らないままで公開する」ということだった。
さらに、鈴木敏夫の策略により「未完成である」という事実が伏せられて公開された。ところが、彩色されないままに公開されたのが、清太がトマトを盗むシーンであったために、観客は「演出」と捉えたようで、未完成であるという事実は概ね気づかれなかった。
本来的には未完成品を映画館で見させられるというのは宜しくないことなのだが、現代から過去を振り返るという態度で見れば「未彩色の『火垂るの墓』を見られて羨ましい」とも思う。実際にあのシーンが未彩色だと、どのように見えるのだろう?実に気になる。
- 「ジブリの教科書4 火垂るの墓(PR)」
- 「ジブリの教科書8 平成狸合戦ぽんぽこ(PR)」
- 「ジブリの教科書19 かぐや姫の物語(PR)」
近藤喜文と保田道世の取り合い
「火垂るの墓」は「となりのトトロ」と同時上映だったわけだが、それはつまり、スタジオジブリが通常の二倍の戦力を投入しなければならないことになる。
そして、2人の監督が同じ人物を使いたいと考えた場合にその問題はより深刻となってしまう。
「火垂るの墓」と「となりのトトロ」の制作においては、少なくとも2人の人物が高畑勲と宮崎駿との間で取り合いになった。
アニメーターの近藤喜文と、色彩設計の保田道世がその2人である。
当時スタジオジブリに所属していなかった近藤喜文を、宮崎駿は何度も足を運んで説得を試みた。一方、高畑勲は自分では動かなかったが「近藤喜文がやってくれなかったら火垂るの墓はどうなるのか」という鈴木敏夫の質問に対して「できないですね」と答えたそうな。
どちらの監督にとっても余人を持って代えがたい存在だったのだが・・・最終的に近藤喜文は「火垂るの墓」に参加している。
これは近藤喜文本人の選択によるものではなく、鈴木敏夫の采配であった。その理由は簡単に述べると「そもそも優れたアニメーターである宮崎駿は自分で描けば良い、高畑勲はそういうわけにはいかない」ということであった。
しかしそうなると宮崎駿は不満なわけで、「腱鞘炎だと偽って明日から入院する!」と完全な嫌がらせのようなことを言い出したのだが、その翌日にも面白い逸話が残っており、「ジブリの教科書3 となりのトトロ(PR)」で鈴木敏夫が以下のように語っている:
次の日の朝、八時ぐらいに宮さんから電話がかかってきて、いきなり「コンちゃんのこと、殴った」というのでビックリしました。よくよく聞いてみたらそれは夢だったんですが、「気が済んだからやる」ということになり、それが『トトロ』のスタートでした。
これほどまでに、近藤喜文という人物の能力を2人の監督が欲しがったということである。
さらに、色彩設計の保田道世さんも取り合いになる。
保田道世さんは東映動画時代から高畑、宮崎と仕事をしているまさに盟友と呼べる人物であった。最終的にはプロデューサーの原徹、鈴木敏夫、高畑勲、宮崎駿、保田道世の五人が集まって会議をすることで、「主に『火垂るの墓』を担当し、『トトロ』については基本的な色彩設計をした上でもう一人色指定のスタッフを立てる」ということになった。
つまりは、宮崎駿はどうしても欲しかったスタッフを2人とも高畑勲に奪われたということになる。
結果的に「火垂るの墓」は傑作になったからこれで良かったような気もするのだが、こうなってくると、近藤喜文と保田道世の両方を獲得した「フルスペックの『となりのトトロ』」を見てみたかった気もするね。
「スタッフを高畑勲に奪われた」という文脈では、庵野秀明のこともよく語られている。庵野秀明は「火垂るの墓」で観艦式の巡洋艦を担当している事実があるのだが、「『トトロ』のOPアニメーションと『火垂るの墓』の巡洋艦のどちらをやりたいか?」と問われて、宮崎駿とはすでに仕事をした(ナウシカの巨神兵)ので、高畑勲と仕事をすることを選んだと言われている。しかしながら、現状ではこの逸話を裏付ける(一次)資料を見つけることが出来なかった。
特段この逸話を否定する声明も発表されていないので、おそらくは事実なのだとは思うのだが、一応注意は必要であると思う。
ただ、この逸話を前提にすると、宮崎駿は高畑勲に3人ものスタッフを奪われたことになる。益々「フルスペックの『となりのトトロ』」への思いが強くなる。
- 「ジブリの教科書3 となりのトトロ(PR)」
- 「ジブリの教科書4 火垂るの墓(PR)」
高畑勲監督も空襲経験者
高畑勲監督は、1935年に三重で生まれているが、父親が岡山一中の校長になったことで、1943年に岡山へ転居している。
そしてその翌年、9歳であった高畑勲は「岡山大空襲」に遭ってしまった。
「岡山大空襲」は1945年6月29日の午前2時43分に開始されている。つまり、深夜の空襲であった(B29による焼夷弾の投下)。
すぐ上の姉と2人で焼夷弾で燃え盛る夜の街を逃げ惑い、街の中央を流れていた川(旭川)にたどり着いて、黒い雨に打たれながら夜が開けるまで震えて過ごしていたという。
つまり、「火垂るの墓」で描かれた焼夷弾による空襲の描写はは監督の実体験が反映されているということになる。
ただし、「火垂るの墓」で描かれている「神戸大空襲」は、原作者の野坂昭如が経験した1945年6月5日昼に行われたものが元になっており、いずれもB29からの焼夷弾の投下であったが、その時間が異なるため、昼の焼夷弾がどのように見えるかなど、映画のリアリティを上げるために焼夷弾について様々に調べたようである。
ただその中で、焼夷弾の構造に関連して少々問題が発生した。
というのは、空襲の経験者である高畑勲監督を始め、焼夷弾による空襲を経験した人は、その有り様を「火の雨」と表現しており、まさに火のついた焼夷弾が空から降ってくる様を見ているし、写真にすら残っている。
高畑監督は、自衛隊の専門家に焼夷弾の構造について聞くことができる機会を得た(実際に話しを聞いたのは演出助手)。しかし、自衛隊の専門家によると「その構造上、焼夷弾が空中発火することはありえない」ということであり、自らの経験やその他の証言、そして写真と矛盾することを言われてしまう。
高畑勲は、映画に描写されるどんなものでも細かく徹底的に調べ上げる人物であるので、その描写は極めて信頼できるものだと思うのだが、「火垂るの墓」の焼夷弾については少々注意が必要であることになる。このことについて個人的に調べて考えたことを以下の記事にまとめている:
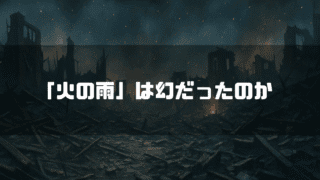
記事の結論としては「空襲経験者の証言と自衛隊の説明を矛盾なく説明することができる」となるのだが、ただの素人の結論に過ぎないので、注意深くあらねばならないことに変わりはない。
原作者の野坂昭如がロケハンを案内してくれていた
映画「火垂るの墓」の制作にあたって、高畑監督をはじめとするスタッフの一部が、原作の舞台になった場所をロケハンしているのだが、その案内をしてくれたのが原作者の野坂昭如本人であった。
作品の舞台となった、神戸、芦屋、御影、満地谷などを丁寧に案内したことが「ジブリの教科書4 火垂るの墓(PR)」において、美術監督の山本二三が語っている。
そんな野坂昭如だが、アニメーションとしての「火垂るの墓」には大変に満足していたようで「アニメ恐るべし」というエッセイを「小説新潮」に寄稿している(エッセイの内容は「ジブリの教科書4 火垂るの墓」で確認することができる)。
- 「ジブリの教科書4 火垂るの墓(PR)」
輪郭線は茶色
「火垂るの墓」そして「となりのトトロ」の特徴として、実は「人物の輪郭線が茶色である」という事実がある。
輪郭線は通常黒いのだが、それでは「火垂るの墓」や「となりのトトロ」の世界観にそぐわないということで、新たな試みが行われた。
しかし、新たな試みであったが故に、様々な技術的困難があったようだが、そのかいもあって2つの傑作が生まれた。
しかし、こういうことって「言われなきゃわからないこと」であって、この事実を情報として知るまでは全く気がついていなかった。制作サイドの多大な苦労と工夫の殆どは我々消費者に届いていないという悲しい現実の端的な例になってしまっているかもしれない。
一方で、「輪郭線が茶色」という事実を我々にそれほどまでに意識してほしいのかと考えれば、そういうでもない気がする。むしろ、それに気が付かなかったことこそが、制作サイドの苦労の結果であり、工夫の成果と見ることもできるだろう。まあ、言い訳に過ぎないのだけれど。
- 「ジブリの教科書4 火垂るの墓(PR)」
この記事を書いた人
最新記事
- 2025年12月23日
「美しい物語」ではなかった羽衣伝説-日本各地の天女伝承とその結末- - 2025年12月21日
【ホーム・アローン2】雑学&豆知識集-裏話や制作秘話を紹介- - 2025年12月19日
【ホーム・アローン(1作目)】雑学&豆知識集-裏話や制作秘話を紹介- - 2025年12月18日
「未来のミライ」と「となりのトトロ」に見る共通点 -孤独が生んだ”夢だけど夢じゃなかった”世界- - 2025年12月14日
「未来のミライ」のあらすじ(ネタバレあり)-結末までのストーリーを解説・考察-