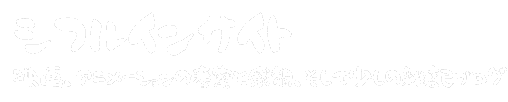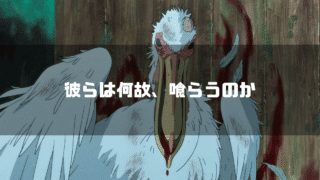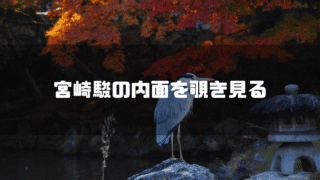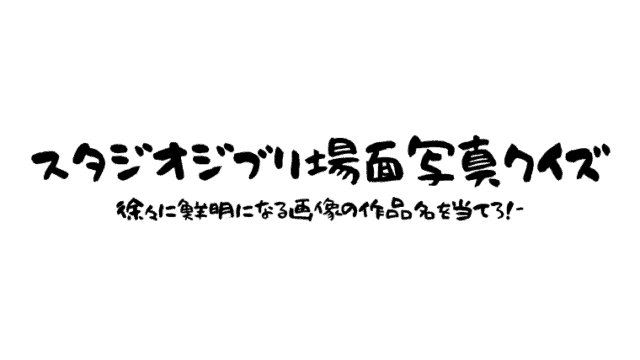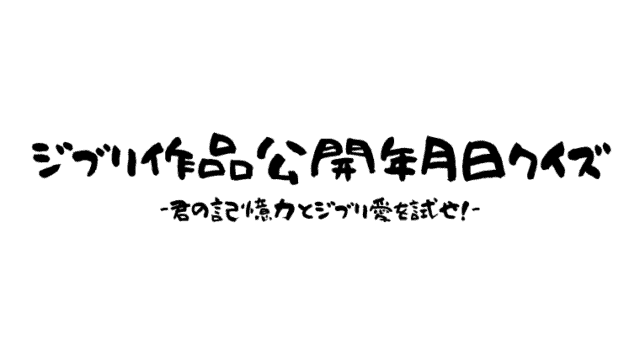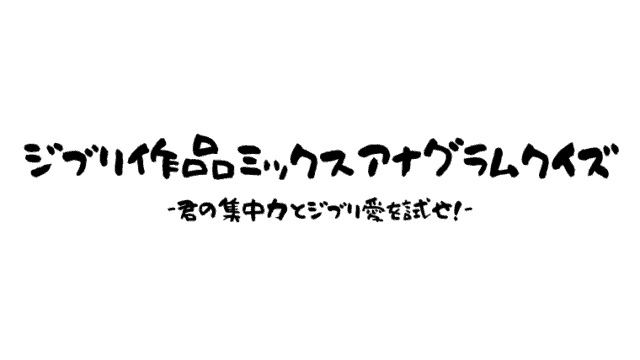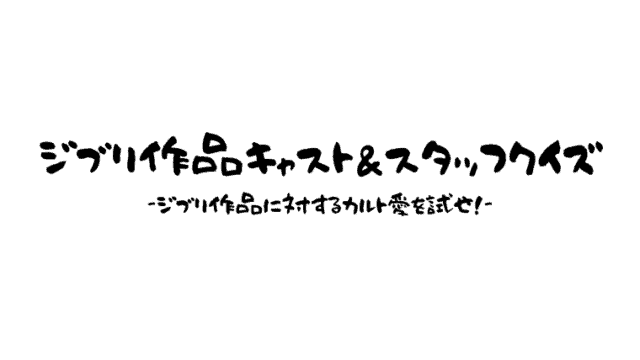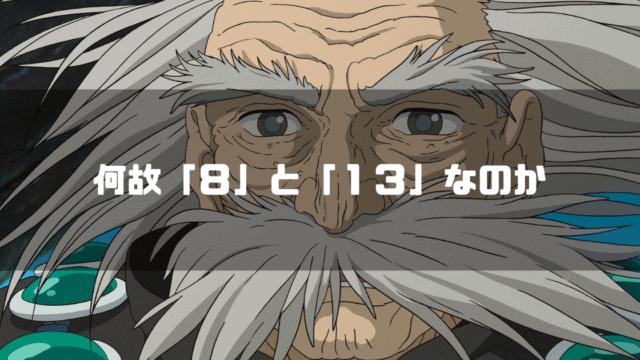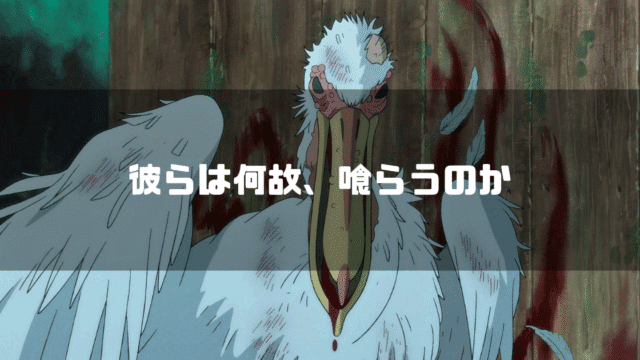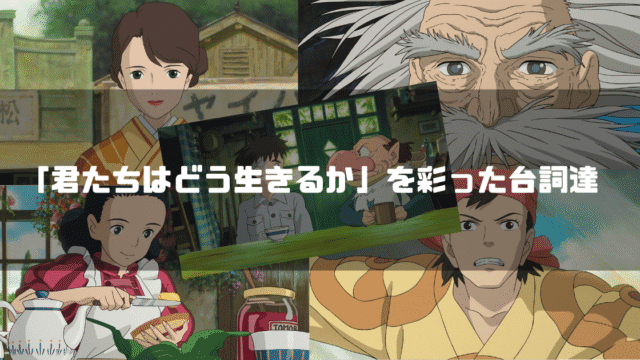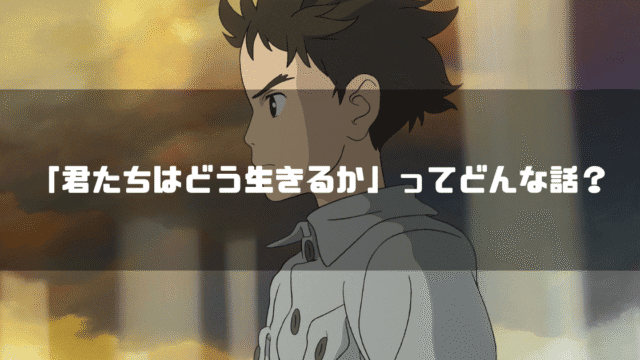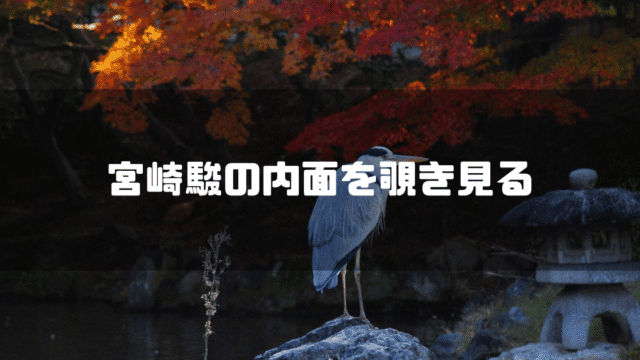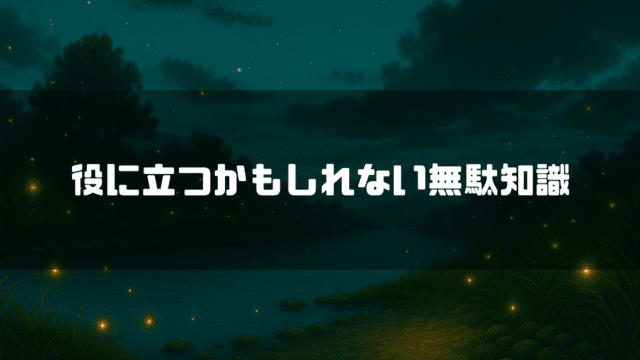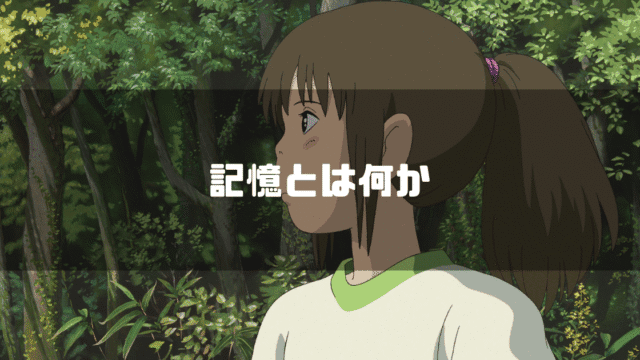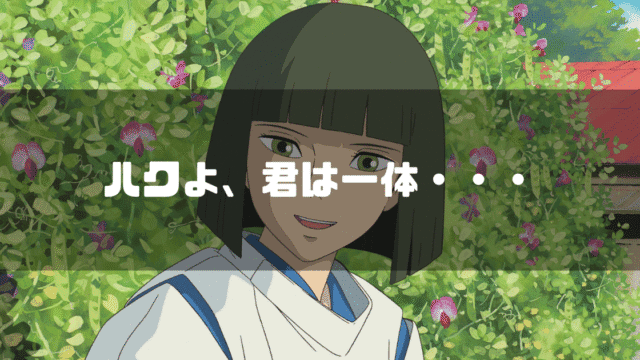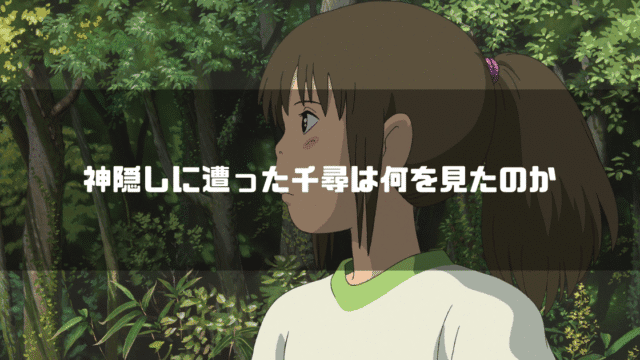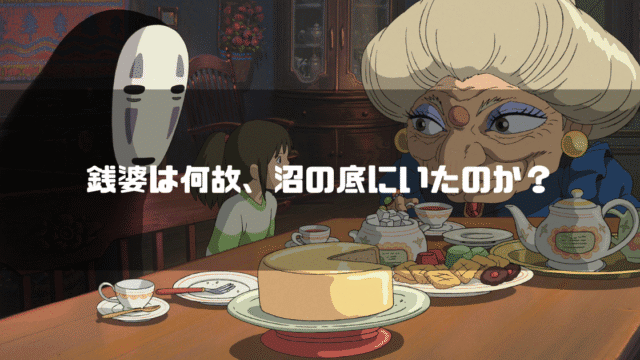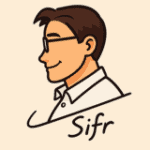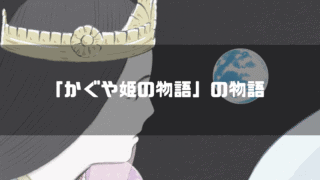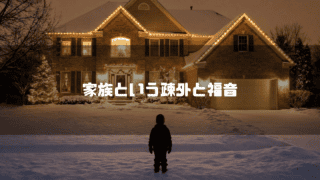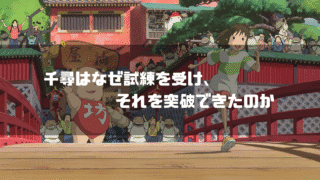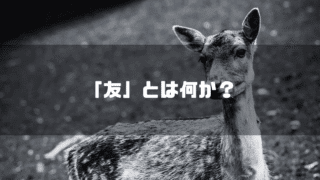【君たちはどう生きるか】青サギ(サギ男)のモデルとなった鈴木敏夫のおもしろ「サギ」列伝-スタジオジブリを支えた辣腕の歴史-
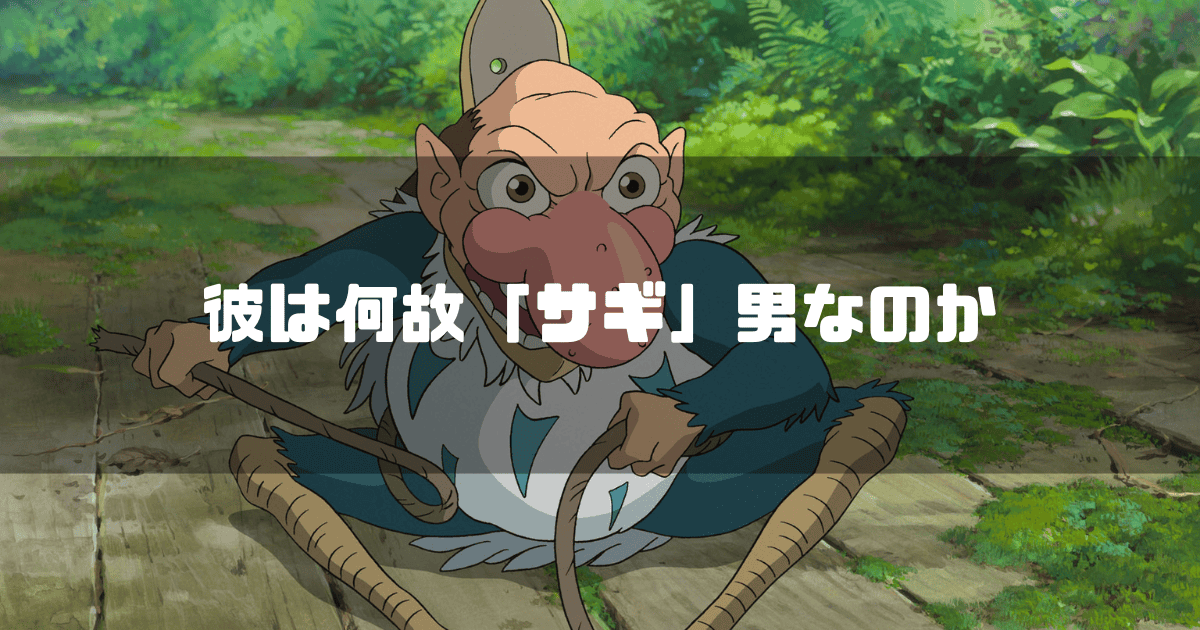
「君たちはどう生きるか(スタジオジブリ公式)」は2023年に公開された宮崎駿監督による劇場用アニメーション作品である。
「君たちはどう生きるか」は宮崎駿の自伝的な作品であり、登場人物にはモデルが存在していることが多い(キリコは保田道世さん、大叔父は高畑勲監督など)。今回はその中でも「青サギ」あるいは「サギ男」のモデルとなった鈴木敏夫プロデューサーの辣腕の歴史を振り返ることによって、「なるほど、鈴木敏夫は『サギ』男だな。」と納得してもらおうと思う。
「青サギ(サギ男)」のモデルが鈴木敏夫であることは、制作ドキュメンタリーの「宮崎駿と青サギと・・・(PR)」など様々なメディアで言及されているが、「SWITCH Vol.41 No.9 特集 ジブリをめぐる冒険(PR)」でのインタビューでも鈴木敏夫は以下のように語っていた:
サギ男は誰がどう見たって僕なわけですよ。それでね、描いてしまったものはしょうがない、どうやって宮さんに言うかですよね。もう仕方なく「宮さん、サギ男って良いキャラクターですよね」と言った。「モデルがいるんですか?」と訊ねると「いないよ!」と宮さんは答えた。そのもの言い、すごかったですよ。「いない、いない。いないよ!鈴木さんじゃないよ!」と。これがね、宮崎駿なんです。
実際、本編中で眞人を塔にいざなう姿は宮崎駿に映画を作らせようとする鈴木敏夫の姿を想起されるし、インコに食われそうになる眞人を救う姿や泥水をかぶる姿には「クリエーターとしての宮崎駿を世間の批判や金の亡者から守っている鈴木敏夫の姿」が投影されていると見ることができるだろう。
しかし、スタジオジブリを運営したり、宮崎駿や高畑勲といった優れたクリエーターといっしょに仕事するというのは並大抵なことではなく、尋常ならざる決断が迫られるわけである。
今回はその「決断」の中から、ほぼ「サギ」と言いたくなるようなものを紹介する。以下の文章で紹介する逸話だけでも、鈴木敏夫が「サギ男」として登場したことに納得できるのではないだろうか(なお、作品全体のあらすじや、大伯父・父・母の象徴、インコとペリカンの謎など、他の考察については「『君たちはどう生きるか』あらすじ・考察まとめ」で解説している)。
この記事の内容を、AIが対話形式(ラジオ形式)で分かりやすく解説してくれます。
-
鈴木敏夫「サギ列伝」―大胆な嘘と強行策が支えたジブリ史
ナウシカ五〇万部の虚報、未着色シーンの未説明、公開日偽装ポスター、タイトル強行公開など、鈴木敏夫が興行と制作を成立させるために放った一連の「ハッタリ」を振り返る。 -
「千と千尋」DVD赤み騒動―“仕様”とされた色調変更の余波
2002年発売DVDの赤みがかった映像は「千尋の心情表現」という公式説明で交換対応等はなされず、視聴者の混乱と訴訟を招いた。
青サギ(サギ男)のモデル鈴木敏夫のおもしろ「サギ」列伝
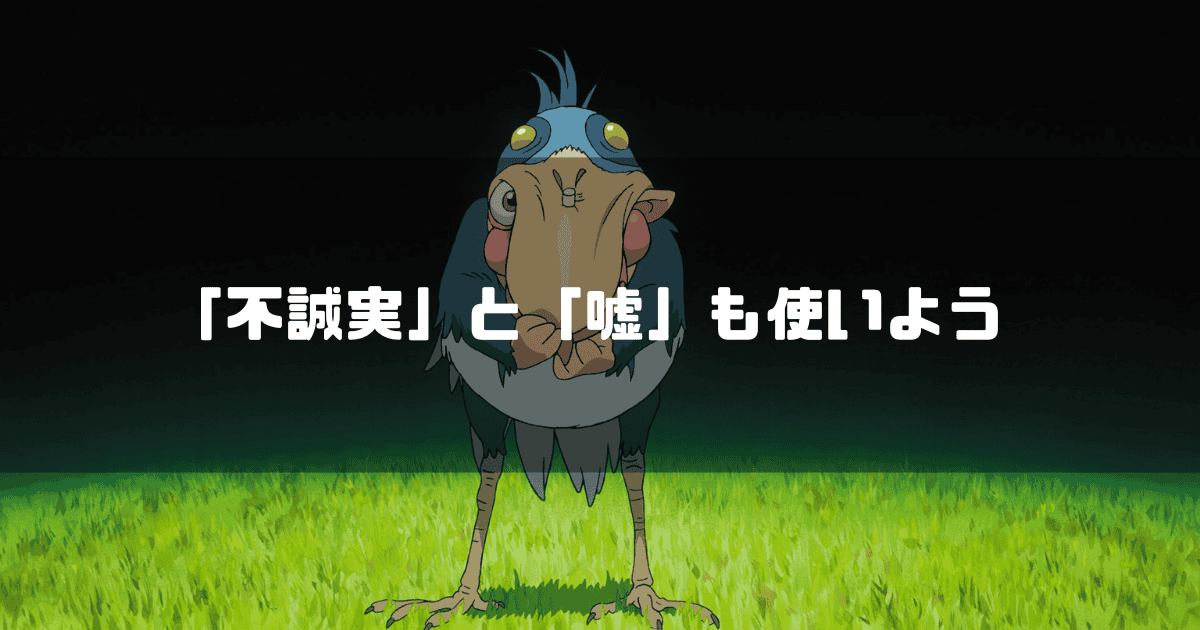
「風の谷のナウシカ」の原作漫画は50万部売れているという大嘘
鈴木敏夫は大学を卒業した1972年に徳間書店に入社。始めは「週刊アサヒ芸能」を配属されていたが、1978年の春から「アニメージュ」の創刊に深く関わることになる。
その折、「太陽の王子ホルスの大冒険(1968年公開)」の演出をしていた高畑勲に取材依頼をするのだが、電話口で1時間理由を述べられた挙げ句に断られ、電話を代わった宮崎駿にも30分もかけて断られことになる。なんともしんどい話だが、これが運命のファーストコンタクトとなった。
その後、「ルパン三世 カリオストロの城」、「じゃりン子チエ」の取材などを通して、鈴木敏夫は宮崎駿、高畑勲らと親交を深めていくことになる。
原作が必要なら作れば良い
徳間書店の社長であった徳間康快の旗振りに応じる形で、1981年に、鈴木敏夫は宮崎駿と相談して「戦国魔城」というタイトルの映画の企画を提案したのだが、残念ながら没になってしまう。
しかしそのボツ理由が「原作がない」というものだった。企画会議に大映(徳間グループの映画会社)の人にも「原作がないものを映画にして当たるわけがない」と言われてしまっただが、鈴木敏夫がそれを宮崎駿に伝えると「それなら原作を描いてしまいましょう」という反応をもらい、漫画「風の谷のナウシカ」の執筆が始まることになった(連載は「アニメージュ」)。
この辺もすごいよね。私なら原作を作るのではなくて原作を探そうとすると思うが、「ないものを作る」という判断が大事であったということになる。宮崎駿が漫画を描きたがっていたということもあったかも知れないが。
「風の谷のナウシカ」の映画化を決めた50万部の大嘘
上述のように「原作作っちゃえばいいじゃん作戦」が始まったわけだが、もちろん原作があればよいというものではない。「興行」ということを考えれば、その原作にどれほどの人気があるのかを考えるのは普通のことである。
著書「仕事道楽」の中で鈴木敏夫は以下のように語っている:
『ナウシカ』の映画化案が浮上したとき、博報堂から原作本の部数を聞かれた。実際は五万部だったんですが、一瞬逡巡して「五〇万部」と言ったんです。五万部では映画化を渋るかもしれないという考えが頭をよぎったんです。はっきり数字を誤魔化してますから、こういう嘘はあとに残る。
結果的に我々は「風の谷のナウシカ」という映画を観ることができたわけなので、鈴木敏夫の嘘が我々消費者に対して大きな恩恵を与えた事になる。
しかも、「風の谷のナウシカ」は興行的に大成功を収めており、「ジブリの仲間たち(PR)」によると配給収入は7億4000万円であった(映画館の入場者が払った総額である興行収入から映画館の取り分を除いたもの)。
結果として監督であった宮崎駿の元には大金が転がり込むことになるのだが、これにも鈴木敏夫が関わっている。「ジブリの教科書2 天空の城ラピュタ(PR)」で鈴木敏夫は以下のように語っている:
じつは『ナウシカ』を作る時、僕は宮崎駿という監督に映画の興行収入その他のものも含めて利益配分があるように契約書を作っておいた。
~中略(「職務著作(wiki)」の話がなされてる)~
僕は出版社の人間だったので直鎖物に対する敬意がありそれは守りたかった。作った人がどういう扱いをされているかも知っていたので、ちょっと勉強して、この機会に監督個人の著作権を発生させることにしてあったんです。
そして、この大金が宮崎駿を苦しめつつも、次なる傑作「天空の城ラピュタ」を生み出すことになる。
お金がなければ映画を作れば良いー宮崎駿の無限地獄の始まりー
「風の谷のナウシカ」で思わぬ大金を得た宮崎駿は「柳川堀割物語」に投入することを決めた。
「柳川堀割物語」は高畑勲が監督した実写ドキュメンタリー作品であり、福岡県柳川市の水路である「割堀」の荒廃の歴史とそれを復興する地域住民の懸命な努力を描くドキュメンタリー作品である。
ところが、「風の谷のナウシカ」のお陰で手に入れたはずの大金は底をついてしまう(参考:柳川堀割物語|地ムービー!映画情報)。
その状況で宮崎駿は鈴木敏夫に相談に来たのだが、「ジブリの教科書2 天空の城ラピュタ(PR)」において鈴木敏夫はその時の状況を以下のように語っている:
宮さんが僕のところに相談に来ました。
「時間もお金も費やしたけどどまだできない。僕の家はボロ家だけれど、家を抵当に入れてまで映画を作ろうとは思わない。鈴木さん、なにか知恵はないものだろうか。」
僕は即答しました。
大変だけどもう一本映画を作りませんか。そうすりゃなんとかなりますから。
引用した同じ文章の中で「その場でわずか五分で。『天空の城ラピュタ』の内用を全部喋ったんす。」と語られている。
ここで問題にすべきことは「何故、映画をもう一本つくることが問題解決になるか」ということだが、この不可思議な現象の発生は映画に限ったことではない。
つまり、あることをなそうとしたときに集めたお金で黒字になることなどほとんどないわけで、結果として生じた赤字は別の事業のために集めたお金で補填することになるだろう。
自転車操業といえば聞こえが悪いが、事業拡大とはどうものである。ずっと黒字の事業拡大などありえない…そうだよね?
したがって、鈴木敏夫の発言は「詐欺」とは言えない。しかし、宮崎駿を作品制作の無限地獄に導いたという観点では「サギ」と言えるだろう。「君たちはどう生きるか」の青サギが眞人を「大叔父の塔」に導いている姿はまさに「もう一本映画を作りませんか」と宮崎駿に語った鈴木敏夫の姿が重なるのではないだろうか。
未完ではなく演出である-「火垂るの墓」の未着色シーンに関するハッタリ-
少々時代は飛んで、スタジオジブリが設立され、「天空の城ラピュタ」も公開された状況。
ジブリでは「となりのトトロ」と「火垂るの墓」の制作が進んでいた。
ところが、「火垂るの墓」の制作は遅々として進まない。最終的には高畑勲の2つのシーンを塗らないままで公開という要求に応じる形になり、実は公開当時の「火垂るの墓」には未着色のシーンがあった。そのうえで、鈴木敏夫は「ジブリの教科書4 火垂るの墓(PR)」で以下のように語っている:
結局、一九八八年四月に公開さた時点では、二か所の色塗りが間に合わず、シロのままになりました。関係者の一人として、もちろん忸怩たるものがありましたが、表向きにはこれが未完成品であるということは一切、言いませんでした。「ちゃんと言うべきだ」という人もいましたが、説明すれば説明するほど話がややこしくなるから、「こういう時はだまってりゃいいんだ」と腹を括っていました。
未着色のままで公開されたシーンが清太がトマトを盗むシーンであったがゆえに、それを演出と捉えてくれた人が多かったようで、鈴木敏夫の「説明しない」という作戦は見事にハマって未完成品とは気づかれなかったようである。
鈴木敏夫の「説明しない」という判断は、観客に対して不誠実ではあるのだが、結果としての顧客満足度は維持あるいは上がったことになる。
「不誠実さも使いよう」ということだろう。商売とは誠に難しいものである。
「火垂るの墓」は最終的に2つのシーンの色を塗らないままで公開されたのだが、ここに至るまでの高畑勲、プロデューサーの原透、そして鈴木敏夫の攻防戦は苛烈なもので、高畑勲は「公開を延期してください」の一点張りだった。
この辺の攻防戦も「ジブリの教科書4 火垂るの墓(PR)」に詳しく記述されている。とにかく高畑勲の質にこだわる態度は極めて強固なものであり、高畑勲と共に仕事をしたプロデューサーたちはこの態度に困り続けることになる。
高畑勲を騙すためだけのポスターを作るー公開日を死守するための奇策ー
上で述べたように「火垂るの墓」の制作スケジュールは遅れに遅れたのだが、実はその次の作品である「おもいでぽろぽろ」の制作スケジュールも遅れることになった。
そのような状況下、プロデューサーを務めた宮崎駿が、高畑勲を始めとするスタッフを集めて「万が一この映画が公開に間に合わなかったら、お蔵入りにする。不完全な形での上映は絶対にしない」と大演説を行う。それがきっかけとなり「おもいでぽろぽろ」の制作はなんとか公開日に間に合った(参考:「アニメージュとジブリ展」の監修・高橋望が語る「鈴木敏夫の編集者としてのすごさ」と「高畑勲と宮崎駿の絆」)
「平成狸合戦ぽんぽこ」の制作スケジュールも同様に遅れることが予想されるわけだが、プロデューサーであった鈴木敏夫は先んじて手を打つ。「ジブリの教科書8 平成狸合戦ぽんぽこ(PR)」の中で以下のように語っている:
毎回、間に合う、間に合わないで冷や汗をかき続けてきて、僕も流石に学習しています。今回はちょっと作を弄しました。公開予定は一九九四年の夏だったんですが、サバを読んで、高畑さんには「春公開です」と伝えておいたのです。しかも、念には念を入れて「春公開」という文字を入れたポスターまで作り、配給の東宝の人たちにも口裏を合わせてもらいました。
結果として偽の公開日である「春」に公開が間に合わないことが確定的になったタイミングで、鈴木敏夫は高畑勲に「夏公開に延期します」と伝えた。
しかし、これで状況が収束してくれないのが高畑勲であり、制作スケジュールは再び遅れ始め夏公開も危ぶまれる事態に陥る。
ただし、今回は高畑勲も一度公開を延期している(してないけど)という負い目があったのか、鈴木敏夫が提案した「絵コンテの修正による時間の短縮」に応じる形となり、最終的には絵コンテの終盤を変更し10分もの削減に成功し、予定通りの公開にこぎつける。
「もののけ姫」というタイトルを勝手に公開ー失われた「アシタカせっ記」ー
映画「もののけ姫」の宣伝が始まる頃、宮崎駿から鈴木敏夫に映画のタイトルを「アシタカせっ記(『せつ』は本来宮崎駿による造字が使われる)」に変更しようと提案される。
しかし、鈴木敏夫は「もののけ姫」というタイトルが持つインパクトを考えるとどうしても譲れない。そこで鈴木敏夫は強硬策に出る。そのことについて「仕事道楽(PR)」の中で以下のように語っている:
意見が対立したままだったんですが、ここでぼくは、実力行使で解決しちゃいました。彼は特報とか予告編とかにまったく興味を示しませんから、日本テレビで特報第一弾というとき、「もののけ姫」のタイトルを出しちゃったんです。
この作戦に対して宮崎駿が同反応したかが気になるところだが、その反応は意外にそっけないもので「タイトルを出しちゃったんですか?」と聞いて鈴木敏夫が「出しました」と答えると、呆れた顔で自分のでデスクに戻っていった、というものだった。
なかなかに強引な作戦だったが、結果として「もののけ姫」は興行収入193億円を記録したわけだから鈴木敏夫の判断は正しかったということになるだろう。
「ゲド戦記」のエンドロールでの「サギ」未遂
映画「ゲド戦記」は宮崎駿の長男である宮崎吾朗の監督作品である。当時も宮崎駿の長男の作品であるということで非常に話題になっていたことを覚えているし、私も強く興味を持った。
アニメーションの世界にいなかった宮崎吾朗を抜擢したのは鈴木敏夫の判断であったし、「話題性」としては極めて十分である。
宣伝戦略として「宮崎駿」の名前は使わないという方針だった鈴木敏夫だが、エンドクレジットについて「世界一早い『ゲド戦記』インタビュー(完全版)」で以下のように語っている:
悩んでいます。苦し紛れに珍案奇案も考えました。「父 宮崎駿」とか(笑)。だって「アドバイザー」とかもっともらしいこと言っても仕方ないでしょう。あえてもう一つ候補があるとすれば「ゴッドファーザー 宮崎駿」。
実際にこの案は採用されないわけだが、こういうことを考えることそのものが「サギ男」としての鈴木敏夫らしさというものであろう。
以上が個人的に面白いと思った「鈴木敏夫の『サギ』列伝」でございます。細かいことも含めればもう少しあったような気もしますし、公に語られていないことも多いことでしょう。
また、私は鈴木敏夫という人物を遠くから見る立場なので「おもしろ『サギ』列伝」として紹介することができたが、近くで関係を持った人の中には強烈な嫌悪感を表明する人もいる。例えばアニメーション監督の北久保弘之さんは以下のようなXのポストをしている:
俺が鈴木敏夫を嫌いな理由はシンプルな二点。「他人の権威を傘にきて、人を見下して底の浅い説教モードに入る」事と「スタッフもお客さんも含め、その場を取り繕う為なら平気で嘘を吐く」事だなぁ。前者はまだ我慢する事も出来るけど、後者は救いようが無い。
— 佐倉 大 (北久保弘之) (@LawofGreen) September 15, 2012
我々は遠くから鈴木敏夫の仕事の「結果」を享受するだけで終わるので大した問題にはならないが、近くにいた人たちには様々な思いがあるのだろう。
ただ、かつて、「遠く」とも行っていられない事態が発せししており私もその当事者の一人となっていた。この記事はその思い出話で締めくくろうと思う。
「千と千尋の神隠し」のDVD色調問題ーあの夏君は、赤かったー
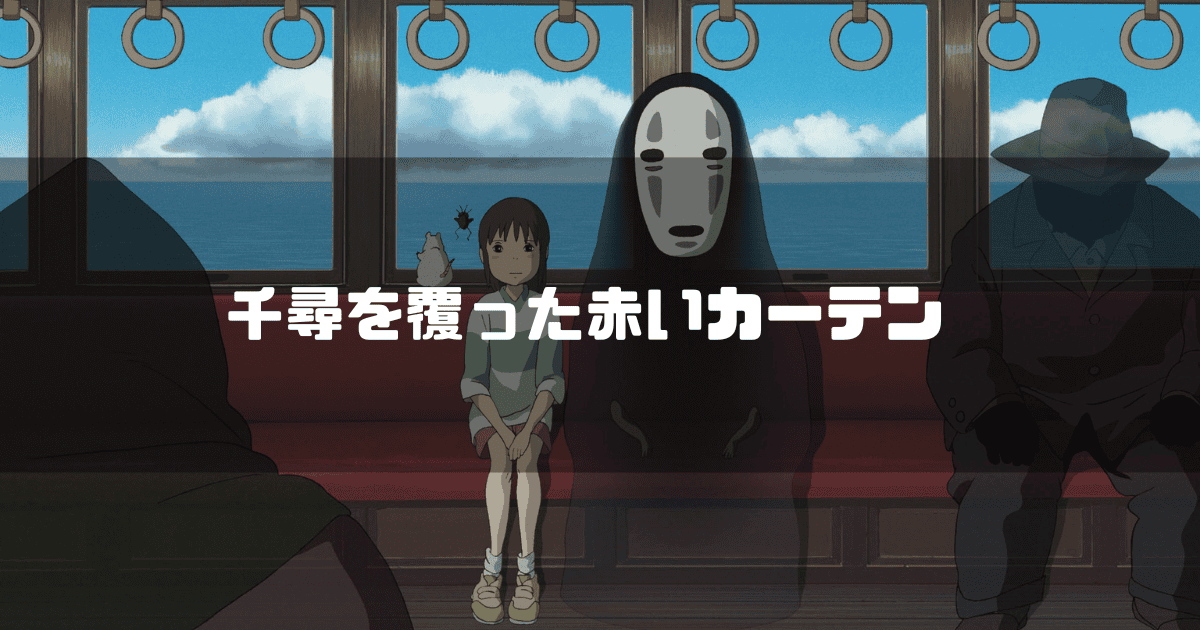
宮崎駿監督作品「千と千尋の神隠し」は2001年7月8日に公開された。そしてその翌年の2002年7月19日にはブエナ・ビスタ・ホームエンターテイメントからDVDが発売されている。
当時子供だった私はTSUTAYAでそのDVDをレンタルしるんるんダンスで視聴を開始した。しかし、本編が始まると何かがおかしい。一緒に見ていた兄の口から我々の違和感の正体が語られた。
「・・・赤いよな」
当時発売されたDVDの映像は実際に赤みがかっており、実は訴訟問題にも発展している。この件に関しては以下のブログ記事に詳しくかつ簡潔にまとめられているので参照していただければ何が起こっていたのかよく分かると思う:
さて、そんな事になっていると走らない当時子供だった我々が出した結論は「たぶんPS2だからだろう」だった。
当時我が家には2000年に発売されたPlayStation2があり、ゲーム機としても活躍していたのだが、それ以上にDVD最盛期としても活躍していた。おそらく他のご家庭でも状況は同じだったのではないだろうか。
しかし、世の中には専用のDVD再生機が存在しているわけで、「おまけみたいな機能で視聴しているからこうなるのだろう」と自分たちを納得させたわけである。
で、この件に関する鈴木敏夫の公式見解は月刊誌『HiVi』2002年11月号(2002年10月発売)でのインタビューで語られている。結論から言うと「仕様です」ということだった。
つまり、赤みがかってはいるのだがそれはミスではなくこちらが意図したことであり、商品として問題はないということである。赤みがかっている理由としては「千尋の心情を表現するために敢えて色調を変更した」と語っている。
ただ、これにどう考えてみても問題が残るだろう。つまり、意図したものならそれは強く強調して事前に知らせるべきだし、実はミスだったのならそのように言うべきである。
もちろん後者の立場に立った場合、商品の交換、返品(したがって返金)という問題が発生してしまうのでどうしてもそれは避けたいだろう。真実がどうであれ、「仕様です」という鈴木敏夫の態度以外に道はなかったものと思う。しかもあれが「仕様」であったことを証明するように、金曜ロードショーで放送されたものも赤みがかっていたという。
この件に関して先ほどポストを引用した北久保さんがこれまたXにポストしている:
その一手間をキチンとやらなかったせいで、何でお金を払ってDVDを買ったお客さんが「色が赤い」状態で我慢しなきゃならんのか。「◯◯ケルビンが〜」とか元データの数値を拾うだけで「映画と同じ発色になる」訳ないじゃんか。で、鈴木敏夫氏はあちこちで専門知識が無い言い訳をするのだが(続く
— 佐倉 大 (北久保弘之) (@LawofGreen) May 2, 2015
専門家の意見なので我々の勝手な想像よりは説得力があるが、結局本当のところはわからない。
そんでもって、事態の発生は2002年という「大昔」の話となってしまい、今となってはある種の思い出として消化されてしまっているし、「俺はあの夏赤い『千尋』を見た!」という奇妙な自負まで醸し出されてしまっているしまつである。
当時まだ子供で「消費者意識」というものがなかったことも原因かも知れないが、「全ては主観性を失って、歴史的遠近法の彼方で古典となっていく」のである。
ちなみに、現在発売されているBlu-rayやDVDは赤みがかっているということはない。
実は「君たちはどう生きるか」のUHD Blu-rayも交換騒動が起こっている:『君たちはどう生きるか』 4K UHD Dolby Vision映像不備に関するお詫びとお知らせ。
交換理由は「Dolby Visionの映像を視聴環境に応じて正しく再生するデータの情報に誤りがあった」というもので、「千と千尋の神隠し」のDVDの赤みと違ってもしかしたら言わなきゃわからないものだったのかも知れないが、今回はきちんと交換対応ということだった。実は私も交換してもらった。
この記事では青サギのモデルである鈴木敏夫氏の「サギ」列伝についてまとめたが、本作の詳細なあらすじや、もう一つの大きな謎である「大伯父や謎の隕石は何を象徴するのか」など、作品全体の解説については「『君たちはどう生きるか』あらすじ・考察まとめ」で網羅している。
この記事で使用した画像は「スタジオジブリ作品静止画」の画像です。
この記事を書いた人
最新記事
- 2025年12月21日
【ホーム・アローン2】雑学&豆知識集-裏話や制作秘話を紹介- - 2025年12月19日
【ホーム・アローン(1作目)】雑学&豆知識集-裏話や制作秘話を紹介- - 2025年12月18日
「未来のミライ」と「となりのトトロ」に見る共通点 -孤独が生んだ”夢だけど夢じゃなかった”世界- - 2025年12月14日
「未来のミライ」のあらすじ(ネタバレあり)-結末までのストーリーを解説・考察- - 2025年11月30日
「時をかける少女(2006年)」のあらすじ(ネタバレあり)と解説・考察-絵画に込められた物語のメッセージ-